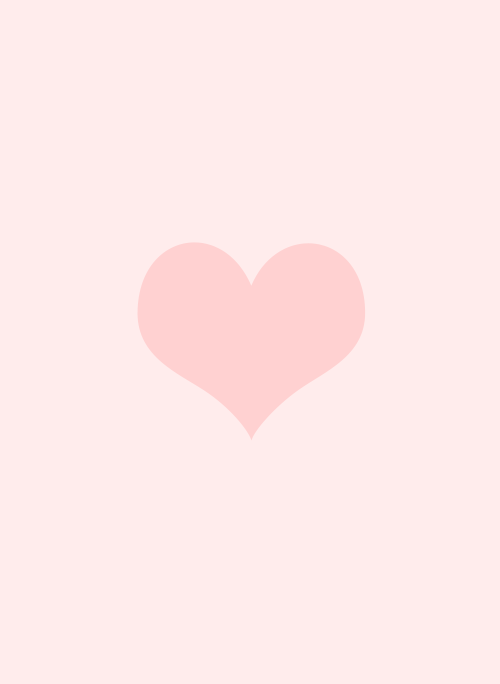罪悪感から涙が溢れてそれを零しながら繰り返し謝るあたしの寝転んでいる身体をよいしょ。そう言って軽々と座っているのに道留君は抱き上げて。
おでこに乗っていた氷の袋はそこからソファーに落っこち、抱き上げたあたしの身体を自分と向き合うように膝の上に乗っければ。
「泣かないのー」
眉を下げて、零れる涙を綺麗な指が拭っていく。
「言っちゃったのはしょうがないからね?」
膝の上に乗っけられたから背の高い道留君とは殆ど同じ目線になって。
そう言い、道留君は自分のその整いすぎて直視すればするほど目眩を引き起こしてしまいそうになる顔をあたしの眼前まで持ってきて、慰めるようにチュッと瞼に唇を一瞬だけくっ付けると。
「もう俺の素顔は他の人に言っちゃダメだよ?あとそれと――…」
俺と壱翔がここに出入りしてるのもナイショね?
色っぽく血色のいい唇の前に人差し指を立ててパチン、と不適にウインクをしたんだ。
――…結局、どうして道留君(と巳陵壱翔)が生徒会役員じゃないのにこの生徒会室を使えるのか。
その理由は解決されず、それを知るのはまた少し未来になってしまって胸にモヤモヤを残したまま。
今はただ、目の前の妖艶な王子様もといあたしの秘密な恋人に真っ赤になって心臓を煩く鳴らすことしか出来ないでいた。