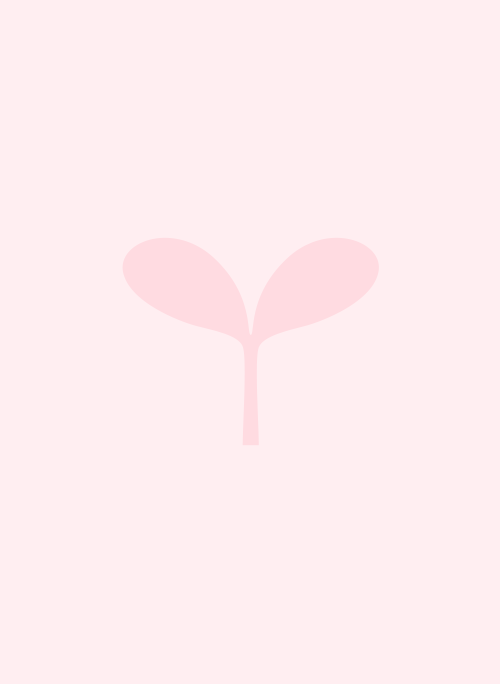家は一階建てで、しかし一人で住むには少し広い家だった。
それでもなんの考えもなく家を出た僕にはこの家の存在はありがたく、一人暮らして行くのだと言う自覚に、板張りの廊下を拭く僕の胸中は浮足立つようである。
家の端々に郷愁の感覚は感じられるも、どうやら具体的に何かをしたような記憶は湧き出る事がないようで、それはなんだか蓋の閉じられた箱の外観だけを懐かしむ感覚に似ていた。
簡素な掃除を終えると、書生の頃から交流のあった文学誌の編集者をする友人に手紙をしたため、それを出すのもかねて近所を散策しに外出した。
吹く風に冷えを感じるようになった近頃の空と目新しくも懐かしい町の景色を眺めながら気になっていた件の図書館へ足を運ぶ。
ザリザリと下駄にひっかかる小石の音の他、目立って耳に入る音はない。
何か羽織ってくればよかったと少し後悔する。
この時期に厚手とは言えシャツ一枚は少々冷えた。
見覚えのある銀杏の木のある門から覗くと、白を基調とした少し大きめの石造りの二階建ては、木目のよく出た渋柿色の扉を片側だけ開け、「開館」と墨で書かれた札が立てかけてあるのみで、じっと沈黙していた。
それでもなんの考えもなく家を出た僕にはこの家の存在はありがたく、一人暮らして行くのだと言う自覚に、板張りの廊下を拭く僕の胸中は浮足立つようである。
家の端々に郷愁の感覚は感じられるも、どうやら具体的に何かをしたような記憶は湧き出る事がないようで、それはなんだか蓋の閉じられた箱の外観だけを懐かしむ感覚に似ていた。
簡素な掃除を終えると、書生の頃から交流のあった文学誌の編集者をする友人に手紙をしたため、それを出すのもかねて近所を散策しに外出した。
吹く風に冷えを感じるようになった近頃の空と目新しくも懐かしい町の景色を眺めながら気になっていた件の図書館へ足を運ぶ。
ザリザリと下駄にひっかかる小石の音の他、目立って耳に入る音はない。
何か羽織ってくればよかったと少し後悔する。
この時期に厚手とは言えシャツ一枚は少々冷えた。
見覚えのある銀杏の木のある門から覗くと、白を基調とした少し大きめの石造りの二階建ては、木目のよく出た渋柿色の扉を片側だけ開け、「開館」と墨で書かれた札が立てかけてあるのみで、じっと沈黙していた。