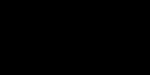「……んっ」
首筋に唇を押し付けられたように作られた赤いキスマークは、きっとこれからも消えて無くなることはないのだろう。
「梢、愛してる」
「うん……」
そして私たちはその日の夜、最高に甘い時間を過ごした。
この時間はずっと続けばいいのにと、ベッドの中で奏多と結ばれながら思っていた。
―――――…
首筋に唇を押し付けられたように作られた赤いキスマークは、きっとこれからも消えて無くなることはないのだろう。
「梢、愛してる」
「うん……」
そして私たちはその日の夜、最高に甘い時間を過ごした。
この時間はずっと続けばいいのにと、ベッドの中で奏多と結ばれながら思っていた。
―――――…