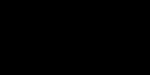「……梢」
泣いている私を、奏多はそっと抱き締めた。
「……ふっ……かな、たあ……」
「よしよし。大丈夫だから」
「ふぇーん……」
しばらくの間、私は奏多の腕の中で泣いていた。
声が枯れるまで―――
そんな私を、奏多はずっと抱き締めてくれていた。
泣いている私を、奏多はそっと抱き締めた。
「……ふっ……かな、たあ……」
「よしよし。大丈夫だから」
「ふぇーん……」
しばらくの間、私は奏多の腕の中で泣いていた。
声が枯れるまで―――
そんな私を、奏多はずっと抱き締めてくれていた。