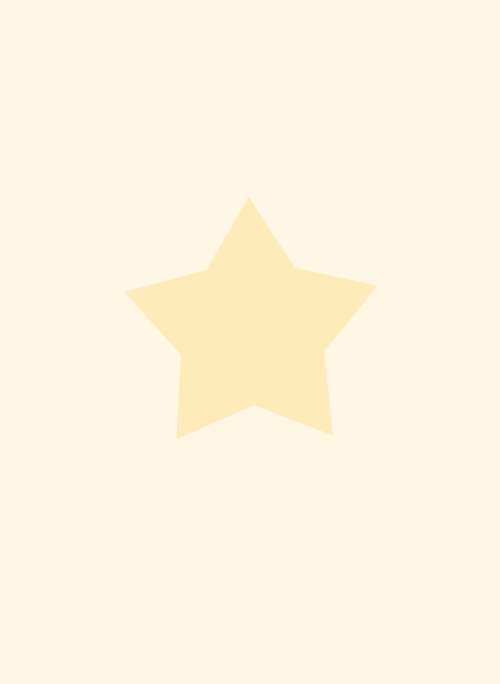「じゃあ昼だけなら」
思わずそう言っていたのは私自身疲れていたからかもしれない。
まさかの言葉に西村さんの方が、一瞬「え?」と、驚いた顔をする。
風俗を上がり、飛び出した夜の街で私はいつも一人だった。
一見華やかできらびやかな世界にいても、寄って来るのは火遊びを望む男ばかり。
割り切れれば良かったかも知れない。
けれど、そんな男相手に本気でぶつかった私はもれなく途中で捨てられた。
いや、実のところは私自身が本物の愛を信じられていなかったのかもしれない。
それでも、どこかに一つぐらいは落ちているのだと、希望を捨てたくなかっただけ。