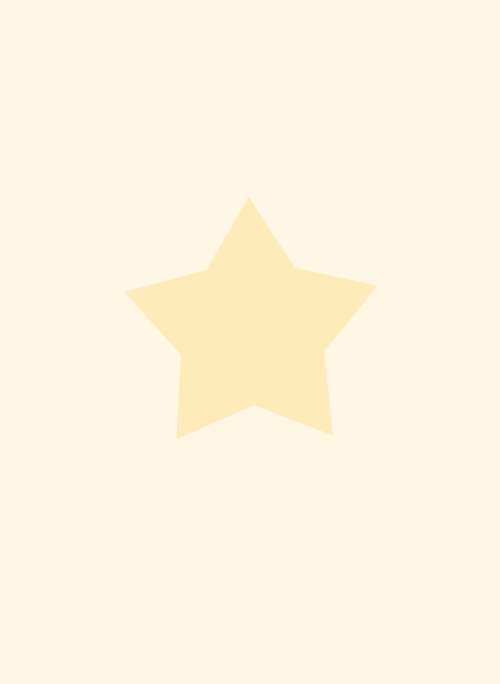出来るだけ動揺しないように、平静を装った私へアキちゃんは財布から何かを取り出した。
「ほら、登録証」
それは一枚のカードで、私にはよく見覚えがあるものだった。
夜働いているキャバクラで仲良くしている女の子、その子が持っているのと同じカード。
つまり……。
「韓国人なんだ」
その言葉を聞くのと、自分の中でかっちり符号が合ったのは同じ瞬間だった。
それはもちろん嫌だとかそういう感情じゃなくて、単純に結構いるもんなんだと感じただけ。
友達にしたってバリバリの関西弁。
おそらく親やその上の世代が韓国人であるだろう二人。
わざわざこうして話すと言う事は、私の知らない所で嫌な思いをした事があったのかもしれないけれど。