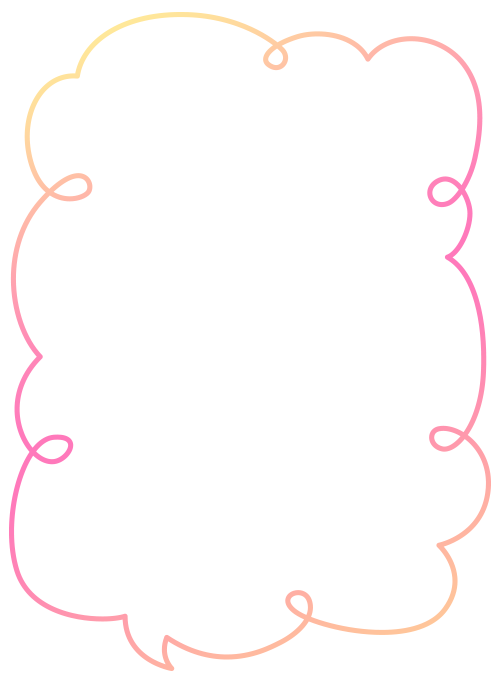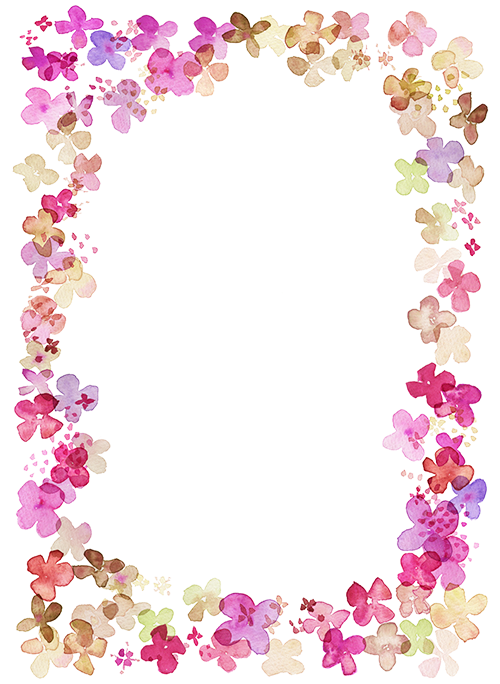「先輩が謝る必要ないですよ。僕が勝手に待っていただけですから」
前髪から滴り落ちる雨の滴がユーヤの頬を濡らす。
茶色くいつも綺麗にセットされている髪はシャンプーをした後のように濡れていて。
その髪を少しだけウザそうにかき上げるユーヤから目が離せなかった。
ユーヤが泣いているような気がしたから。
顔は笑っているのに心が涙を流しているようで。
「……ユーヤ……」
あたしは思わずユーヤの体をギュッと抱きしめた。
前髪から滴り落ちる雨の滴がユーヤの頬を濡らす。
茶色くいつも綺麗にセットされている髪はシャンプーをした後のように濡れていて。
その髪を少しだけウザそうにかき上げるユーヤから目が離せなかった。
ユーヤが泣いているような気がしたから。
顔は笑っているのに心が涙を流しているようで。
「……ユーヤ……」
あたしは思わずユーヤの体をギュッと抱きしめた。