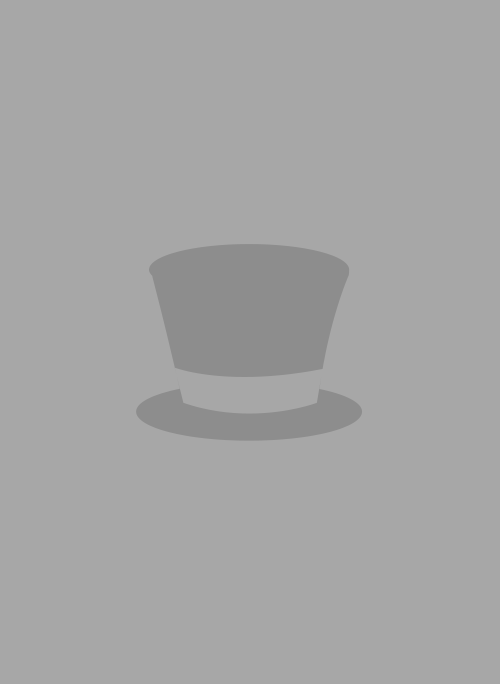「ああ。君もな」
「分かってるわ。……でも、休み明けって結構しんどいわね」
「君ぐらいの年だったらバリバリなのに」
「そんなことないわよ。あたしだって、もうオバサンなんだから」
千奈美がそう言って、照れたようにフワッと髪を掻き揚げる。
昨夜バスルームで使ったシャンプーとコンディショナーの香りが漂ってきた。
彼女はいつも香水を振っているらしく、脇からは甘い匂いがしていて、俺の鼻腔をくすぐる。
その匂いも瞬時にして消え、俺たちは互いに目指す方向へと歩き出した。
俺は会社へと向かい、千奈美は地下鉄の駅へと吸い込まれていく。
彼女はカバンに書類などをたくさん詰め込んでいるようだ。
俺も出社したら、目を通す書類がデスクに山積みされる。
慌てずに歩き出す。
「分かってるわ。……でも、休み明けって結構しんどいわね」
「君ぐらいの年だったらバリバリなのに」
「そんなことないわよ。あたしだって、もうオバサンなんだから」
千奈美がそう言って、照れたようにフワッと髪を掻き揚げる。
昨夜バスルームで使ったシャンプーとコンディショナーの香りが漂ってきた。
彼女はいつも香水を振っているらしく、脇からは甘い匂いがしていて、俺の鼻腔をくすぐる。
その匂いも瞬時にして消え、俺たちは互いに目指す方向へと歩き出した。
俺は会社へと向かい、千奈美は地下鉄の駅へと吸い込まれていく。
彼女はカバンに書類などをたくさん詰め込んでいるようだ。
俺も出社したら、目を通す書類がデスクに山積みされる。
慌てずに歩き出す。