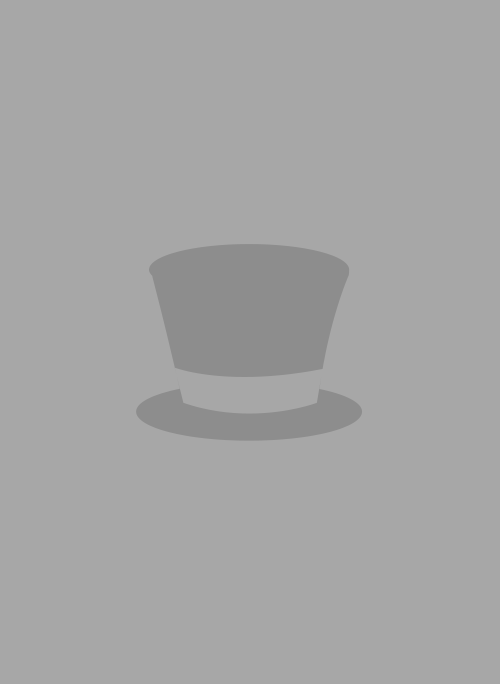これは一大改革になる。
おそらく大財閥の一人娘だった優紀子の葬儀には多くの業界関係者が訪れるだろう。
俺はその席上で芝居をしなければならない。
悲しみを装うというものだ。
これは簡単には出来ないのである。
だが、簡単に出来ないことほどやりがいがあるもので、俺は妻を失った哀れな男を演じきるつもりでいた。
葬儀が終わって、初七日や四十九日も通り過ぎた今年三月の半ばぐらいに、俺は千奈美と再婚する気でいる。
俺にとって彼女は新たなパートナーであり、またこれから先の人生を共に過ごす人間だ。
俺は千奈美がいつも付けている、あの甘い香水の香りを覚えている。
嗅覚にすっかり染み付いているようで、慣れっこになっていた。
定食を食べ終わって、食後のコーヒーを一杯頼む。
これからマンションまで歩いて帰るから、気付けの一杯だった。
おそらく大財閥の一人娘だった優紀子の葬儀には多くの業界関係者が訪れるだろう。
俺はその席上で芝居をしなければならない。
悲しみを装うというものだ。
これは簡単には出来ないのである。
だが、簡単に出来ないことほどやりがいがあるもので、俺は妻を失った哀れな男を演じきるつもりでいた。
葬儀が終わって、初七日や四十九日も通り過ぎた今年三月の半ばぐらいに、俺は千奈美と再婚する気でいる。
俺にとって彼女は新たなパートナーであり、またこれから先の人生を共に過ごす人間だ。
俺は千奈美がいつも付けている、あの甘い香水の香りを覚えている。
嗅覚にすっかり染み付いているようで、慣れっこになっていた。
定食を食べ終わって、食後のコーヒーを一杯頼む。
これからマンションまで歩いて帰るから、気付けの一杯だった。