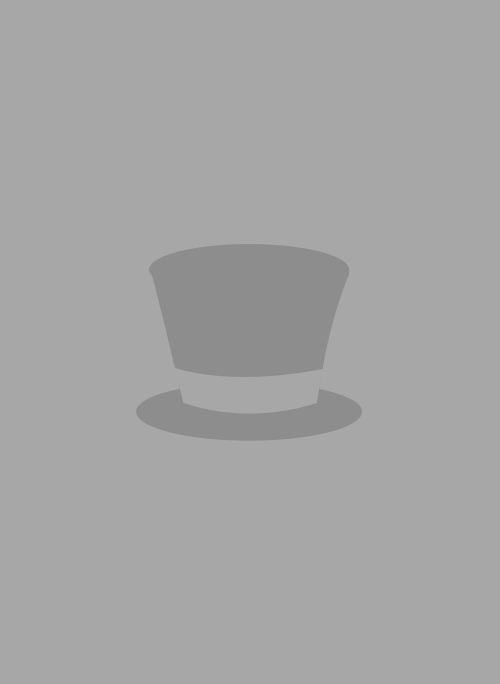21
僕に思わぬ電話が掛かってきたのは、その年の八月中旬だった。
そう、留学中の奈々からである。
彼女はロンドンにある賃貸アパートに住み、毎日大学や付属の図書館に通って、専門の勉強をしているようだ。
僕は充電器に差し込んでいたケータイが鳴り出したのを見て取り、
“もしかして奈々からかも”
と思いながら、フリップを開いてディスプレイを見つめる。
彼女のケータイの番号が明滅していた。
僕が迷わず出る。
「はい」
――ああ、駿一?
「おう、電話じゃ久しぶりだな」
――どう?元気してる?
僕に思わぬ電話が掛かってきたのは、その年の八月中旬だった。
そう、留学中の奈々からである。
彼女はロンドンにある賃貸アパートに住み、毎日大学や付属の図書館に通って、専門の勉強をしているようだ。
僕は充電器に差し込んでいたケータイが鳴り出したのを見て取り、
“もしかして奈々からかも”
と思いながら、フリップを開いてディスプレイを見つめる。
彼女のケータイの番号が明滅していた。
僕が迷わず出る。
「はい」
――ああ、駿一?
「おう、電話じゃ久しぶりだな」
――どう?元気してる?