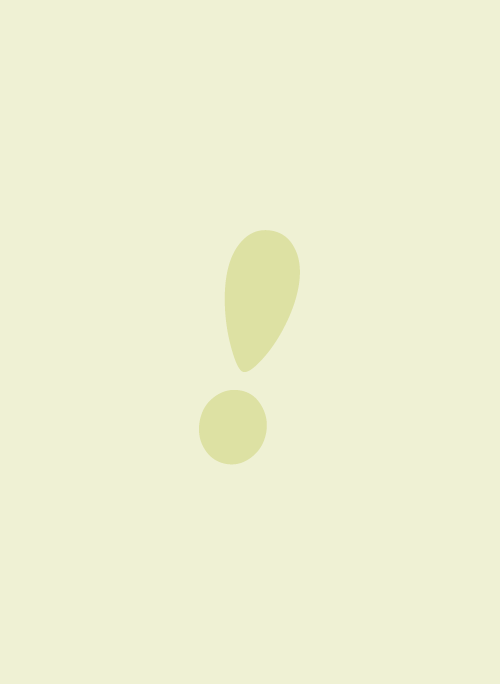幾斗は指先で私の涙を救いながら、話を続けていく。
「俺はその場から動くことも出来なかったよ。ドアが開いて、父さんに駆け寄ろうとしたとき、俺はそれすら許されなかった……」
「俺の手を引いたのは皇也さんだったよ────」
*****
「いや、嫌だ、はなせよ!父さん!父さん!!」
「車を回せ、直ぐに連れて帰る」
「はい、若頭」
「い゛やぁぁあ!父さん!母さん!」
がむしゃらに暴れ、俺の手を掴む大きな手から逃れようと必死だった。
「父さん!父さんッ!!」
俺のあまりの泣きように父さんは焦って近寄ろうとするが、俺の手を握る人の傍で控えていた人たちが父さんの前に立ちはだかる。
そして俺の手を握る人が静かに、でもとても低い声で口を開いた。
「あなたはこちらの要求を受け入れた。もうこの子の親権はあなたにはありません。今後一切、この子には近寄らないように…」
「そ、そんなッ」
「若頭、お車の準備が整いました」
「分かりました。さぁ、行きましょうか。今日でこことはさよならをしましょうね、幾斗くん」
その人の優しい声が怖くて、逆らうことは許さないと語っているような冷たく光る瞳に見つめられ、俺は声も出せなくなった。
「幾斗、幾斗!」
しかし父さんの声で、俺は再び父さんに向かって握られていない方の手を伸ばした。
「父さんッ!嫌、はなせ!はなしてよ」
しかし何を言っても俺の手その人から離されることはなかった。
「やだ!やめて!とらないで、俺から父さんと母さんをとらないでよ!」
そう叫んで、再び俺の手からその人の手を剥がそうと躍起になっていると、後ろから布で口と鼻を覆われた。
「ん゛ー、ん゛ッ!」
暴れようとした時には既に体は抱き込まれ、意識は朦朧としていた。
意識が無くなる寸前、誰かが小さく謝る声がした。