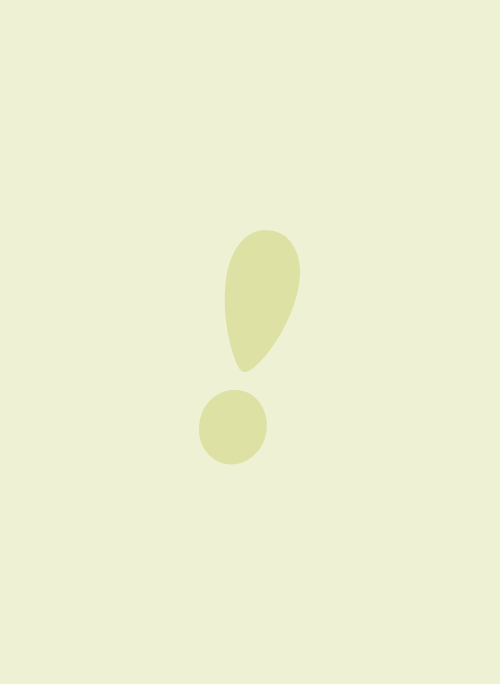そう……
分かってた……
私の顔を見るたび、あなたが一瞬苦しそうな顔をすることを。
それは未だ過去に囚われているから───
私と言うお兄ちゃんと結び付きのある存在は、幾斗を苦しめている。
「何があったかなんて、私には分からないし、この世界の事じゃ、今まで一般人だった私には想像すら出来ない……」
だから・・・──
いつかは話してもらう───
それがいつかは執着しない。私が生きているうちなら何時でも構わない。
でも、いつかは……
私は再び前を向いた。
「いつか幾斗が、お兄ちゃんを笑って思い出せる日が来たら、教えてよ」
後ろで幾斗が息を詰まらせたのを感じた。
「少しずつでいいから。大丈夫よ。私も幾斗も、生きてるんだから・・・」
私は振り向いて笑った。
「でも、約束して。お兄ちゃんの月命日は用事がない限り、一緒にここに来るって。お兄ちゃん、意外と寂しがり屋だから」
私は月日が経った墓石を撫でた。
私が幼い時に亡くなった両親のものだ。
10年以上の月日は、この墓石の風化で物語られている。
お兄ちゃんのも作るか、若桜さんに聞かれたが、私は両親のと一緒にしてもらった。やっぱ家族は一緒でなきゃね。
「お墓なんて、生きてる人の自己満足で、ここに来たってお兄ちゃんはいないって分かってる。けど……」
やっぱり縋ってしまうのが人と言うものだ。
お墓参りをして、魂を送ったつもりで、死者は成仏した事にしている。
そんなの誰にも分からないのに……───