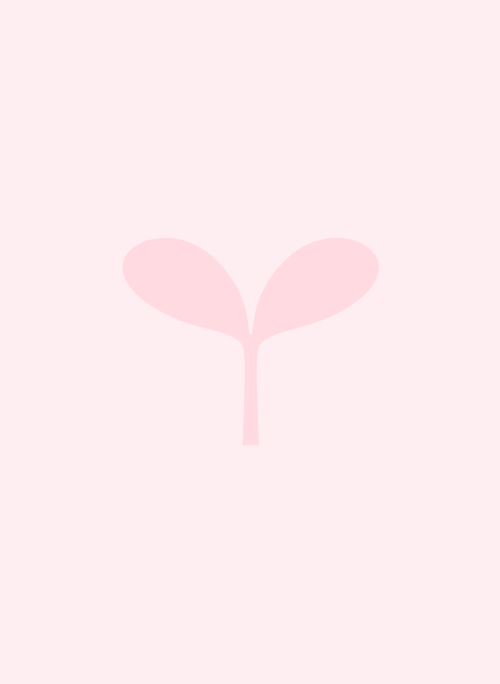わたしは、目を見開いて公平の横顔を見た。
真っ直ぐに前を見ている公平は、とても真剣な表情をしている。
――『愛する花嫁』
それが、何故わたしなのか。
ミサキがいないのだから、仕方ないのはわかる。
今、ミサキの変わりに公平の隣を歩けるのは、わたししかいない。
「おまえしかいないからさ」
ほらね。
「あの紙の指示を読んで、一番に浮かんだのはおまえだったから」
―――…っ
いつも、いつも、いつも、いつも、いつも。
どうしてわたしの心をそうやって揺るがすのか。
ミサキの名前を口にしないと思えば、急にわたしを突き放そうとしたり。
諦めようと思った時に、そうやって優しくしたり。
どうして公平は、わたしを離さないのだろう。