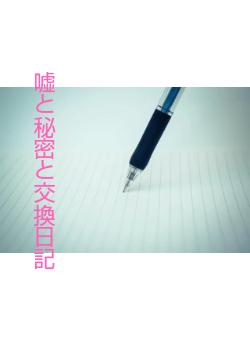バレー部の夏は厳しい。
野球部やサッカー部は、「おまえら、室内でいいよな」とか言うけど、
風の通り抜けにくい体育館のなかは、ほぼサウナ。
そんな場所で数時間体を動かせば、
顔は赤いし、汗で束なった前髪が、顔に貼りついて気持ち悪い。
蝉のうるささをBGMに、私たちは顧問の言葉を待っていた。
汗が全身を流れていく感覚が、どうにも不快で、ぼんやり眉をしかめる。
次の夏の大会は、私たち3年には学校生活最後の試合。
しかし、愛は絶望的だった。
前の大会中に捻挫をし、まだ治りきっていない。
それなのに、
それだからこそか、
メンバーのサポートを献身的にしてくれた。
そして、それは驚くほど、うまくいった。
もともと、プレイヤーとしては、決めを焦るワンマンな部分が目立つ選手だったが、
いざ、サポートに専念するとなると、
それこそが、本分であったかのように、
チームとしての集団を、
それぞれのプレイヤーを、
顧問と部員の調整を、
完璧といえるほどに、こなしてみせた。
おそらく、試合中のワンマンにも見えプレーは、回りのサポートをするための、空回りであったのだと、納得できた。
そして、今。
最後の、出場メンバー発表において、
一番、強く願っているのが、
愛だった。
でたいと、願っているのではない。
頑張ってきたメンバーが、
順当に報われる結果であることを、
必死に願っていた。
そして、そのメンバーの中には、
自分も含まれることも、
私は、薄々気づいていた。
愛から感じる、友情に心を震わされながらも、
一方で、
他人のためによくそんなに一生懸命になれるな、
と、冷ややかに呆れている自分がいることに、気づいた。
今まで、自己中だと思っていた相手が、実はとても面倒見がよい人間で、
今まで、友だち至上主義だと思っていた自分が、実は冷酷な生物であったことに、
この時、私は気づいてしまった。