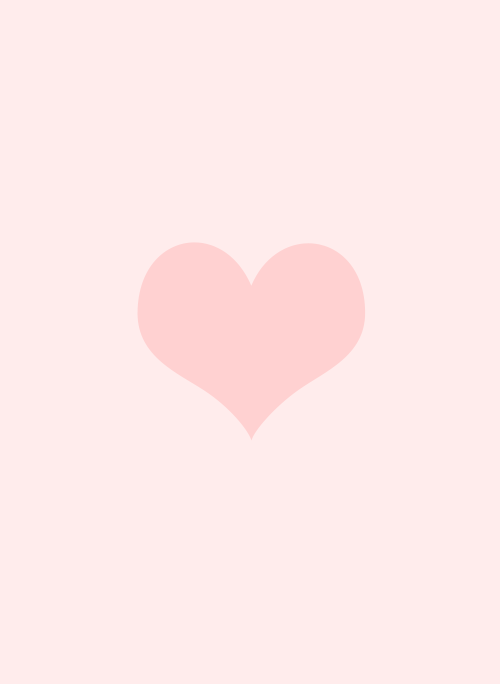視線を落とし、彼女の足に目を向ければ、伸縮性のある頑丈な包帯が巻かれ、しっかりと固定されていた。
「今は、痛くないの?」
「さっき、もらった炎症止めと鎮痛剤飲んできたから大丈夫。」
慈朗の問いに、陽路先輩はにこりと笑って答える。
そんな陽路先輩の左手にもふと目をやってみると、巻かれた包帯に血が滲んでるのが見えた。どうやら、せっかく治りかけていた手の傷もまた開いてしまったらしい。
絶対痛いだろうに、俺達に全くと言っていいほど、そんなことを気にもさせないよう振る舞う陽路先輩…。怪我した本人よりも、俺たちの方がツラくなってしまうのは、陽路先輩が俺たちに、気を回しすぎているからだろう。
彼女の気持ちは、彼女の中だけで葛藤してることに、俺はこのときから気づきかけていたのかもしれない。