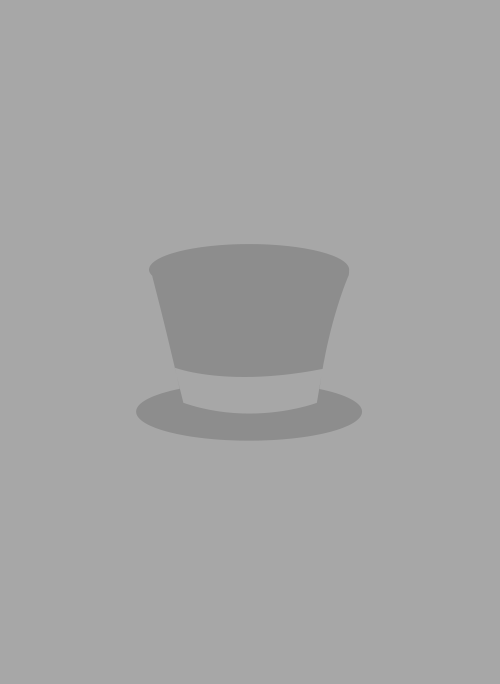それしか出来ないのだ。
今のあたしにとって。
人間というのはあの世までお金を持っていけるわけじゃないし、実際、あたしは喬の突然死で半ば頭がおかしくなりそうになっていた。
だが、まるで鋭利なナイフで抉(えぐ)られたように深い傷は、徐々にではあるが癒されつつある。
それは間違いない。
そしてあたしはたった一度、喬の葬儀の時に面識を持った遺族である実家のご両親に会って、あるものを託されていた。
それは紛れもなく彼の遺骨である。
サラサラとしたパウダー状の骨が小さなガラスのビンに入っていて、あたしはそれを受け取り、この骨を海辺で撒くことにした。
喬の死から丸三ヶ月が経った五月の中頃に、あたしは海開きが開かれた神奈川県の江ノ島に行く。
生前海が好きだと頻りに言っていた彼の遺骨をそこで散骨するつもりでいた。
今のあたしにとって。
人間というのはあの世までお金を持っていけるわけじゃないし、実際、あたしは喬の突然死で半ば頭がおかしくなりそうになっていた。
だが、まるで鋭利なナイフで抉(えぐ)られたように深い傷は、徐々にではあるが癒されつつある。
それは間違いない。
そしてあたしはたった一度、喬の葬儀の時に面識を持った遺族である実家のご両親に会って、あるものを託されていた。
それは紛れもなく彼の遺骨である。
サラサラとしたパウダー状の骨が小さなガラスのビンに入っていて、あたしはそれを受け取り、この骨を海辺で撒くことにした。
喬の死から丸三ヶ月が経った五月の中頃に、あたしは海開きが開かれた神奈川県の江ノ島に行く。
生前海が好きだと頻りに言っていた彼の遺骨をそこで散骨するつもりでいた。