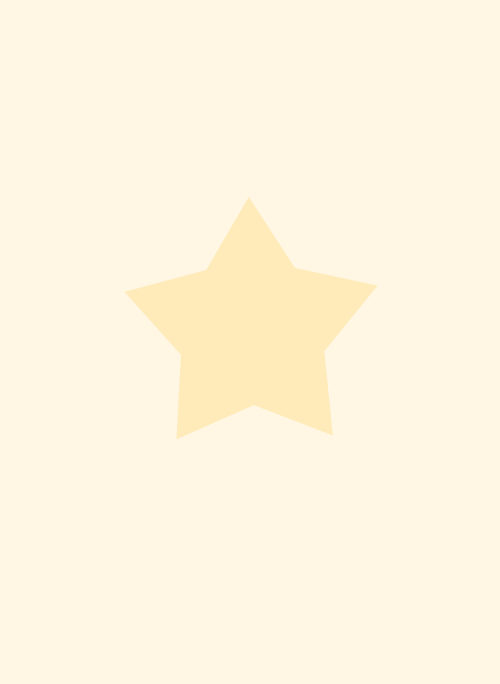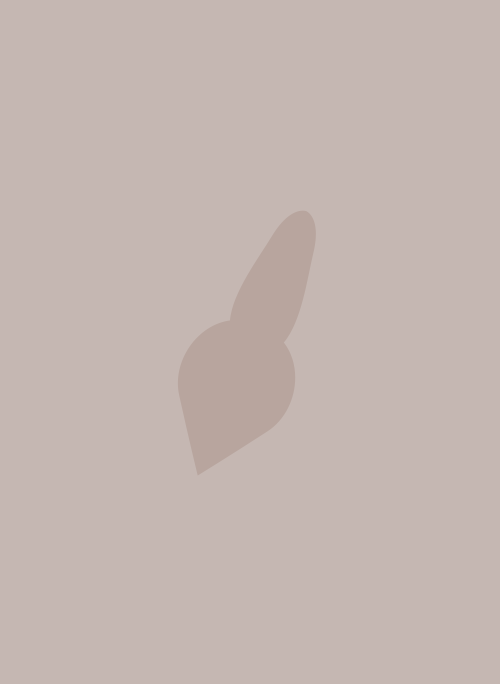すべてを喰らい尽くすかのように、
私の首に
むしゃぶりついた。
彼女の瞳の色を、もうしばらく
みていたかっただけ。
その日も私は夜の中を歩いていた。
人気のない道も、私にとっては歩きなれた土のかたまり。
ふと顔を上げると、前を猫が歩いていた。
闇のように黒い艶を持った毛並み。
鼻のさきが
手足のさきが
しっぽのさきが
白く抜かれていた。
そして私は路地を曲がった。
少女がひとり、立っていた。
彼女に見られた。
ちがう、か。
彼女を、見てしまったんだ。
白磁のようになめらかな肌
ちいさく慎ましやかに閉じられた、くちびる
その身を飾る髪は、蜘蛛の糸のように白く細く丈夫で、薄気味悪い。
そして、幼子のように愛らしい大きな眼。
それが湛えた色といったら!
愛情と憎悪が混在し、戸惑いと決意が揺らいで溶けた、
吐き気のするような黒。
少女は私に向かって駆け寄り、
私はなぜか少女を受け止めるかのように両手を広げる。
そして少女は私の首根っこにしがみつき、
慎ましやかに閉じていたはずのくちびるを大きく開け、
隠されていた犬歯で私の皮膚を食い破って、血液を啜った。
時が経ち。
ようやく離れた彼女は私の血で濡れたくちびるを、
生き物のような赤い舌で、ぺろりと舐めた。
私はなんの迷いもなく、彼女の腕を引き寄せ、
そのくちびるに自分のそれを重ねた。
存外に熱い口腔を舐めまわし、
少女の舌を探り、絡めて吸う。
彼女がそれに応え、私の中に蠢く舌を差し入れる。
歯列をなぞり、唾液を飲み乾して、
先の出来事よりもさらに陰惨で、長く、醜悪な事態は終わった。
「おもいだしたのか……?」
初めて聞いた少女の声は、
想像していたものよりも幾分か、
やわらかく、いとおしく。
「なにを?」
少女が落胆を隠せない素振りで俯くのを、
私はなぜか
ひどく愉しげに
見ていた。
.