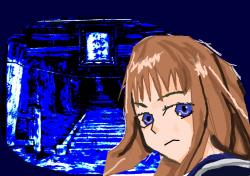次の日。
大は今日も気持ちが沈んでしまい、何も手が付けられない状態が続いていた。
服装もダラダラになり、朝食も喉を通らない。朝からコーヒーしか口にしていない。
このまま、ずっとこうしていたら、自分はどうなるのか。
そんな事を考えてしまう。
すると、もう寝てしまうか、と思っていた時だ。
玄関のチャイムが鳴った。
誰だろうか。こんな夜に自分を訪ねてくれる人など、なかなかいない。
不安がりながら玄関へ向かい、鍵を開けた。
「はい……」
そこにはある人の姿があった。
顔は決して笑ってはいないが、とにかく抱き締めたくなるような可愛い人が。
部屋の奥は暗い。電気さえ点けていなかった。
その人はゆっくりと近付いてきた。そして大の腕を掴んだ。
『……今日、泊まっていい』
「是非とも」