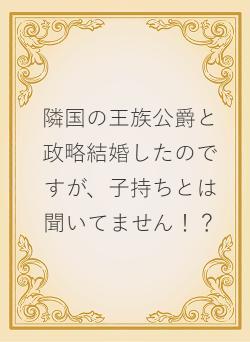壁に掛けられた時計の針が巡り、厨房の手伝いがひと段落すると、休憩時間がもらえた。
「休憩、休憩! リエル。食堂に行くわよ」
「……はい!」
当然のように声をかけてもらえて、仲間として受け入れてもらえた実感が湧く。
先輩侍女は、楽しそうに噂話をたくさん教えてくれる。
「王太子カリオン殿下は婚約者のオフィーリア様を溺愛しているのよ」
「でもライバル令嬢のデイジー様が横恋慕しててね……」
王族の噂話は大丈夫なのだろうか、と思いつつも、顔を寄せ合って囁き合う輪の中は、不思議と居心地がよかった。
「あとね、ここの料理長は前任者が急死してお弟子さんに変わったばかりなんだけど、クビになりそうって噂よ」
「ええ?」
厨房で見かけた長い緑髪をポニーテールにした青年料理長は、新任だったらしい。
リエルが首を傾げたタイミングで、重たい溜息が聞こえてきた。噂の料理長が食堂に入ってきたのだ。
「噂をすれば、料理長ね。あちらも休憩?」
「なんだか重い空気ですね」
侍女たちがひそひそと見守る中、 彼は重い足取りでリエルたちがいるテーブルのすぐ隣のテーブルに行き、悩ましげに弱音を吐いた。
白いシャツに膝丈の前掛けエプロンを締め、濃い藍色のズボンと使い込まれた革靴を履いた青年料理長は、どこかお姉様風の所作と言葉遣いだった。
「……困ったわぁ。これでは予定していた献立が作れないじゃなぁい……」
料理長はテーブルの上にノートを何冊も広げる。
料理人仲間が「困りましたねえ」と相槌を打っている。トラブルのようだ。
「今日は人手も足りないしぃ、仕込みも間に合わないわぁ〜。第二王子殿下がお戻りになるのは来週だと思ってたのに……」
(そういえばシオン様が「予定より早く帰還した」と仰っていたかも)
リエルはシオンの顔を思い出しながら耳をそばだてた。
「第二王子殿下はただでさえ偏食が激しいのよ。お師匠様が遺してくださった料理メモを参考に好みの料理を作るんだけど、いつも料理を残されてしまうの。なのに、お好みの食材が足りないなんて」
なるほど。好き嫌いが激しい第二王子を満足させるための食材が足りないらしい。
(汽車の中ではそんな雰囲気なかったけどな……)
仮にも王城の厨房が食材不足で悩むことがあるのか、とリエルが驚いていると、料理長は外国からの貿易でだけ入手できる希少な食材をリストから順に読み上げた。
どれも「この味は苦手」と顔をしかめる人の方が多いような、癖の強い食材ばかりだ。
料理長の苦労を思っていると、低くて渋い声が聞こえた。
「お前、違うぞ、馬鹿弟子……」
(……見えてしまった)
料理長の隣。
誰にも見えていないはずの場所で、寝巻きをまとった老人の幽霊が嘆いている。触れることができない手で料理長のポニーテールを引っ張ろうとしたり、鼻をつまもうとしたりしながら、独り言を言っている。
「そのメモは好物ではなく苦手な物じゃ。馬鹿弟子……あの夜は酒が美味すぎたんじゃぁあ……」
リエルはすぐにピンときた。ぼやいているのは先代料理長の幽霊に違いない。
「先輩。先代料理長ってお酒好きでした?」
「そうねえ。飲みすぎで倒れてしまって、そのまま亡くなったそうよ」
侍女の先輩の言葉は、予想通りだった。やはり、料理長に憑いているのは先代料理長だ。
「弟子よ。気づいてくれ。わしは泥酔したとき、いつも文字が左に傾いておったじゃろう。そこの棚に隠してある手帳の最後のページにはちゃんと好物を書いてあるのじゃ」
(ふむ……? じゃあ、その手帳を見せたら問題は解決するってこと?)
リエルは立ち上がり、棚に手をかけた。しかし、棚には鍵がかかっていて、開かなかった。
こういう時は、先輩頼みだ。
「先輩、この棚を開けたいのですが、鍵ってありますか?」
棚に手をかけた姿勢で先輩侍女に向かって問いかけた刹那、耳元で聞き覚えのある美声がした。
「これを開ければいいのか?」
「えっ……」
リエルはぎょっとした。
いつの間にか隣に、黒ローブ姿で頭からすっぽりとフードをかぶり、たぬきの仮面を着けたシオンがいる。しかも、食堂中から「なにあれ」「変な人がいる」と囁かれているではないか。
(変に悪目立ちしてる……)
リエルが後ずさって二歩分の距離を取ると、シオンは周囲の注目に気づいた様子で手を振った。
「俺は困っている子の味方、お助け魔法使い。通りすがりのたぬきの妖精――という設定だ。皆、気にしないでほしい」
「無理がありすぎる……」
思わず率直な感想が零れてしまうリエルに、シオンは悪びれることなく一歩近づき、声をかける。
「ところで、リエル。この棚を開けてみようではないか」
テーブル席に座ったままの先輩侍女が視線と口パクで「え、その不審者と知り合いなの?」と問いかけてくるのが、少しだけ居心地悪かった。