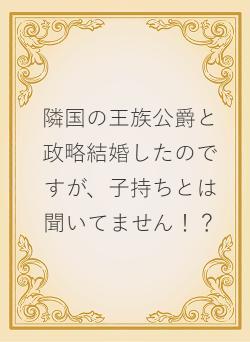翌朝、リエルは侍女仲間に改めて紹介された。
「今日から一緒に仕事をするリエルさんです。わからないことがたくさんあると思うので、先輩として教えてあげてちょうだいね」
「リエルです。よろしくお願いします」
同僚の視線には、歓迎の色がほとんどない。
噂をして注意された侍女たちは気まずそうだし、他の侍女たちはどちらかというと無関心だ。
リエルは必要以上に距離を詰めず、挨拶も返答も簡潔に済ませた。
朝礼の時間が短くて全員名乗っていられないので、自己紹介するのはリエルだけ。
名札もないので、誰が何という名前なのかもわからないまま、初日の仕事が始まった。
「風邪が流行っているせいで、厨房は人手不足中です。あなたたち、野菜の皮剥きと皿洗い要員として駆り出されてくれますか?」
最初の仕事は、厨房の手伝いだ。
◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
厨房にいる王宮料理人は、料理人の中でもエリート揃いだ。
人数は普段より少ないようだが、緑髪をポニーテールにした青年料理長を中心にして、忙しそうに働いている。
そんな料理人たちに専用の作業場を用意され、侍女たちは隅で野菜の皮剥きと洗い物の手伝いを始めた。雰囲気は明るく、手を動かしながら噂話に花を咲かせている。
「第二王子が旅先で病気の種を拾ってきたって噂よ」
さすがに王族の不穏な噂を口にするのはいかがなものか。
しかも第二王子というと、汽車で知り合ったシオンのことではないか。
リエルがじゃがいもの芽をくり抜きながらポーカーフェイスをキープしていると、先輩侍女がじゃがいもと包丁を奪っていった。
「包丁仕事はまだ早いんじゃない? 怪我をするわよ」
心配されているのだろうか? それとも、意地悪?
リエルが解釈に迷っていると、他の侍女が新しい包丁を渡してくれた。
「コニー、新人だからって仕事させないのはだめよ。新人ちゃん、ゆっくりでいいから頑張りなさいな」
「マリアったら知らないの? この子、子爵家の令嬢なのよ。包丁なんて触ったこともないはずだわ。怪我をしてからじゃ、責任取れないでしょう?」
オレンジに近い金髪の侍女がコニーで、赤毛がマリアだ。会話を聞く限り、心配してくれていたようだ。
「あら。コニー。他の貴族令嬢も包丁仕事してるけど? 特別扱いはだめよ」
「違う違う。いきなり任せるんじゃなくて、教えてから仕事をさせた方がいいって言ってるのよ」
先輩方が我が子の教育方針をめぐって争う保護者みたいに睨みあっている。リエルは戸惑った。
「先輩方、お気遣いありがとうございます。私、料理に慣れておりますので問題ございません」
リエルが言うと、「子爵令嬢なのに?」という珍しいものを見るような視線と声が複数上がる。働きに出された後に覚えることはあっても、貴族令嬢が実家で包丁を握って料理に慣れるのは珍しいことなのだ。
言葉で説明するより、実際に見せた方が早い。
リエルが根菜を手に取り、するすると皮をむいてみせると、注目が集まった。
「あらやだ、あたくしより上手」
「本当に慣れてるのね。子爵家ってどうなっているのよ」
「ほら、この子って悪評が……」
悪評の話題が出ると、他の侍女たちが「こほん、こほん」と咳払いして話題を変える。
「ちょっと! 本人を目の前にしてそういうことを言うのやめなさいよ」
「そうよ、そうよ。自分の立場になって想像してごらんなさい」
「ごめんなさい。ただ、私が言いたかったのって、養女だし、子爵家で使用人みたいに虐げられてたんじゃないかなってことなのよ」
ああ、とため息に似た呟きが数人から零れて、同情的な視線が注がれる。
どうやら、この侍女たちはリエルを「仲間」と認定したようだった。実際、使用人のように虐げられていたリエルの側としては微妙に古傷を抉られている話題だ。
「先輩方、私のことは気にしないでください。それより、いろいろとお仕事のことをご指導お願いしたいです。初日なので……」
話題を変えようとしてお願いすると、先輩侍女たちは顔を見合わせ、「じゃあ、お城のことを教えてあげるわ」と新しい話題に切り替えてくれた。
「リエルは第二王子殿下がどんな方か知らないでしょ?」
新しい話題は、王族の噂だった。
「御年二十二歳で、婚約者がいないこと、魔塔の統括者であらせられること以外、ほとんど存じ上げません。……先輩、そちらの籠のにんじん、私が担当しますね」
「ありがとう。実はね、あたくしたちもあまり存じ上げないのよ。あまり人前に姿を見せない方なの」
にんじんの皮をむきながら相槌を打っていると、他の侍女が「そうそう」と声を連ねる。
「第二王子殿下って噂によると寝たり遊んだりしてばかりの残念な方なんですって。公式の場にはあまり出てこなくて、お忍びで城下町をふらついたり遠出することが多くてね……」
「研究熱心で魔塔に籠ってるとか、旅好きだとか、なんだか噂ばかりで本当のことがよくわからない方なのよね」
「遺跡を巡って魔法研究のためのアイテムを発掘してくるって噂よ」
噂話に夢中なせいか、隣でじゃがいもの皮むき中の侍女の手元が危うくなる。確か、他の侍女に呼ばれていた名前はコニーだ。
リエルはすっと手を伸ばし、彼女の手首を掴んだ。
「コニー先輩。危ないです……」
生意気と受け取られないよう気を付けながら控えめに言うと、コニーは一瞬、不意を突かれた顔で固まった。
「リエル。自己紹介してないのに名前を覚えてくれたのね」
「先輩がたが呼び合っていらしたので」
「そう……ありがとう。あなた、しっかりしてるのね」
先輩侍女たちはそれを聞き、「じゃああたくしの名前は?」「あたしの名前もわかる?」と言い出した。
会話を聞いていたので、言い当てられる。
「アニス先輩、リリアンナ先輩、ナタリア先輩……」
リエルが順番に名前を言い当てると、全員が上機嫌になった。
「それにしてもリエルは包丁の扱いが本当に上手ね。誰に教わったの?」
貴族令嬢は料理をしないので、令嬢教育で包丁の使い方を教えられることはない。
ただ、リエルの場合は実家にいたときに料理人の幽霊が教えてくれた。
過去を少しだけ懐かしんでいると、侍女たちは改めて謝ってくれた。
「……昨日は、ごめん」
「いえ。もう気にしていません」
侍女たちは制服のポケットから小さな手帳を取り出し、ツルツルしたページを開いて、そこに貼られていた可愛いシールを一枚ずつくれた。
「これ、あげるわ」
「くまの絵が描かれてるシールなんて、初めて見ました」
茶色いくまの絵が描かれたシールをリエルが物珍しく見ていると、オルディナ出身の侍女が共感する目になった。
「地方都市のオルディナにはこういう品物、ないもんね。じゃあ、わたしはこれあげる」
「わあ、うさぎのシール……」
「王都ではこういうシールを交換するのが流行っているのよ」
手帳のツルツルしたページは、こんな風に使うのか。みんなにもらったシールでいっぱいになった手帳を見ると、何度も見返したくなる宝物ができた気分。
「皆さん、ありがとうございます!」
この様子だと、職場ではうまくやっていけそうだ。
リエルは手帳を大切に抱きしめた。