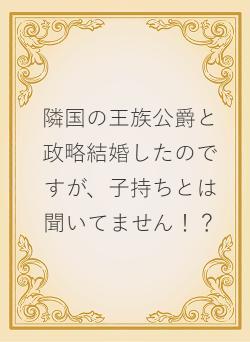「さて、改めて城内を案内いたしましょうか」
「ありがとうございます、侍女長」
『幸福なる駆け落ち城』は広大で、機能別に棟が分かれている。
使用人たちが主に集まる使用人棟と、政治用途で使われる国政執務棟、騎士たちがいる騎士寮、王族の住む宮殿に、魔塔……。
「侍女長。あの黒い塔は魔塔ですよね?」
「ええ、そうですよ。魔塔は危険な場所なので、普通の使用人が立ち入ることはありません」
話している最中に、ドオン! と爆発音がして、塔の上層階から黒煙が上がる。
「えっ……爆発した……」
「……よくあることです」
「よく、あること、なんですか……」
「ええ。ですから、近づかないでください」
どうも魔塔は危険な場所で、かつ、自分には縁がなさそうだ。よかったような、残念なような。
自分でも判然としない気分で、リエルは心細さをごまかすように、侍女長のすぐ後ろを歩いた。
廊下、作業場、そして、使用人用の食堂へ。
「リエル。こちらの食堂は、使用人の憩いの場、と言えばわかりやすいでしょうか?」
「侍女長。とてもわかりやすい説明をありがとうございます」
食堂には数名の侍女がいた。
王城で働く侍女は、貴族や商家の令嬢が礼儀見習いとして勤めることが多い。
そのせいか、集まって話している彼女たちの雰囲気は、まるで社交界のティータイムだ。
家柄や親の事業の話、婚約者の話が聞こえてくる。しかも、身に覚えがある話題が聞こえてくる。
「ねえ、侍女長と一緒にいた新人の子、見た?」
「あら。新人が入ってきたのね。わたし、まだ見てないわ」
「私、あの子、たぶん知ってるのよね」
(……私のこと、だ)
食堂に入ってきた侍女長とリエルには気づかない様子で話しこんでいる。
年齢的にはリエルと同じぐらいだ。見覚えがある顔なので、リエルは嫌な予感がした。
「知ってるって? あなたと同じオルディナ出身ってこと?」
「そうね、よく知らないけど……ネーベルハルト子爵家の養子だったと思う……」
間違いない。同郷だ。
一年前に王都に引っ越しをした商家の娘だ。
「あまりよくない噂があった子、だったかなぁ……」
根拠は曖昧、話し手の確信は弱い。
それでも噂は広まって、いつの間にか事実のように定着してしまう。リエルはそれをよく知っていた。
(嫌だな……結局、どこへ行っても変わらないってことか……)
冷えた気分でいると、侍女長が声を上げて嗜めてくれた。
「あらまあ、あなたたち。よく知らないのに、どうして良い子じゃないと決めつけるんです? 悪評を広めて楽しむなんて、淑女としての品性に欠けますよ」
「あっ、侍女長……!」
「やだ、いらしたんですね⁉︎」
侍女たちは口を閉じて立ち上がり、リエルに気づくと気まずそうな顔で頭を下げた。
「淑女らしくないあなたたちには、今後一週間、共同作業を命じます。騎士団寮の清掃当番を増やしましょう」
「ええ~~っ⁉︎ 嫌です~‼︎」
「騎士団のトイレ、すごく汚いんですよ! 使い方が雑なの!」
「汚いから綺麗にするのでしょう?」
賑やかなやり取りに呆然としていると、リエルの目に、うっすらとした幽霊の騎士が見えてきた。
「うちの野郎どもが……すまん……生前、何度注意しても改善されなかったんだ……すまん……」
あ、謝っている……。
ぶつぶつと謝罪する騎士は、ふとリエルの方を見た。
ぱちっ。
ばっちり目が合って、「嬢ちゃん」と呼ばれて、ぎくりとする。
「見えるのか、オレが」
「うっ……」
気づかれた。
リエルが後ずさりしていると、侍女長が目ざとく気づいて心配そうに背中を撫でる。
「陰口で嫌な気持ちになったでしょう、リエル。大丈夫ですか? ごめんなさいね」
「い、いえ……その、侍女長」
幽霊の騎士が両手を合わせて拝んでくる。
た、頼まれている――リエルは少し考えてから提案した。
「騎士団寮に、『施設を綺麗に使ってください』って張り紙をしてみたらどうでしょうか……? あまりひどかったら自分たちで掃除してもらうとか……」
こうして、侍女仲間との初対面は気まずいスタートを切ったのだった。
そんなスタートを背景に、幽霊の騎士は「ありがとう……」と満足そうに昇天していく。ペンダントが幽霊の昇天を祝福するようにきらきらとオレンジ色に輝いた。
『トイレを綺麗に使わせると約束したのに守れなくて……あいつら人数が多いから祟るのも大変だったんだ……』
「祟ってたんだ……」
どうも、このペンダントは、幽霊を助けると光るみたいだ。
リエルはそんな推理をしつつ、光が収まったペンダントを指先で撫でた。
「ありがとうございます、侍女長」
『幸福なる駆け落ち城』は広大で、機能別に棟が分かれている。
使用人たちが主に集まる使用人棟と、政治用途で使われる国政執務棟、騎士たちがいる騎士寮、王族の住む宮殿に、魔塔……。
「侍女長。あの黒い塔は魔塔ですよね?」
「ええ、そうですよ。魔塔は危険な場所なので、普通の使用人が立ち入ることはありません」
話している最中に、ドオン! と爆発音がして、塔の上層階から黒煙が上がる。
「えっ……爆発した……」
「……よくあることです」
「よく、あること、なんですか……」
「ええ。ですから、近づかないでください」
どうも魔塔は危険な場所で、かつ、自分には縁がなさそうだ。よかったような、残念なような。
自分でも判然としない気分で、リエルは心細さをごまかすように、侍女長のすぐ後ろを歩いた。
廊下、作業場、そして、使用人用の食堂へ。
「リエル。こちらの食堂は、使用人の憩いの場、と言えばわかりやすいでしょうか?」
「侍女長。とてもわかりやすい説明をありがとうございます」
食堂には数名の侍女がいた。
王城で働く侍女は、貴族や商家の令嬢が礼儀見習いとして勤めることが多い。
そのせいか、集まって話している彼女たちの雰囲気は、まるで社交界のティータイムだ。
家柄や親の事業の話、婚約者の話が聞こえてくる。しかも、身に覚えがある話題が聞こえてくる。
「ねえ、侍女長と一緒にいた新人の子、見た?」
「あら。新人が入ってきたのね。わたし、まだ見てないわ」
「私、あの子、たぶん知ってるのよね」
(……私のこと、だ)
食堂に入ってきた侍女長とリエルには気づかない様子で話しこんでいる。
年齢的にはリエルと同じぐらいだ。見覚えがある顔なので、リエルは嫌な予感がした。
「知ってるって? あなたと同じオルディナ出身ってこと?」
「そうね、よく知らないけど……ネーベルハルト子爵家の養子だったと思う……」
間違いない。同郷だ。
一年前に王都に引っ越しをした商家の娘だ。
「あまりよくない噂があった子、だったかなぁ……」
根拠は曖昧、話し手の確信は弱い。
それでも噂は広まって、いつの間にか事実のように定着してしまう。リエルはそれをよく知っていた。
(嫌だな……結局、どこへ行っても変わらないってことか……)
冷えた気分でいると、侍女長が声を上げて嗜めてくれた。
「あらまあ、あなたたち。よく知らないのに、どうして良い子じゃないと決めつけるんです? 悪評を広めて楽しむなんて、淑女としての品性に欠けますよ」
「あっ、侍女長……!」
「やだ、いらしたんですね⁉︎」
侍女たちは口を閉じて立ち上がり、リエルに気づくと気まずそうな顔で頭を下げた。
「淑女らしくないあなたたちには、今後一週間、共同作業を命じます。騎士団寮の清掃当番を増やしましょう」
「ええ~~っ⁉︎ 嫌です~‼︎」
「騎士団のトイレ、すごく汚いんですよ! 使い方が雑なの!」
「汚いから綺麗にするのでしょう?」
賑やかなやり取りに呆然としていると、リエルの目に、うっすらとした幽霊の騎士が見えてきた。
「うちの野郎どもが……すまん……生前、何度注意しても改善されなかったんだ……すまん……」
あ、謝っている……。
ぶつぶつと謝罪する騎士は、ふとリエルの方を見た。
ぱちっ。
ばっちり目が合って、「嬢ちゃん」と呼ばれて、ぎくりとする。
「見えるのか、オレが」
「うっ……」
気づかれた。
リエルが後ずさりしていると、侍女長が目ざとく気づいて心配そうに背中を撫でる。
「陰口で嫌な気持ちになったでしょう、リエル。大丈夫ですか? ごめんなさいね」
「い、いえ……その、侍女長」
幽霊の騎士が両手を合わせて拝んでくる。
た、頼まれている――リエルは少し考えてから提案した。
「騎士団寮に、『施設を綺麗に使ってください』って張り紙をしてみたらどうでしょうか……? あまりひどかったら自分たちで掃除してもらうとか……」
こうして、侍女仲間との初対面は気まずいスタートを切ったのだった。
そんなスタートを背景に、幽霊の騎士は「ありがとう……」と満足そうに昇天していく。ペンダントが幽霊の昇天を祝福するようにきらきらとオレンジ色に輝いた。
『トイレを綺麗に使わせると約束したのに守れなくて……あいつら人数が多いから祟るのも大変だったんだ……』
「祟ってたんだ……」
どうも、このペンダントは、幽霊を助けると光るみたいだ。
リエルはそんな推理をしつつ、光が収まったペンダントを指先で撫でた。