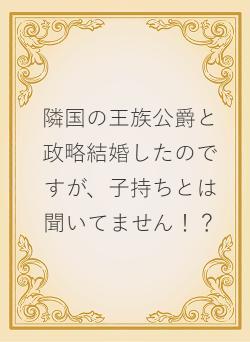ラクリマリア王国は、大陸の中央部にある。
周囲の国は気候に恵まれていて豊かだが、この国は瘴気竜のせいで苦労している。
「でもね、我が国はその分、魔法技術が卓越しているんだよ」
「青薔薇商会の影響力も大きい」
「外交も巧みで、周辺国との均衡を保ってきた国だ」
王都の民は旅行客や新参者を見ると誇らしげに語りかけているので、リエルは興味深く情報を耳に入れた。
「王室メンバーも敬愛できる方々で、優秀なんだ」
「ただし、第二王子のハルティシオン殿下だけは残念なんだけどね」
――ハルティシオン殿下。
その名前を聞いた時、頭がずきりと痛む。ほんの、一瞬。
寒さのせいだろうか。
「お嬢さん。可愛いぬいぐるみを買っていかないかい?」
気にしていると、通りに面した雑貨屋の主人がぬいぐるみを売り込んできた。
節約のために断ろうと視線を向けて、ぬいぐるみの可愛らしさに目が留まる。つぶらな瞳に、温かみのある茶色の毛並み、ぽふっとした縞模様の尻尾。
「たぬきのぬいぐるみ? か、可愛いですね」
思わず足を止めていると、シオンがぬいぐるみを買ってくれた。
「プレゼントするよ」
「あ……ありがとう、ございます」
可愛いぬいぐるみを抱っこしていると、幸福感が湧いてくる。
リエルは頬を緩めた。
「君が喜んでくれて嬉しい。たぬきに感謝だな」
シオンは満足そうに微笑み、店主からおまけとして差し出されたたぬきの仮面を受け取る。そして、道の先で尖塔を覗かせる王城を指した。
「リエル。あれが我が国の誇る『幸福なる駆け落ち城』だ」
「名前は奇妙ですけど、風格がありますね」
「うちの王族は駆け落ち気質なんだ。そして、欲が深くて幸せになるために手段を選ばない……」
「それ、暴君気質じゃないですか? 大丈夫……?」
駆け落ち城の正門は、遠目に見ていた以上に威圧感がある。
白い石で築かれた巨大な門扉の前には、武装した衛兵と入城監査官が目を光らせて、入城者の身分を確認している。
リエルはシオンに荷物を返してもらい、身分証と紹介状を取り出した。
「リエル。ここでいったんお別れだな。俺は予定より早く帰還した報告をしたり家族に借りた金を返したりと、まあ、いろいろする。落ち着いたらまた会おう」
「いろいろ頑張ってください。道中ありがとうございました」
リエルはひらひらと手を振って見送った。
こちらは新米侍女。
あちらは希少なエリート魔法使い様。偶然の縁もこれまでだろう。
見送る視線の先で、シオンは堂々とした態度でフードを持ち上げ、入城監査官に顔を見せた。
「あちらにいる白い髪の乙女は、俺の初恋の人だ。丁重にもてなしてくれ」
――今なんて?
リエルが耳を疑っていると、入城監査官は背筋を正し、恭しい態度で頭を下げた。
「ハルティシオン殿下。おかえりなさいませ!」
――殿下⁉
「しいっ、今はお忍び中だ」
「殿下の初恋の方は金髪だとお伺いしておりましたが?」
「髪の色なんていくらでも変わる」
明らかに聞いてはいけない会話が聞こえてしまった。
ハルティシオン殿下というのは、この国の第二王子にして魔術研究機関『魔塔』の統括者ではないか。
「お忍びで女性をたらし込むのは感心しませんね。お父上にご報告いたします」
「違う。たらし込んだわけじゃないんだ。彼女は城で働く予定だ」
「勝手に決められても困ります……」
「いや、俺が決めたんじゃなくて最初からその予定で紹介状を持ってるんだ」
入城監査官と押し問答してから、シオンはリエルの顔色を気にするように視線を向けてくる。
(聞かなかったことにしてあげよう)
リエルが素知らぬ顔をしていると、シオンは近寄ってきた。
「リエル。今のは……」
「シオン様。私は全く何も聞いていませんが、何か?」
とぼけてみせると、シオンは蜂蜜色の瞳を丸くして両手で頭を抱えだ。
「くっ……嘘が下手で可愛い……っ俺を殺す気か……」
「えっ……」
「殿下……!? いかがなさいました⁉︎」
奇行を見て入城監査官が声を上げて駆け寄ってくる。もう「聞こえませんでした」が通じる状況ではないが、シオンは入城監査官を押しのけて立ち上がった。
「可愛くて優しい嘘に感謝を」
引き気味のリエルの右手を取り、シオンは自然な所作で手の甲にキスをした。
「な……っ!」
動揺して固まるリエルを覗き込むようにして、シオンは嬉しそうに目を細めた。
「君と触れ合えるのが嬉しい。もっと悪戯したくなる」
……どきりとさせることを言う!
リエルが反応に困っていると、シオンは右手の人差し指を自分の唇にあてて、恥じらうように目を伏せた。
「それでは、また」
伏せ目で微笑む顔が、春の陽だまりのように麗しい。
言うだけ言って、彼はくるりと背を向け離れていった。
それを見送り、リエルは自分の頬を軽く叩いた。
(落ち着け、私)
相手は王族。
乙女心を動かされても、良いことはない。
「ときめいてはいけない……」
「あの……我が国のでん……あ……あれが、申し訳ございません」
入城監査官は同情的に声をかけてくれた。第二王子をあれ呼ばわりしてしまっているが。リエルは微妙な気持ちになりつつ、身分証と紹介状を差し出した。
「私は王城勤務の下級侍女として勤務する予定のリエル・ネーベルハルトです。こちらが紹介状になります」
「……確認しました。こちらへ」
キリッとした顔で挨拶すると、入城監査官はぎこちなく顎を引き、人の良さそうな顔に照れたような笑みを浮かべて案内役に引き継いでくれた。入城監査官と案内役の会話が聞こえてくる。
「第二王子殿下の初恋の人だそうです。あ、でも殿下はお忍びで、正体を隠しておられるようですよ」
「へえ。あの殿下の初恋の人って年上の金髪お姉さんじゃなかったっけ。まあ、いいか」
「いやー、そう思ったんですが、髪の色は変わったらしくて。あと、目の色はちゃんと紫なんですよ。ほら、殿下って初恋の方の瞳の色に髪を染めてるって噂があるじゃないですか……」
……その引き継ぎ方はどうなの?
ひそひそ声のはずの会話が、どうも耳に届く。リエルは聞こえないフリをしながら自分の髪をつまんだ。
真っ白な髪は、生まれつきだ。
周囲の国は気候に恵まれていて豊かだが、この国は瘴気竜のせいで苦労している。
「でもね、我が国はその分、魔法技術が卓越しているんだよ」
「青薔薇商会の影響力も大きい」
「外交も巧みで、周辺国との均衡を保ってきた国だ」
王都の民は旅行客や新参者を見ると誇らしげに語りかけているので、リエルは興味深く情報を耳に入れた。
「王室メンバーも敬愛できる方々で、優秀なんだ」
「ただし、第二王子のハルティシオン殿下だけは残念なんだけどね」
――ハルティシオン殿下。
その名前を聞いた時、頭がずきりと痛む。ほんの、一瞬。
寒さのせいだろうか。
「お嬢さん。可愛いぬいぐるみを買っていかないかい?」
気にしていると、通りに面した雑貨屋の主人がぬいぐるみを売り込んできた。
節約のために断ろうと視線を向けて、ぬいぐるみの可愛らしさに目が留まる。つぶらな瞳に、温かみのある茶色の毛並み、ぽふっとした縞模様の尻尾。
「たぬきのぬいぐるみ? か、可愛いですね」
思わず足を止めていると、シオンがぬいぐるみを買ってくれた。
「プレゼントするよ」
「あ……ありがとう、ございます」
可愛いぬいぐるみを抱っこしていると、幸福感が湧いてくる。
リエルは頬を緩めた。
「君が喜んでくれて嬉しい。たぬきに感謝だな」
シオンは満足そうに微笑み、店主からおまけとして差し出されたたぬきの仮面を受け取る。そして、道の先で尖塔を覗かせる王城を指した。
「リエル。あれが我が国の誇る『幸福なる駆け落ち城』だ」
「名前は奇妙ですけど、風格がありますね」
「うちの王族は駆け落ち気質なんだ。そして、欲が深くて幸せになるために手段を選ばない……」
「それ、暴君気質じゃないですか? 大丈夫……?」
駆け落ち城の正門は、遠目に見ていた以上に威圧感がある。
白い石で築かれた巨大な門扉の前には、武装した衛兵と入城監査官が目を光らせて、入城者の身分を確認している。
リエルはシオンに荷物を返してもらい、身分証と紹介状を取り出した。
「リエル。ここでいったんお別れだな。俺は予定より早く帰還した報告をしたり家族に借りた金を返したりと、まあ、いろいろする。落ち着いたらまた会おう」
「いろいろ頑張ってください。道中ありがとうございました」
リエルはひらひらと手を振って見送った。
こちらは新米侍女。
あちらは希少なエリート魔法使い様。偶然の縁もこれまでだろう。
見送る視線の先で、シオンは堂々とした態度でフードを持ち上げ、入城監査官に顔を見せた。
「あちらにいる白い髪の乙女は、俺の初恋の人だ。丁重にもてなしてくれ」
――今なんて?
リエルが耳を疑っていると、入城監査官は背筋を正し、恭しい態度で頭を下げた。
「ハルティシオン殿下。おかえりなさいませ!」
――殿下⁉
「しいっ、今はお忍び中だ」
「殿下の初恋の方は金髪だとお伺いしておりましたが?」
「髪の色なんていくらでも変わる」
明らかに聞いてはいけない会話が聞こえてしまった。
ハルティシオン殿下というのは、この国の第二王子にして魔術研究機関『魔塔』の統括者ではないか。
「お忍びで女性をたらし込むのは感心しませんね。お父上にご報告いたします」
「違う。たらし込んだわけじゃないんだ。彼女は城で働く予定だ」
「勝手に決められても困ります……」
「いや、俺が決めたんじゃなくて最初からその予定で紹介状を持ってるんだ」
入城監査官と押し問答してから、シオンはリエルの顔色を気にするように視線を向けてくる。
(聞かなかったことにしてあげよう)
リエルが素知らぬ顔をしていると、シオンは近寄ってきた。
「リエル。今のは……」
「シオン様。私は全く何も聞いていませんが、何か?」
とぼけてみせると、シオンは蜂蜜色の瞳を丸くして両手で頭を抱えだ。
「くっ……嘘が下手で可愛い……っ俺を殺す気か……」
「えっ……」
「殿下……!? いかがなさいました⁉︎」
奇行を見て入城監査官が声を上げて駆け寄ってくる。もう「聞こえませんでした」が通じる状況ではないが、シオンは入城監査官を押しのけて立ち上がった。
「可愛くて優しい嘘に感謝を」
引き気味のリエルの右手を取り、シオンは自然な所作で手の甲にキスをした。
「な……っ!」
動揺して固まるリエルを覗き込むようにして、シオンは嬉しそうに目を細めた。
「君と触れ合えるのが嬉しい。もっと悪戯したくなる」
……どきりとさせることを言う!
リエルが反応に困っていると、シオンは右手の人差し指を自分の唇にあてて、恥じらうように目を伏せた。
「それでは、また」
伏せ目で微笑む顔が、春の陽だまりのように麗しい。
言うだけ言って、彼はくるりと背を向け離れていった。
それを見送り、リエルは自分の頬を軽く叩いた。
(落ち着け、私)
相手は王族。
乙女心を動かされても、良いことはない。
「ときめいてはいけない……」
「あの……我が国のでん……あ……あれが、申し訳ございません」
入城監査官は同情的に声をかけてくれた。第二王子をあれ呼ばわりしてしまっているが。リエルは微妙な気持ちになりつつ、身分証と紹介状を差し出した。
「私は王城勤務の下級侍女として勤務する予定のリエル・ネーベルハルトです。こちらが紹介状になります」
「……確認しました。こちらへ」
キリッとした顔で挨拶すると、入城監査官はぎこちなく顎を引き、人の良さそうな顔に照れたような笑みを浮かべて案内役に引き継いでくれた。入城監査官と案内役の会話が聞こえてくる。
「第二王子殿下の初恋の人だそうです。あ、でも殿下はお忍びで、正体を隠しておられるようですよ」
「へえ。あの殿下の初恋の人って年上の金髪お姉さんじゃなかったっけ。まあ、いいか」
「いやー、そう思ったんですが、髪の色は変わったらしくて。あと、目の色はちゃんと紫なんですよ。ほら、殿下って初恋の方の瞳の色に髪を染めてるって噂があるじゃないですか……」
……その引き継ぎ方はどうなの?
ひそひそ声のはずの会話が、どうも耳に届く。リエルは聞こえないフリをしながら自分の髪をつまんだ。
真っ白な髪は、生まれつきだ。