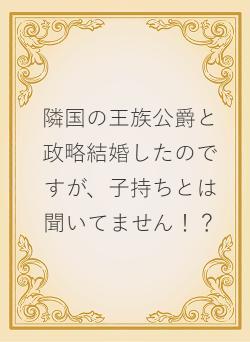「リエル。このソーセージは我が国の誇る魔法技術で保温されていて温かいんだ。食べてみてくれ」
「さっきから美味しそうな匂いがしてるなって思ってました。では、お言葉に甘えていただきます」
ソーセージを口に運ぶと、外側の皮がぷっくりとしていて、噛むと中から肉汁があふれ出す。
熱い。上に塗られた赤野菜のソースがうま味と絶妙に混ざり合って、とても美味しい。
ふと気づくと、シオンが穏やかな微笑を湛えて見つめていた。
目が合うと、上質なシルクのハンカチを取り出し、リエルの口の端を拭いてくれる。赤野菜のソースが付いていたのだと気づき、リエルは頬をカッと紅潮させた。
「すみません、シオン様。それ、洗ってお返しします」
「いや。俺が勝手に拭きたくなって拭いただけだから。むしろ、無断で触れてすまない」
シオンはハンカチを軽く宙に放った。
すると、無音のまま、空中でハンカチが水色の炎に包まれる。煙を吐くこともなく、瞬きするほどの時間で炎は消えて、ハンカチは炭すら残らず消滅した。
「ま、……魔法?」
「口元を拭ったハンカチを俺が所持しているのは不快かと思ったので」
呆然とするリエルに頷き、シオンは楽しげに目を細めて味を尋ねた。
「ちなみにお味はいかが? リエル?」
「美味しいです……」
初めて見た魔法は、ちょっと怖かった。
魔法使いはその学術知識や魔法の技術で国を衰退から守り、支える人材。人口の二割に満たない、極めて貴重な存在だ。地方都市オルディナには、いなかった。
「私、魔法使いの人を見るのは初めてです」
「君にとって、初めての魔法使いが俺だというのは……光栄だな」
「光栄……?」
どちらかというとリエルが「会えて光栄です」と言うべきではないだろうか?
首を傾げていると、汽車はブレーキをかけて速度を緩めていく。
目的地、王都ブランビリエに着いたのだ。
話していたせいだろうか。汽車の旅をした体感時間がかなり短く感じる。
リエルは心のどこかで安堵する自分に気づいた。
シオンとケイティは、自分に好意的で親しくしてくれる。でも、彼らの根底にあるのは「別の誰かへの親しみ」だ。
だから、友好的にしてくれて嬉しい一方で、喜びの隣に、名前のつけられない違和感が残った。
リエルはキャリーケースを持ち、立ち上がった。
「ブランビリエの駅に到着したようですね。降りましょう。車内食をご馳走してくださって、ありがとうございました」
「リエル。俺が荷物を持とうか?」
隣に立つシオンは背が高く、差し出された手は大きくて、頼もしく見える。
けれど、リエルはふるふると首を横に振った。
「いえ、自分で持ちます。自分の荷物なので。出会ったばかりの方に、そこまで何もかもお世話になれません」
「警戒心があって立派だな。女の子はそれくらいじゃないと世の中物騒だから、いいと思う」
感心したように言いながら、シオンは荷物を奪って運び始めた。
オルディナでは厄介者として扱われていたから、丁重に接遇されるとくすぐったい心地がする。
「別に警戒してるわけでは……というか、仰ることとやってることが違いません?」
「俺にはそういう悪いところがあるんだ。でも、運ぶだけだから」
「……運んでくださってありがとうございます」
お礼を言うと、シオンは蕩ける夕陽のような柔らかな微笑を湛えた。
その破壊力抜群の美貌に、通行人の女性が頬を赤らめて見とれている。
黒フードで顔を隠さないといけないわけだ。隠していてもこれなのだが。
石造りの大きな駅舎に面したホームには、旅人や商人が溢れている。
駅舎の中は天井が高く、白い石柱が等間隔に並んでいた。
切符を役人に渡し、行き先を告げて外へ出ると、ここはもう八万人が生活する王都ブランビリエだ。
地方都市オルディナは人口が三千人ほどだったので、その差に圧倒される。
「ここが王都……」
道幅は広く、雪が積もっている。
風によって巻き上がる雪の粉は、上空から注ぐ雪と合わせて、視界を薄い白色に霞ませた。
行き交う人々の服は厚手で、単なる防寒用のコートではなく、洗練されたデザイン。
悪目立ちしそうなほど継ぎ接ぎだらけの自分の服を見下ろし、リエルは小さく拳を握った。
(気にしない。私の人生、これからなんだから)
高い城壁に囲まれ、雪化粧された街並みは立派だ。窓から天使の双翼と盾の意匠の王国旗を下げている家が多くて、愛国心が窺える。
「リエル。王城に行くんだろう? こちらだよ」
「道案内、助かります。ありがとうございます」
王都の空気を胸いっぱいに吸い込みながら、リエルは新しい一歩を踏み出した。
そんなリエルを眩しそうに見つめて、シオンは晴れやかに言葉を贈った。
「俺の愛する王都、ブランビリエへようこそ。これから君は、必ず幸せになる。天に誓って、絶対だ」
その声が聞こえたらしく、周囲の王都民が言葉をかけてくる。
「おや、いらっしゃい、お嬢さん」
「ブランビリエへようこそ!」
偶然にも曇り空にも切れ間ができて、貴重な陽光が注ぎ込んでいる。
リエルは温かな気分になった。
「隣の彼と結婚するのかい? 美男子じゃないか。お幸せに」
歓迎されるというのは、いいものだ。でも。
「結婚は、しません」
誤解は正さないといけない。リエルは赤くなって訂正した。