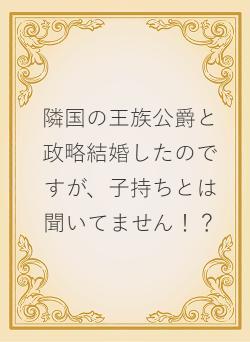少し経つと、汽車の内部を巡る食事ワゴンがやってきた。
「お客様。旅のお供に軽食サービスはいかがでしょうか?」
ようやく訪れた食事の時間だ。
リエルが目を輝かせて返事をしようとした瞬間。
「リエル。よければ俺に奢らせてくれないか」
「……え?」
返事をするより先に、シオンは食事を買ってくれた。魔法の保温容器に入ったホットソーセージの詰め合わせ。五種類の根菜サラダに、ホット・ハニーティー。デザートのタルトまで選ばせてくれたので、好物のレモンタルトを選んでみた。
座席に設置された簡易テーブルに置かれた料理の匂いに、思わず腹が小さく鳴った。
リエルは誤魔化すように視線を伏せる。
「ありがとうございます、シオン様。私、お金を払いますね」
「嬉しそうな顔が見られただけで、十分だ。金は有り余ってるし、気にしなくていい」
シオンはローブの袖をめくり、指輪や腕輪を見せてくれた。どれも魔術師が扱う魔力を蓄えられる魔宝石だ。
魔宝石は希少で、宝石の何倍も高額。つまり、彼はとんでもない大金持ちということになる。
「俺はもうすぐ自由の身を卒業するのだが、その前に思い残すことがないよう、二ヶ月ほど冒険の旅をしてきたんだ」
「冒険の旅、ですか」
「ああ。仕事の都合で、二ヶ月だけ何もしなくても仕事に支障が出ない期間ができたものだから」
「お仕事お疲れ様です」
リエルがありがたく根菜サラダを食べ始めると、彼は旅の話に触れて、腰の剣を示した。
素人目にも特別な一振りだとわかる、美しい剣だ。
剣身が煌めく不思議な素材でできていて、柄の側は夜空のてっぺんを切り取ったような藍色。そこから切っ先に近づくにつれて夜明け色に変化する色彩だ。
「これは天から星竜が舞い降りたと噂の遺跡に潜った時の戦利品。星竜の剣といって、オークションにかければ子孫が三代に渡って贅沢に生活できるくらいの金になる」
(……は?)
あまりに桁外れな話に、言葉を失った。
「英雄物語に出てくるような伝説級の剣じゃないですか」
「俺は英雄になる男なのでな……と言ったら、信じるか?」
そう言って、少し照れたように笑うシオンに、ケイティがぴしゃりと口を挟む。
「シオン様。大口を叩く男は軽く見られますわよ」
「ごめんなさい」
ケイティに窘められると、すぐに謝る。
リエルはくすっと笑った。こんな風に他者との会話で和むのは、いつ以来だろう。
「ええと、つまりシオン様は、『お金持ちだから施しを気にするな』と仰りたいのでしょうか? でも、無償の好意を信じるのは怖いかも。なにせ、今までの環境は他人を利用したり踏み台にする大人ばかりで……」
いけない、考えが声に出ている。
リエルが思考を口に出して垂れ流していることに気づいた時には、シオンとケイティは揃って不審そうな顔になっていた。
「答えたくなければ、無理にとは言わないが……今まで幸せじゃなかったのか?」
「どんな環境にいたんですの?」
まるで「幸せで当然だ」と思っていたかのような反応だった。
恵まれた環境で育った人に時おり見られる現象だ。
自分がそうだから他人も同じだ、と当たり前のように思い込んでいる。
そんな無邪気さを、リエルはほろ苦く感じた。
「あ……もしや、ご気分を害してしまっただろうか?」
「いえ、大丈夫です」
シオンは人の気持ちを察することができる青年のようだった。
すぐに気が付き、心配そうに眉を下げる。その顔が、まるで「見捨てないで」と懇願しているように見えてリエルは目を擦った。
「目の調子が悪いのか?」
「いえ。大丈夫です」
「同じことばかり言う……人見知りされているのだろうか。確かに俺たちは怪しいが」
シオンが真剣に言うので、リエルは謎の罪悪感を刺激された。別に悪いことは何もしていないのに、彼には「この人を悲しませてはいけない」と思わせる何かがあるようだった。
「リエルのことを知りたいな。差し支えなければ、いろいろ教えてくれないか? 困っていることがあれば、力になりたいし……」
必死な顔でお願いされると、不思議と警戒心より先に親しみが湧いてきた。
――シオン様、おそるべし。
「私は十五歳で、これから王城で住み込みで働く予定です」
「奇遇だな、俺は城の魔塔勤めの魔法使いだ。一緒に城まで行こうか。 参考までに、魔塔勤めは信用ならない魔法使いが多いから気を付けろ」
「斬新な自己紹介ですね……」
リエルはサラダをつつく手を休めて、木製カップに手を伸ばした。
ほのかに光る魔法塗料で真っ赤な林檎を持った茶色いクマの絵が描いてある。両手で包み込むように持つと、手のひらがじんわりと温まった。
「リエル。俺は君の今までの話が聞きたいな。食事代のかわりに詳しく話してくれないかな?」
「食事代、ですか。そうですね……」
過去とは「さようなら」をしたばかりだが、他人に話してもいいかもしれない。食事代だと思えば、抵抗感も薄れる。
リエルは今までの身の上話を打ち明けた。すると、シオンはリエルの不遇に驚き、悲しみ、怒ってくれた。
「なんてひどい話なんだ。こんなことが許されるはずがない!」
物騒な発言をしているが、話を聞いてもらえて、共感してもらえた。
……家を出てよかった。
家を出なかったら、目の前のひとりと一匹には巡り合えなかったから。
「大丈夫だ。君は今から幸せになる。俺が保証するよ」
「ありがとうございます、シオン様は良い方ですね。同じ王城勤めでもありますし、心強いです」
車窓の外を見ると、曇り空が果てしなく広がっている。この国の住人誰もが見慣れた風景だ。
『瘴気竜に狙われた王国』。
ラクリマリア王国は、周辺国からそう呼ばれている。
いつからか、この国の空は分厚い瘴気の雲で覆われるようになった。
瘴気の雲の上には邪悪な黒い瘴気竜が居座っている。
瘴気竜はラクリマリア王国に執着していて、瘴気の雲を作ったり、気まぐれに地上に近づいて人々を脅かしたりする日々。
曇天のせいで、ラクリマリア王国では土地が痩せ、作物は育たない。
瘴気竜は地上近くに飛翔しても人や建築物に直接的な被害をもたらしたことはないが、人々はいつも「いつ瘴気竜が飛んでくるか」と恐れている。
国はなんとか成り立っている。今は、まだ。
「お客様。旅のお供に軽食サービスはいかがでしょうか?」
ようやく訪れた食事の時間だ。
リエルが目を輝かせて返事をしようとした瞬間。
「リエル。よければ俺に奢らせてくれないか」
「……え?」
返事をするより先に、シオンは食事を買ってくれた。魔法の保温容器に入ったホットソーセージの詰め合わせ。五種類の根菜サラダに、ホット・ハニーティー。デザートのタルトまで選ばせてくれたので、好物のレモンタルトを選んでみた。
座席に設置された簡易テーブルに置かれた料理の匂いに、思わず腹が小さく鳴った。
リエルは誤魔化すように視線を伏せる。
「ありがとうございます、シオン様。私、お金を払いますね」
「嬉しそうな顔が見られただけで、十分だ。金は有り余ってるし、気にしなくていい」
シオンはローブの袖をめくり、指輪や腕輪を見せてくれた。どれも魔術師が扱う魔力を蓄えられる魔宝石だ。
魔宝石は希少で、宝石の何倍も高額。つまり、彼はとんでもない大金持ちということになる。
「俺はもうすぐ自由の身を卒業するのだが、その前に思い残すことがないよう、二ヶ月ほど冒険の旅をしてきたんだ」
「冒険の旅、ですか」
「ああ。仕事の都合で、二ヶ月だけ何もしなくても仕事に支障が出ない期間ができたものだから」
「お仕事お疲れ様です」
リエルがありがたく根菜サラダを食べ始めると、彼は旅の話に触れて、腰の剣を示した。
素人目にも特別な一振りだとわかる、美しい剣だ。
剣身が煌めく不思議な素材でできていて、柄の側は夜空のてっぺんを切り取ったような藍色。そこから切っ先に近づくにつれて夜明け色に変化する色彩だ。
「これは天から星竜が舞い降りたと噂の遺跡に潜った時の戦利品。星竜の剣といって、オークションにかければ子孫が三代に渡って贅沢に生活できるくらいの金になる」
(……は?)
あまりに桁外れな話に、言葉を失った。
「英雄物語に出てくるような伝説級の剣じゃないですか」
「俺は英雄になる男なのでな……と言ったら、信じるか?」
そう言って、少し照れたように笑うシオンに、ケイティがぴしゃりと口を挟む。
「シオン様。大口を叩く男は軽く見られますわよ」
「ごめんなさい」
ケイティに窘められると、すぐに謝る。
リエルはくすっと笑った。こんな風に他者との会話で和むのは、いつ以来だろう。
「ええと、つまりシオン様は、『お金持ちだから施しを気にするな』と仰りたいのでしょうか? でも、無償の好意を信じるのは怖いかも。なにせ、今までの環境は他人を利用したり踏み台にする大人ばかりで……」
いけない、考えが声に出ている。
リエルが思考を口に出して垂れ流していることに気づいた時には、シオンとケイティは揃って不審そうな顔になっていた。
「答えたくなければ、無理にとは言わないが……今まで幸せじゃなかったのか?」
「どんな環境にいたんですの?」
まるで「幸せで当然だ」と思っていたかのような反応だった。
恵まれた環境で育った人に時おり見られる現象だ。
自分がそうだから他人も同じだ、と当たり前のように思い込んでいる。
そんな無邪気さを、リエルはほろ苦く感じた。
「あ……もしや、ご気分を害してしまっただろうか?」
「いえ、大丈夫です」
シオンは人の気持ちを察することができる青年のようだった。
すぐに気が付き、心配そうに眉を下げる。その顔が、まるで「見捨てないで」と懇願しているように見えてリエルは目を擦った。
「目の調子が悪いのか?」
「いえ。大丈夫です」
「同じことばかり言う……人見知りされているのだろうか。確かに俺たちは怪しいが」
シオンが真剣に言うので、リエルは謎の罪悪感を刺激された。別に悪いことは何もしていないのに、彼には「この人を悲しませてはいけない」と思わせる何かがあるようだった。
「リエルのことを知りたいな。差し支えなければ、いろいろ教えてくれないか? 困っていることがあれば、力になりたいし……」
必死な顔でお願いされると、不思議と警戒心より先に親しみが湧いてきた。
――シオン様、おそるべし。
「私は十五歳で、これから王城で住み込みで働く予定です」
「奇遇だな、俺は城の魔塔勤めの魔法使いだ。一緒に城まで行こうか。 参考までに、魔塔勤めは信用ならない魔法使いが多いから気を付けろ」
「斬新な自己紹介ですね……」
リエルはサラダをつつく手を休めて、木製カップに手を伸ばした。
ほのかに光る魔法塗料で真っ赤な林檎を持った茶色いクマの絵が描いてある。両手で包み込むように持つと、手のひらがじんわりと温まった。
「リエル。俺は君の今までの話が聞きたいな。食事代のかわりに詳しく話してくれないかな?」
「食事代、ですか。そうですね……」
過去とは「さようなら」をしたばかりだが、他人に話してもいいかもしれない。食事代だと思えば、抵抗感も薄れる。
リエルは今までの身の上話を打ち明けた。すると、シオンはリエルの不遇に驚き、悲しみ、怒ってくれた。
「なんてひどい話なんだ。こんなことが許されるはずがない!」
物騒な発言をしているが、話を聞いてもらえて、共感してもらえた。
……家を出てよかった。
家を出なかったら、目の前のひとりと一匹には巡り合えなかったから。
「大丈夫だ。君は今から幸せになる。俺が保証するよ」
「ありがとうございます、シオン様は良い方ですね。同じ王城勤めでもありますし、心強いです」
車窓の外を見ると、曇り空が果てしなく広がっている。この国の住人誰もが見慣れた風景だ。
『瘴気竜に狙われた王国』。
ラクリマリア王国は、周辺国からそう呼ばれている。
いつからか、この国の空は分厚い瘴気の雲で覆われるようになった。
瘴気の雲の上には邪悪な黒い瘴気竜が居座っている。
瘴気竜はラクリマリア王国に執着していて、瘴気の雲を作ったり、気まぐれに地上に近づいて人々を脅かしたりする日々。
曇天のせいで、ラクリマリア王国では土地が痩せ、作物は育たない。
瘴気竜は地上近くに飛翔しても人や建築物に直接的な被害をもたらしたことはないが、人々はいつも「いつ瘴気竜が飛んでくるか」と恐れている。
国はなんとか成り立っている。今は、まだ。