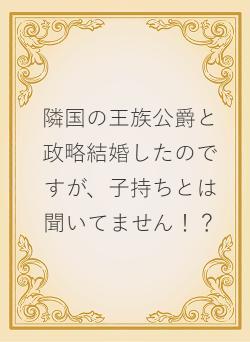――思い出す。思い出す。
天の高み。雲の向こう。
議論の声、冷えた理屈、選別の目。
地上で救いを求めて泣く人々の存在。
瘴気竜。王子。
あのとき、私はなぜ、何もできなかったのだろう。
リエルは、天界の天使だった。
天使として生まれたリエルは、生まれた瞬間から少女の姿だ。
金色の髪に、すみれ色の瞳。
背には、光を宿した白い羽が揺れていた。
生まれて最初に目にした光景は、無限に広がる青空と緑の大地。
そして、親のような気配を醸し出している性別不詳の大天使ジブリールだった。
天界には厳密な序列があり、大天使は世界の行方を決める権限を持つ。畏敬すべき存在だ。
「可愛い天使だ。誕生おめでとう」
ジブリールの声は優しかった。
大天使ジブリールは、陽光を溶かしたような金髪を高い位置で優雅に結い上げていて、瞳の色はエメラルド。肩に青いちび瘴気竜を乗せた姿は中性的で、どことなく侍女長に似ていた。
侍女長に初めて会ったときの「どこか懐かしい感じ」の正体は、この大天使だろう。
より正確に言うなら、「過去に地上で王妃になった天使」がこの大天使に似ているのかもしれない。
「私の名はジブリール。お前のママだ。性別がないからパパでもいい」
生まれたときから、リエルの頭の中には知識があった。
ジブリールが「こういう知識は持っていた方がいいだろう」と思ったことを必要な知識として持たせてくれたのだ。
「こっちのちび瘴気竜は、星竜のルキ。私が祝福を授けて天使として作り出したのだから、お前もまたジブリールと名乗るがいいね」
「ジブリール様は雲の上の方なので、同じ名前を名乗るのはためらわれます」
すると、ジブリールは「ほう、お前はしっかり者で賢いね」とキャンディをくれた。
キャンディは甘かった。
けれど、甘さのあとに、きゅっと舌を刺す酸味が残る。
「地上ではレモン味と呼ばれているよ」
「レモン味……」
無言で甘味を喜ぶリエルを見て、ジブリールは慈しむような微笑を浮かべた。
「このペンダントは、私が作った天使に渡すようにしているお守りだよ。お前の心身を邪悪なものから守ってくれるし、よきものを集めることもできる。肌身離さず、付けていなさい」
ジブリールはペンダントをくれた。
透明な卵型の宝石に羽がついたデザインのペンダントトップが綺麗で、リエルは一目で気に入った。
「ありがとうございます、ジブリール様」
「しかし、『雲の上』とは地上風の物言いをする。私が地上好きだから影響されたのかな? ここは雲の上なのだから、お前もまた雲の上の生き物なのだよ」
「本当ですね。不思議なことを申しました」
リエルを抱き上げて、ジブリールはよしよしと頭を撫でた。
「それでは、正式な場所以外では私に似た名前でリエルという愛称を名乗るがいいよ。可愛いであろう?」
「はい、ジブリール様」
リエルは、同時期に生まれた白猫の聖獣ケイティと姉妹のように育てられた。
「私たち大天使は、必要に応じて、もしくは気まぐれに眷属の天使を増やす。増えた子は仕事を手伝ってもらうこともあるし、愛でるだけのこともある。今、私の宮殿では働き手が足りているので、お前たちは何もしなくていい。好きに過ごしなさい」
大天使ジブリールの眷属天使は、「愛でられるだけ」の存在が圧倒的に多かった。天使たちは日々気ままに過ごしていた。
「存在するだけでいい。お前はただ、そこに咲く花のように美しくあればいいんだよ」
それは天界において、もっとも慈悲深い祝福の言葉だった。
けれど、リエルの胸に落ちたのは、冷たい澱のような違和感だ。
胸の奥に、言葉にならない違和感が沈んだ。
ここにいて、ただ咲いているだけでいい――その在り方を、どうしても受け入れられなかった。
永遠に続く青空、変化のない安寧。
その眩しすぎる光の中に閉じ込められて、自分が透明に透けて消えてしまいそうな、言いようのない焦燥がリエルの中に積もっていく。
ある日、緑の絨毯に寝そべって、リエルは呟いたものだ。
「ケイティ、私、何かしたい」
白猫のケイティはそんなリエルの額に乗り、ごろごろと喉を鳴らす。
「リエルは今呼吸をしていますわ」
「うん……」
そういうことが言いたかったわけじゃない。
リエルは吐息を震わせつつ、目を閉じた。白猫のケイティは柔らかくて暖かい。
規則正しい呼吸の音も、ごろごろと鳴る喉の音も、眠気を誘う。
だから、気持ちよく眠りを貪り、気づいたときには一日が過ぎている。
「ケイティ。私やっぱり、これを繰り返しているだけなのは、なんだか嫌」
「リエルは変なことを気にしますのね」
リエルはジブリールに会いに行った。
ジブリールは気まぐれで、いつどこにいるかわからない。
地上にふらりと降りていることもあれば、新しい天使や聖獣を愛でていることもある。
あちらこちらを探し回って、ようやく見つけたジブリールは羊の聖獣の群れの中で埋まって寝ていた。
「ルキよ、お前はできる子だ。剣を置いたあとはそれとなく人間たちに歌を広めるんだぞ。難しい? いやいや、お前ならできる。やってみなさい」
近寄ると、怪しい独り言が聞こえてくる。
「ルキよ、剣の近くにメッセージを刻めるかい。やってごらん。瘴気は宝石に吸われ、持ち主を守る。だが、真っ黒に汚れ切った宝石は、身につけているだけで持ち主を病ませる……石を破壊せよ。そののちに浄化せよ。一番良いのは、真実の愛の光で心を包んでやることだが……」
リエルとケイティが顔を見合わせていると、ふたりの接近に気づいた様子で、ジブリールは羊たちの中から出てきた。
頭から足先まで羊毛をまとい、無表情で「どうしたんだい」と問いかけてくる。
その姿に、リエルは一瞬、言葉を失った。
「ジブリール様。何かお仕事をさせてください」
「ふむ。リエルはやはり働き者の素質を持っている子だね。よろしい、これから天界会議があるから付いてきなさい」
大天使ジブリールは、天界会議の議題について教えてくれた。
「ルキフェルという堕天使が地上に降り、瘴気を纏った瘴気竜と化して人間の国を滅ぼそうとしている……まあ、私の子なのだが」
胸が、どくんと脈打った。
知らない名前のはずなのに、ジブリールの子だと言われると、その存在が他人とは思えなかった。
天界会議は騒然としていて、針の筵のようだった。
天使たちは円環の座に集い、淡々と、しかし苛立ちを含んで語り合った。
語られる言葉のひとつひとつが、誰かの生と死を決めている。
リエルは少し怯えながら白猫の聖獣ケイティを膝に乗せ、大天使ジブリールの膝に座った。
「リエル、ケイティ。怖がることはないよ。お茶を飲んでくつろぎなさい」
「はい、いただきます、ジブリール様」
お茶をいただくと、ジブリールは「うんうん」と頷いて手を挙げ、会議で発言する。
「私の子は、人間のように悩んだり憎しみに心を染めて暴走したりする。だが、子供のすることだから、許してあげておくれ。人間に似ているだけあって、間違えることもあるのだよ。満足したら冷静になるだろうさ」
慈悲深いようでいて無責任な言葉に、天使たちから非難の声が上がる。
「国をひとつ滅ぼそうとしているのに反抗期の子供のいたずらみたいに語るな」
「羽をむしり取ってやりたい」
「責任を取れ、責任を」
ジブリールは我が子を処罰したくないらしい。
しかし、他の天使たちは「それではいけない」と糾弾している。
リエルはそんな意向を理解しつつ、会議の話に耳を傾けた。
天の高み。雲の向こう。
議論の声、冷えた理屈、選別の目。
地上で救いを求めて泣く人々の存在。
瘴気竜。王子。
あのとき、私はなぜ、何もできなかったのだろう。
リエルは、天界の天使だった。
天使として生まれたリエルは、生まれた瞬間から少女の姿だ。
金色の髪に、すみれ色の瞳。
背には、光を宿した白い羽が揺れていた。
生まれて最初に目にした光景は、無限に広がる青空と緑の大地。
そして、親のような気配を醸し出している性別不詳の大天使ジブリールだった。
天界には厳密な序列があり、大天使は世界の行方を決める権限を持つ。畏敬すべき存在だ。
「可愛い天使だ。誕生おめでとう」
ジブリールの声は優しかった。
大天使ジブリールは、陽光を溶かしたような金髪を高い位置で優雅に結い上げていて、瞳の色はエメラルド。肩に青いちび瘴気竜を乗せた姿は中性的で、どことなく侍女長に似ていた。
侍女長に初めて会ったときの「どこか懐かしい感じ」の正体は、この大天使だろう。
より正確に言うなら、「過去に地上で王妃になった天使」がこの大天使に似ているのかもしれない。
「私の名はジブリール。お前のママだ。性別がないからパパでもいい」
生まれたときから、リエルの頭の中には知識があった。
ジブリールが「こういう知識は持っていた方がいいだろう」と思ったことを必要な知識として持たせてくれたのだ。
「こっちのちび瘴気竜は、星竜のルキ。私が祝福を授けて天使として作り出したのだから、お前もまたジブリールと名乗るがいいね」
「ジブリール様は雲の上の方なので、同じ名前を名乗るのはためらわれます」
すると、ジブリールは「ほう、お前はしっかり者で賢いね」とキャンディをくれた。
キャンディは甘かった。
けれど、甘さのあとに、きゅっと舌を刺す酸味が残る。
「地上ではレモン味と呼ばれているよ」
「レモン味……」
無言で甘味を喜ぶリエルを見て、ジブリールは慈しむような微笑を浮かべた。
「このペンダントは、私が作った天使に渡すようにしているお守りだよ。お前の心身を邪悪なものから守ってくれるし、よきものを集めることもできる。肌身離さず、付けていなさい」
ジブリールはペンダントをくれた。
透明な卵型の宝石に羽がついたデザインのペンダントトップが綺麗で、リエルは一目で気に入った。
「ありがとうございます、ジブリール様」
「しかし、『雲の上』とは地上風の物言いをする。私が地上好きだから影響されたのかな? ここは雲の上なのだから、お前もまた雲の上の生き物なのだよ」
「本当ですね。不思議なことを申しました」
リエルを抱き上げて、ジブリールはよしよしと頭を撫でた。
「それでは、正式な場所以外では私に似た名前でリエルという愛称を名乗るがいいよ。可愛いであろう?」
「はい、ジブリール様」
リエルは、同時期に生まれた白猫の聖獣ケイティと姉妹のように育てられた。
「私たち大天使は、必要に応じて、もしくは気まぐれに眷属の天使を増やす。増えた子は仕事を手伝ってもらうこともあるし、愛でるだけのこともある。今、私の宮殿では働き手が足りているので、お前たちは何もしなくていい。好きに過ごしなさい」
大天使ジブリールの眷属天使は、「愛でられるだけ」の存在が圧倒的に多かった。天使たちは日々気ままに過ごしていた。
「存在するだけでいい。お前はただ、そこに咲く花のように美しくあればいいんだよ」
それは天界において、もっとも慈悲深い祝福の言葉だった。
けれど、リエルの胸に落ちたのは、冷たい澱のような違和感だ。
胸の奥に、言葉にならない違和感が沈んだ。
ここにいて、ただ咲いているだけでいい――その在り方を、どうしても受け入れられなかった。
永遠に続く青空、変化のない安寧。
その眩しすぎる光の中に閉じ込められて、自分が透明に透けて消えてしまいそうな、言いようのない焦燥がリエルの中に積もっていく。
ある日、緑の絨毯に寝そべって、リエルは呟いたものだ。
「ケイティ、私、何かしたい」
白猫のケイティはそんなリエルの額に乗り、ごろごろと喉を鳴らす。
「リエルは今呼吸をしていますわ」
「うん……」
そういうことが言いたかったわけじゃない。
リエルは吐息を震わせつつ、目を閉じた。白猫のケイティは柔らかくて暖かい。
規則正しい呼吸の音も、ごろごろと鳴る喉の音も、眠気を誘う。
だから、気持ちよく眠りを貪り、気づいたときには一日が過ぎている。
「ケイティ。私やっぱり、これを繰り返しているだけなのは、なんだか嫌」
「リエルは変なことを気にしますのね」
リエルはジブリールに会いに行った。
ジブリールは気まぐれで、いつどこにいるかわからない。
地上にふらりと降りていることもあれば、新しい天使や聖獣を愛でていることもある。
あちらこちらを探し回って、ようやく見つけたジブリールは羊の聖獣の群れの中で埋まって寝ていた。
「ルキよ、お前はできる子だ。剣を置いたあとはそれとなく人間たちに歌を広めるんだぞ。難しい? いやいや、お前ならできる。やってみなさい」
近寄ると、怪しい独り言が聞こえてくる。
「ルキよ、剣の近くにメッセージを刻めるかい。やってごらん。瘴気は宝石に吸われ、持ち主を守る。だが、真っ黒に汚れ切った宝石は、身につけているだけで持ち主を病ませる……石を破壊せよ。そののちに浄化せよ。一番良いのは、真実の愛の光で心を包んでやることだが……」
リエルとケイティが顔を見合わせていると、ふたりの接近に気づいた様子で、ジブリールは羊たちの中から出てきた。
頭から足先まで羊毛をまとい、無表情で「どうしたんだい」と問いかけてくる。
その姿に、リエルは一瞬、言葉を失った。
「ジブリール様。何かお仕事をさせてください」
「ふむ。リエルはやはり働き者の素質を持っている子だね。よろしい、これから天界会議があるから付いてきなさい」
大天使ジブリールは、天界会議の議題について教えてくれた。
「ルキフェルという堕天使が地上に降り、瘴気を纏った瘴気竜と化して人間の国を滅ぼそうとしている……まあ、私の子なのだが」
胸が、どくんと脈打った。
知らない名前のはずなのに、ジブリールの子だと言われると、その存在が他人とは思えなかった。
天界会議は騒然としていて、針の筵のようだった。
天使たちは円環の座に集い、淡々と、しかし苛立ちを含んで語り合った。
語られる言葉のひとつひとつが、誰かの生と死を決めている。
リエルは少し怯えながら白猫の聖獣ケイティを膝に乗せ、大天使ジブリールの膝に座った。
「リエル、ケイティ。怖がることはないよ。お茶を飲んでくつろぎなさい」
「はい、いただきます、ジブリール様」
お茶をいただくと、ジブリールは「うんうん」と頷いて手を挙げ、会議で発言する。
「私の子は、人間のように悩んだり憎しみに心を染めて暴走したりする。だが、子供のすることだから、許してあげておくれ。人間に似ているだけあって、間違えることもあるのだよ。満足したら冷静になるだろうさ」
慈悲深いようでいて無責任な言葉に、天使たちから非難の声が上がる。
「国をひとつ滅ぼそうとしているのに反抗期の子供のいたずらみたいに語るな」
「羽をむしり取ってやりたい」
「責任を取れ、責任を」
ジブリールは我が子を処罰したくないらしい。
しかし、他の天使たちは「それではいけない」と糾弾している。
リエルはそんな意向を理解しつつ、会議の話に耳を傾けた。