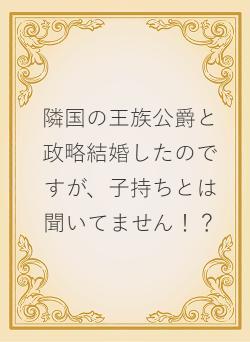(……シオン様?)
「あたくしが認識阻害の力を使っているから、シオン様はあなたに気づいていませんわ」
「ケイティってすごいんだね」
「リエル。上をごらんなさい」
ケイティは少し緊迫した気配で上を示す。
促されるまま視線を上げて、リエルは身を強張らせた。
雲の切れ間から、もやもやとした邪悪な瘴気をまとった巨大な瘴気竜が、ゆっくりと首を覗かせている。目を疑う光景だった。
(――瘴気竜……!)
声にならない悲鳴が、喉の奥で絡まった。
肺が凍りついたように息が詰まり、指先から感覚が抜けていく。
「おはよう、雲の上の君。そろそろ君が動く頃合いかと思って、今宵も待っていたよ」
魔塔の頂上に立つシオンが、瘴気竜に語り掛けている。
「悪いが、研究はまだ完成していない。あともう少しなんだ。君がそれまで眠っていられるよう、俺は天に祈ろう」
大きく両手を広げ、曇天を抱きしめるようにして、シオンは魔法の呪文らしき文言を唱えた。それに応じて、彼を中心とした虚空に魔法の光が細い線を描いていく。
金色の線が円を描き、内側に小さな円が無数に生まれて。円と円を結ぶように、蒼銀色の光の線が複雑な幾何学模様を描いていく。細かく隙間を埋めていくのは、魔法文字か。
「リエル。あれは契約魔法陣よ。シオン様は定期的にあれをしているの」
「契約……?」
ケイティが教えてくれる。
まるで、英雄物語の舞台の一幕でも見ている気分だ。
「天界の神々よ、天使の子孫であるハルティシオンが奇跡を願います……」
そんな声が聞こえて、リエルはぞくりと身を震わせた。
魔法陣が天に捧げられるように溶けていき、遥か上空で応える気配が感じられる。それにより、シオンの体から、何か大切なものが削り取られて天に吸われていく。
(……魔力? いえ、これは――)
吸われているものは、魔力などという生易しいものではなかった。もっと生きるために欠かせない、切実なもの。――生命力だ。
本能めいた感覚でそれを理解して、リエルの足が震える。
(だ……だめ!)
シオンの中にあったはずの温度が、呼吸が、命そのものが、光に変換されて天へと引き抜かれていく。
しかも、失った隙間を埋めるように、黒い瘴気が集まってくる。
瘴気竜の額からだ。
そこから噴き出した瘴気が、煙のようにうぞぞぞと降りてくる。その瘴気は、シオンの体へと纏わりつき、体の中へと侵入していく。
(何をしているの⁉ こんなの、絶対に体に悪いじゃない!)
リエルが「止めなきゃ」と思ったのを察したように、ケイティが鋭く警告する。
「止めると国が滅びますわよ」
「‼」
「シオン様は、定期的にあの儀式をして瘴気竜から国を守っているのですわ」
高所から見渡す王都の夜景に、そこで暮らす人々の生命を意識させられる。
(そん、な……)
リエルが硬直している間に、瘴気竜は雲の向こうに姿を消した。沈静化されたのだ。
「リエル。あの瘴気竜は、堕天使よ」
「堕天使?」
ケイティは魔塔の屋上に降り立ち、リエルを下ろした。
その瞬間、シオンが咳き込み、鮮やかな血を吐く。
青年の体がぐらりと傾くのが見えて、リエルは今度こそ駆けだした。
「シオン様!」
倒れ込む体のそばに膝をつき、覗き込む。
震える手でその頬に触れると、氷のように冷たくて、リエルは心臓が氷で撫でられたように青ざめた。
朦朧とした様子でうっすらと目を開けるシオンは、自分を覗き込むリエルを見て夢を見ているような表情を浮かべた。
形のよい唇が、弱々しく息を吐く。
「天使様」
「……!」
金色の瞳は、リエルを見ているようで、どこか遠くを見つめていた。
「会いに来てくださったんですね。ずっと、会いたかったんです」
純情に呟く声に、喉が詰まったように苦しくなる。
――この人は今、私ではなくて別の誰かが会いに来てくれたと思っているんだ。
(私が本当に天使様だったらよかったのに)
なんだか泣いてしまいそうな心に蓋をして、リエルは彼の冷えた手を両手で握りしめた。
「……会いに来ました」
この人の天使様は、どんな風に喋るのだろう。そんなことを考えながら涙を落とすと、シオンは目を瞬かせて口元を拭い、驚いた様子で身を起こした。
「……リエル? これは、現実か?」
「あ……すみません」
「どうしてここに……、なぜ、泣いている? ……服が濡れているじゃないか!」
狼狽えた様子でハンカチを取り出し、リエルの目元に当てるシオンは、自分が血を吐いて倒れたことなど忘れたような顔をしていた。
――会いたかった人に会えたのだと、夢を見させることができなかった。
でも、騙すみたいになるよりも、気づいてもらえた方がよかったのかもしれない。
正解がわからない迷宮に迷い込んだような気分で俯くリエルの耳に、ぱちん、と指を鳴らす音が届く。
すると、ふわりと全身を暖かな風が撫でて、濡れていた服があっという間に乾いた。魔法だ、と理解してリエルは慌てた。
「お疲れなのに……魔法を使わせてしまって、すみません」
「疲れてないよ」
「……嘘ばかり」
――人間は嘘つきだ。
リエルは思った。
嘘には種類があって、誰かを貶めて自分が気持ちよくなるための嘘や、自分を守ったり実際より大きく立派に見せるための嘘がある。けれど、それ以外にも、誰かの心を慰めたり、傷つくのを防いだり、元気つけるための嘘もあって、シオンはそんな嘘をついている。だからリエルは、嘘つきな彼を嫌いになれない。
(……私のさっきの嘘は、どっちの嘘だっただろう)
「ケイティがここに連れてきたのか? とりあえず、外は冷えるから中へ入ろう」
シオンはリエルの肩を抱き、魔塔の中へと招き入れた。
ケイティは小さなサイズになり、澄まし顔で付いてくる。
◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
暖かな室内で上質なファブリックのソファに落ち着くと、外との気温の差のせいか、精神的なショックのせいか、頭の奥が小さくじんじんと痛む。
連続で現実を疑うような出来事が起きて、なんだか疲れてしまった。それに、自分に対する残念な気持ちが湧いている。
(私、何もできなかった……)
今も、何もできていない。――そんな思いがある。
「言い伝えにある通り、王族は天使の末裔なんだ。だから時折、俺のように天界に祈りを届かせられる能力者が生まれる……母もそうだった」
シオンは隠し事が露見した少年のような顔で、さきほどの事件について告白した。
「俺はその能力を活かし、定期的にさっきみたいに天界に頼んで瘴気竜を大人しく寝かしつけてもらっているんだ」
窓の外では、夜空を覆っていた雲に切れ間ができて、月明かりが清らかに光の筋を見せている。
この国では貴重な月光の美しさに、リエルは見惚れた。
「……綺麗ですね」
「俺があれをしなくても済むように、魔術装置を研究してる。一年以内には完成させるつもりだ」
シオンはごそごそと懐を探り、赤い糸巻きを取り出した。
赤い糸巻きを見た瞬間、リエルの脳裏に薔薇色の髪の魔女の名が浮かぶ。
『赤い糸の魔女』だ。
その連想を裏切ることなく、シオンは糸巻きを軽く握りしめ、その名を呼ぶ。
「ロザミア。来客にハーブティを出してほしい」
それを聞いた瞬間に、リエルの心にまた影が差す。
(私に言ってくれればいいのに)
王城勤めの侍女なのに、お客様のように何もしないでもてなされている。それが、なんだか情けなかった。
ロザミアはすぐにやってきて、部屋の外からノックが鳴る。
「殿下。人使いが荒いあなたのために、部下が仕方なくやってきましたよ」
扉を開けてワゴンを押し、ロザミアが入ってくる。
「あら殿下。来客というのは彼女でしたか。こんな夜中に部屋に連れ込むなんて」
「想像しているような不埒なことはしないよ。お茶をありがとう、もうお下がり」
じゃれ合うようなやり取りをして、ロザミアは軽く手を振りながら部屋を出ていった。
その後ろ姿を見送るシオンの横顔は、どこか力が抜けている。
「ロザミアは幼馴染なんだ。女装や魔女を名乗る趣味は理解できないが、料理長と気が合いそうだよな――」
リエルは言葉が耳に入らなくなっていた。ロザミアが男性だという情報を認識しそびれて、またこっそりと嫉妬に思い悩んでしまう。
(今日はなんだか、よくないことばかり考えちゃうみたい)
その顔色の悪さを眠気や疲れによるものだと思ったのか、シオンは気づかわしげに表情を曇らせた。
「リエル。それを飲んだら部屋に送るよ。明日も仕事だろう? 睡眠を摂らないとな」
「ありがとうございます」
温かいカモミールティーは口当たりが優しく、癒される味だ。ほっとする。
「俺はつい、自分の欲のために、君の大切な時間を奪ってしまう。ほどほどにしないといけないな」
「いえ……私は大丈夫です。なんだか、私の方こそ、何もできないのに貴重なお時間を使わせてしまっていて……」
リエルが首を横に振ると、シオンは一瞬だけ、迷子のような目になった。
「俺にとっては、君と過ごす時間が一番、貴重だ」
何かを言い返したくなって、けれど、飲み込んでしまう。
触れたら壊れてしまいそうな、あるいは、触れた途端に消えてしまいそうな危うい静寂に、心がざわざわとする。それをかろうじて抑え込んで、リエルは頭を下げた。
(ああ、困ったな)
一年の契約関係だ。
これ以上、踏み込んではいけないのに。
結末を想像するだけで呼吸が止まるほど苦しくなっている自分に、リエルは気づかないふりができなかった。
◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
シオンの体調は最悪だった。
天界に生命力を削られ、瘴気を身に引き受けた反動が、内側からじわじわと効いてくる。
呼吸を整え、平静を装ってはいるが、放っておけばまた血を吐くだろう。慣れている。いつものことだ。
それでも、リエルが自分の近くにいて、シオンの名を呼び、心配してくれる。
それだけで体の重さが少しだけ軽くなるのだから、我ながら単純だと思う。
(……まったく)
かつては違った。
天使様は、触れてはいけない、特別な存在だった。
だが今は――。
思い出すのは、赤くなった頬。
こめかみに口づけた瞬間の、あからさまな動揺。小さな耳に、淡く色づく可憐な唇。
(……可愛い)
守りたい。今は、そう思う。
彼女は自立している。
慎重で、現実的で、甘えない。
誰かに縋ることを選ばず、不安を飲み込んででも、自分の足で立とうとする――そんな年下の少女だ。
シオンは彼女を包み込みたいと思ってしまう。
誰にも渡さず、自分のものにしてしまいたいと欲してしまう。
これは信仰ではない。崇拝でもない。
(……厄介だな)
自分が長く生きられないことは、わかっている。
天界との契約は、確実に命を削っていく。
彼女の人生を、短命な自分が囲い込む資格なんてない。
ふさわしい相手に託して、彼女を幸せにしてもらうのがいい。
……わかっている。
それでも。自分がそばにいたくて、隣を他の男に譲りたくなくて、苦しい。
ほんの一年。
期間限定でいい。
嘘でも、偽りでもいい。
彼女が自分を見て笑い、名前を呼び、隣に立つ時間を――せめて今だけは、手放さずにいさせてほしい。
パーティの日、彼女の隣に立てるその夜を思い浮かべて、シオンは静かに目を閉じた。