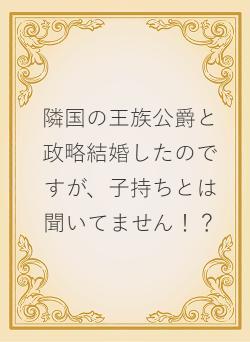魔塔への応援勤務は一日で終わり、翌日からは元の職場へ戻された。
王城勤めを始めて、まだ日が浅い。
けれど、魔塔から慣れ親しんだ職場に戻ると、「ここが居場所だ」という感情が湧く。見慣れた先輩侍女たちに囲まれると、肩の奥に溜まっていた力が自然と抜けた。
「おかえりなさい、リエル」
「おかえり。ひどい目に遭ったりしなかった?」
「魔塔の話を聞かせて!」
侍女仲間と話をしていると、侍女長が会話に入ってくる。
「リエル。あなたが魔塔の魔法使いと光返しの夜会に出席するので休日を与えるように、と魔塔から正式に命令が来ましたよ」
光返しの夜会というのは、シオンが言っていたパーティのことだろう。
「確かにパーティの出席の約束をしましたが、光返しの夜会とはどのようなパーティなんですか?」
「昔は儀礼的な意味合いが強かったのですが、最近は普通のパーティーと変わりませんよ」
侍女仲間から教えてくれた説明を合わせると、まず、この国には天使が王族に嫁いだ言い伝えがあるという。
それは、リエルも知っている話だ。
そして、ここからが初耳の情報なのだが、王妃になった天使は、王国に新しい季節の祝祭を作ったらしい。
地上を見守ってくれる天界に感謝して、天に向けて光り輝くような音楽や感謝の言葉を捧げる――それが光返しの夜会の発祥なのだ。
「リエル。魔塔の魔法使いって誰? 魔塔で知り合ったの?」
「どんなドレスを着るの?」
「当日はお姉さんがお化粧してあげるわ!」
侍女たちは自分のことのように張り切り出した。
相手が第二王子だという事実は、到底口にできない。
身分の問題以前に、説明するだけで余計な騒ぎになりそうだ。
そのため曖昧に話を濁していると、侍女のひとりが思い出したように眉を顰める。
「……まさか、例の『たぬき魔法使い』じゃないでしょうね?」
その一言で、誰を指しているのかがすぐにわかってしまい、リエルは言葉に詰まった。
否定も肯定もしないまま一瞬黙り込んでしまったのが、どうやら答えになってしまったらしい。
「えっ、あのたぬきと!?」
「まあまあ、意外と本気だったのねえ!」
ざわり、と空気が弾む。驚きと好奇心が混ざった声が重なり、視線が一斉にリエルへ集まった。
リエルはどう返していいかわからず、困ったような微笑を浮かべるしかなかった。
「まあ、好意はわかりやすく向けられてたものねえ!」
「大丈夫? 嫌だったら振ってもいいのよ。お姉さんが一緒にお断りしてあげようか?」
働くうちに気づいたが、この職場の侍女たちは総じて世話焼きで、情に厚い。
和気藹々とした職場は、居心地がいい。
リエルが満更でもない気分で侍女仕事をしていると、コニーが「見て」と肘を突いてきた。
「王太子カリオン殿下と婚約者のオフィーリア様よ」
促されて見ると、廊下を仲睦まじい雰囲気で歩く男女がいた。
群青色の髪をした王太子カリオンは眼鏡をしていて、愛しそうな視線を婚約者に注いでいる。
婚約者であるオフィーリアは、ブルーローゼ侯爵家の長女だ。心根を表すような真っ直ぐな象牙色の髪を揺らしてひだまりのような微笑を湛え、王太子に寄り添っている。
「お似合いね」
「幼い頃からの両想いなんですって」
侍女たちが遠目に褒め称える中、リエルは別の箇所を見ていた。
王太子と婚約者の後ろに、小さな男の子の幽霊がいる。
象牙色の髪色がオフィーリアによく似ているので、血縁者なのかもしれない。
「王太子殿下がしっかりなさっててよかったわよね。第二王子殿下は初恋の人がいるからってパーティにも顔を出さなくて縁談も全部断ってるんだって」
「あら、でも今回は『赤い糸の魔女』様とご出席予定って噂よ」
「ロザミア様は幼馴染ですものね。伯爵家のご令嬢でもあるし、婚約者候補筆頭だから婚約発表するのかも……」
(婚約者候補筆頭だったの、ロザミアさん?)
脳裏にシオンとロザミアの姿が思い浮かぶ。
並ぶふたりは間違いなく釣り合いが取れていた。そんな思いと同時に、胸の奥にどろりとした黒い感情が染みを作って、心が軋む。
以前ケイティが言っていた「あなたが後で傷つかないために忠
告しますけど」という声が思い出される。
――誰かを好きになると、傷つくこともある……。
(……気にするの、やめよう)
リエルは、胸の奥に芽生えかけた感情ごと、そっと自分の心に蓋をした。
傷つくからと言われても、気づいたらどうしようもなく、落ちている。
恋って、厄介だ。
◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
その夜。
リエルが自室の寝台に横になろうとしたとき、かすかな泣き声が聞こえた。
「えーん、ふえーん……」
幽霊の泣き声だ。
姿を見なくても、なんとなくわかる。リエルはそっと起き上がり、窓の外を見た。
真っ暗な中庭に、小さな男の子がいる。
日中に見かけた幽霊だ。
リエルはショールを羽織り、男の子の元に行った。
「どうしたの?」
問いかけると、男の子はうるうるとした瞳で縋るように見上げてくる。
「リアおねえしゃまの、うびあ……おっちゃったの……」
だいぶ舌足らずだが、「リアお姉様の指輪が落ちちゃった」と言っているのではないだろうか。
リアお姉様とは、おそらくオフィーリアだ。
「わかった。探してあげる」
衛兵の巡回をやり過ごし、裾をまくって池に手を入れる。
冷たい水の底を探ると、指先に硬い感触が触れた。それを掴んだ瞬間、胸の奥がふっと緩む。
「あった」
月光にきらりと光る指輪を見せると、子供は白い歯を見せて笑顔を弾けさせた。
「そえ、リアおねえしゃまの!」
「オフィーリア様にお返しするわね」
「うん!」
いつも幽霊が喜ぶと光るペンダントは、今宵も煌めいた。色は、優しいピンク色だ。
リエルが濡れた裾を気にしながら立ち上がった、その時だった。
「夜ふかしさんね、リエル?」
不意に、背後から声をかけられる。
振り向くと、回廊の影にケイティがいた。
「ちょうどいいわ、こっちに来なさい。静かにね」
ケイティは尻尾を振り、魔塔の近くまでリエルを導いた。
そして、ゆらりと輪郭を揺らしてその姿を変身させた。
小さな白猫の姿から、人を背中に乗せられるくらい大きなサイズに。
「……ケイティって、何者?」
「ふふん。とってもえらい、猫様です。さあ、特別に乗せてあげます。背中にお座りなさい」
「の、乗る……っ?」
遠慮してはいけないのだろうか、と逡巡していると、ケイティはぐいぐいと迫ってくる。
押されるがまま乗ると、全身がふわりと宙に浮いた。
「きゃあっ?」
「夜はお静かに。うふふ、心配しなくても落としたりしませんわ」
なんと、ケイティは空を飛翔した。
幽霊だからだろうか。翼もないのに、安定感抜群でふわふわと高度を上げていく。
初めての体験に、リエルはどきどきしながらケイティの首にすがりついた。
「ごらんなさい、リエル」
「うん?」
示された先、魔塔の頂上に、見知った姿があった。
いつも結んでいる紫の髪を奔放に風に靡かせる長身の青年。
夜気の中で、そこだけ空気が澄んでいるような存在感のある魔法使いの王子――シオンだ。
王城勤めを始めて、まだ日が浅い。
けれど、魔塔から慣れ親しんだ職場に戻ると、「ここが居場所だ」という感情が湧く。見慣れた先輩侍女たちに囲まれると、肩の奥に溜まっていた力が自然と抜けた。
「おかえりなさい、リエル」
「おかえり。ひどい目に遭ったりしなかった?」
「魔塔の話を聞かせて!」
侍女仲間と話をしていると、侍女長が会話に入ってくる。
「リエル。あなたが魔塔の魔法使いと光返しの夜会に出席するので休日を与えるように、と魔塔から正式に命令が来ましたよ」
光返しの夜会というのは、シオンが言っていたパーティのことだろう。
「確かにパーティの出席の約束をしましたが、光返しの夜会とはどのようなパーティなんですか?」
「昔は儀礼的な意味合いが強かったのですが、最近は普通のパーティーと変わりませんよ」
侍女仲間から教えてくれた説明を合わせると、まず、この国には天使が王族に嫁いだ言い伝えがあるという。
それは、リエルも知っている話だ。
そして、ここからが初耳の情報なのだが、王妃になった天使は、王国に新しい季節の祝祭を作ったらしい。
地上を見守ってくれる天界に感謝して、天に向けて光り輝くような音楽や感謝の言葉を捧げる――それが光返しの夜会の発祥なのだ。
「リエル。魔塔の魔法使いって誰? 魔塔で知り合ったの?」
「どんなドレスを着るの?」
「当日はお姉さんがお化粧してあげるわ!」
侍女たちは自分のことのように張り切り出した。
相手が第二王子だという事実は、到底口にできない。
身分の問題以前に、説明するだけで余計な騒ぎになりそうだ。
そのため曖昧に話を濁していると、侍女のひとりが思い出したように眉を顰める。
「……まさか、例の『たぬき魔法使い』じゃないでしょうね?」
その一言で、誰を指しているのかがすぐにわかってしまい、リエルは言葉に詰まった。
否定も肯定もしないまま一瞬黙り込んでしまったのが、どうやら答えになってしまったらしい。
「えっ、あのたぬきと!?」
「まあまあ、意外と本気だったのねえ!」
ざわり、と空気が弾む。驚きと好奇心が混ざった声が重なり、視線が一斉にリエルへ集まった。
リエルはどう返していいかわからず、困ったような微笑を浮かべるしかなかった。
「まあ、好意はわかりやすく向けられてたものねえ!」
「大丈夫? 嫌だったら振ってもいいのよ。お姉さんが一緒にお断りしてあげようか?」
働くうちに気づいたが、この職場の侍女たちは総じて世話焼きで、情に厚い。
和気藹々とした職場は、居心地がいい。
リエルが満更でもない気分で侍女仕事をしていると、コニーが「見て」と肘を突いてきた。
「王太子カリオン殿下と婚約者のオフィーリア様よ」
促されて見ると、廊下を仲睦まじい雰囲気で歩く男女がいた。
群青色の髪をした王太子カリオンは眼鏡をしていて、愛しそうな視線を婚約者に注いでいる。
婚約者であるオフィーリアは、ブルーローゼ侯爵家の長女だ。心根を表すような真っ直ぐな象牙色の髪を揺らしてひだまりのような微笑を湛え、王太子に寄り添っている。
「お似合いね」
「幼い頃からの両想いなんですって」
侍女たちが遠目に褒め称える中、リエルは別の箇所を見ていた。
王太子と婚約者の後ろに、小さな男の子の幽霊がいる。
象牙色の髪色がオフィーリアによく似ているので、血縁者なのかもしれない。
「王太子殿下がしっかりなさっててよかったわよね。第二王子殿下は初恋の人がいるからってパーティにも顔を出さなくて縁談も全部断ってるんだって」
「あら、でも今回は『赤い糸の魔女』様とご出席予定って噂よ」
「ロザミア様は幼馴染ですものね。伯爵家のご令嬢でもあるし、婚約者候補筆頭だから婚約発表するのかも……」
(婚約者候補筆頭だったの、ロザミアさん?)
脳裏にシオンとロザミアの姿が思い浮かぶ。
並ぶふたりは間違いなく釣り合いが取れていた。そんな思いと同時に、胸の奥にどろりとした黒い感情が染みを作って、心が軋む。
以前ケイティが言っていた「あなたが後で傷つかないために忠
告しますけど」という声が思い出される。
――誰かを好きになると、傷つくこともある……。
(……気にするの、やめよう)
リエルは、胸の奥に芽生えかけた感情ごと、そっと自分の心に蓋をした。
傷つくからと言われても、気づいたらどうしようもなく、落ちている。
恋って、厄介だ。
◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
その夜。
リエルが自室の寝台に横になろうとしたとき、かすかな泣き声が聞こえた。
「えーん、ふえーん……」
幽霊の泣き声だ。
姿を見なくても、なんとなくわかる。リエルはそっと起き上がり、窓の外を見た。
真っ暗な中庭に、小さな男の子がいる。
日中に見かけた幽霊だ。
リエルはショールを羽織り、男の子の元に行った。
「どうしたの?」
問いかけると、男の子はうるうるとした瞳で縋るように見上げてくる。
「リアおねえしゃまの、うびあ……おっちゃったの……」
だいぶ舌足らずだが、「リアお姉様の指輪が落ちちゃった」と言っているのではないだろうか。
リアお姉様とは、おそらくオフィーリアだ。
「わかった。探してあげる」
衛兵の巡回をやり過ごし、裾をまくって池に手を入れる。
冷たい水の底を探ると、指先に硬い感触が触れた。それを掴んだ瞬間、胸の奥がふっと緩む。
「あった」
月光にきらりと光る指輪を見せると、子供は白い歯を見せて笑顔を弾けさせた。
「そえ、リアおねえしゃまの!」
「オフィーリア様にお返しするわね」
「うん!」
いつも幽霊が喜ぶと光るペンダントは、今宵も煌めいた。色は、優しいピンク色だ。
リエルが濡れた裾を気にしながら立ち上がった、その時だった。
「夜ふかしさんね、リエル?」
不意に、背後から声をかけられる。
振り向くと、回廊の影にケイティがいた。
「ちょうどいいわ、こっちに来なさい。静かにね」
ケイティは尻尾を振り、魔塔の近くまでリエルを導いた。
そして、ゆらりと輪郭を揺らしてその姿を変身させた。
小さな白猫の姿から、人を背中に乗せられるくらい大きなサイズに。
「……ケイティって、何者?」
「ふふん。とってもえらい、猫様です。さあ、特別に乗せてあげます。背中にお座りなさい」
「の、乗る……っ?」
遠慮してはいけないのだろうか、と逡巡していると、ケイティはぐいぐいと迫ってくる。
押されるがまま乗ると、全身がふわりと宙に浮いた。
「きゃあっ?」
「夜はお静かに。うふふ、心配しなくても落としたりしませんわ」
なんと、ケイティは空を飛翔した。
幽霊だからだろうか。翼もないのに、安定感抜群でふわふわと高度を上げていく。
初めての体験に、リエルはどきどきしながらケイティの首にすがりついた。
「ごらんなさい、リエル」
「うん?」
示された先、魔塔の頂上に、見知った姿があった。
いつも結んでいる紫の髪を奔放に風に靡かせる長身の青年。
夜気の中で、そこだけ空気が澄んでいるような存在感のある魔法使いの王子――シオンだ。