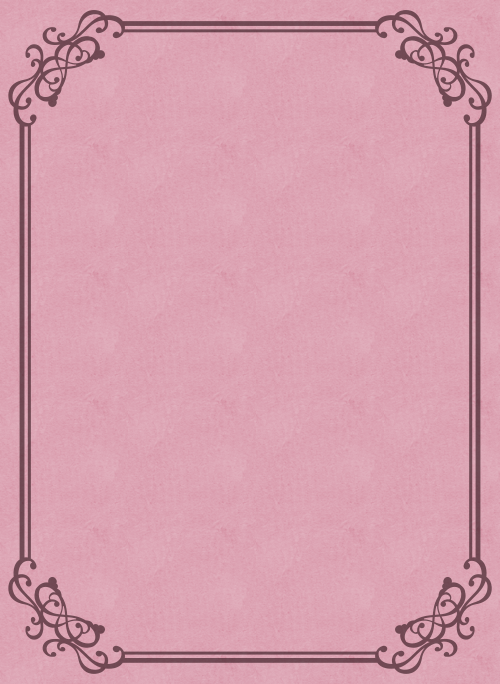「うん。俺のこと大好きって味」
「なっ、なにそれ…!」
「だって恋するほど甘くなるんだから、そーゆーことでしょ?」
後ろから抱きしめられてるから顔は見えないけど、叶兎くん絶対に楽しそうに笑っている。
「ね、胡桃。やっぱ血だけじゃ足りないんだけど」
「…だ、ためだよここ一応執務室!!」
何となく、そうなる気がしてた。
叶兎くんがこのモードになるとほんとに止まらない。
こんなとこ誰かに見られたら…恥ずか死ぬ。
勢いで立ち上がろうとした、その瞬間。
手首を掴まれて、ぐっと引き戻された。
「わっ……!?」
声が漏れるのと同時に、視界がくるりと反転した。
背中に、柔らかいはずのソファの背もたれがぶつかる。
逃げ場のない位置に追い込まれたと気づいた時にはもう遅かった。
気づけば叶兎くんが、上から覆いかぶさるように私を閉じ込めている。
腕と腕の間に囲われて、視界いっぱいに広がるのは至近距離の彼の顔だけ。
距離が近すぎて、息遣いまで分かる。