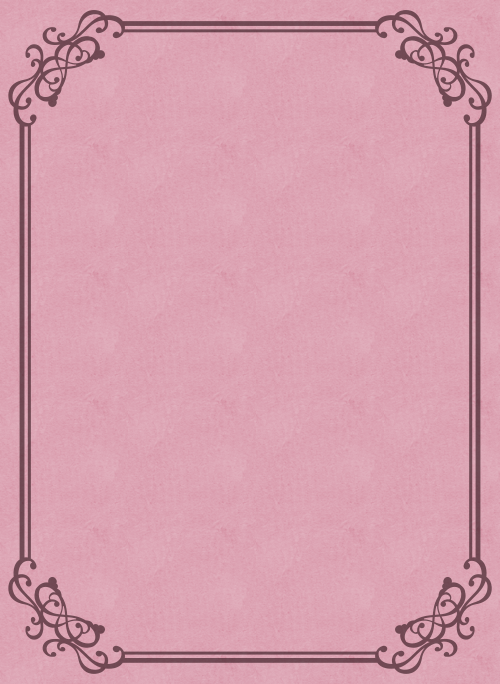…なのに。
叶兎くんの指は、そっと私の首元に触れてきた。
唇が触れるよりも先に吐息がかかって、ぞくっと背筋が震える。
「力抜いて」
囁く声に、逆らえなくなる。
言われるまま目を閉じると、次の瞬間。
ちくり、とした小さな刺激。
でも一瞬で、すぐにそれは熱に変わる。
吸われる感覚がじんわりと広がっていく。
首元から、胸の奥まで、ゆっくりと。
叶兎くんに触れられているという実感が、
安心と一緒に、甘い痺れを運んでくる。
……だめだ、これ…。
どれくらい経ったのかわからない頃、名残惜しそうに唇が離れた。
もちろん、書類なんて書けるわけもなく。
ペンを持つ手は完全に止まっていた。
「……ホント、甘。なんかまた甘くなった?」
「そうなの…?」
自分の血の味なんて正直わからない。
私にとっては、ただ、くらっとする感覚が残るだけで。