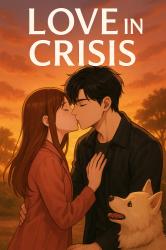七海が、あの男に肩を抱かれて
廊下の向こうへ連れ去られていく——
その後ろ姿が、ずっと頭から離れなかった。
(……あんな顔、してたんだな)
七海の横顔は、不安で揺れていた。
けれどそれ以上に……
玲央という男に触れられると、
七海の心が大きく動くのが分かってしまった。
(あれ……俺じゃない)
胸の奥が、
ゆっくりと、でも確実に沈んでいく。
***
玲央——
あの男が俺に向かって放った言葉。
七海は俺がもらいますんで。
(……あれは、冗談じゃなかった)
言った声にも、
抱く腕にも、
七海を見る目にも……
本気が滲んでいた。
(俺が知っている七海じゃない顔を……
あの男は、いくつも知っている)
その事実が胸に刺さっていた。
***
俺が七海に聞いたとき、
「七海……本当なのか?」
七海は返事ができなかった。
(あれが……答えなのか)
泣き出しそうな瞳。
震える指先。
七海は先生としての俺ではなく、
“男としての俺”に向き合うのが怖かったのだろう。
(もう……
俺が勝てる場所は少ないのかもしれない)
胸の奥がひりついた。
***
七海にとって俺は“優しい大人”だ。
七海が小さい頃から見てきた。
困ったら手を差し伸べてきた。
泣いたら慰めてきた。
(でも……
恋は、優しいだけじゃ勝てない)
ゆっくり気づいてしまった。
七海の胸をドキドキさせるのは、
俺ではない。
七海を乱す言葉を吐けるのも、
俺ではない。
“七海の目を奪っているのは、あの男だ。”
その事実が、
胸を切り裂くように痛かった。
***
(七海……
お前、昨日からずっと誰かの匂いをつけてたな)
七海が教室に入ってきた瞬間、
微かな“甘さ”を感じた。
その距離感の香りは——
俺のじゃない。
(あの男……七海に近づいていたんだ)
七海の頬の赤みも、
言えない沈黙も。
全部、
“もう俺の手が届かない場所で揺れてる”
というサインだった気がした。
***
(俺は教師だから……
本気になってはいけない)
分かっていたはずだった。
だけど、
七海が連れていかれるのを見たとき、
(……嫌だ)
喉の奥でその言葉が生まれた。
教師としてじゃない。
ひとりの男として。
(七海……
お前の全部を知っているのは、俺だと思ってた)
だけどそれは、
勘違いだったのかもしれない。
***
夕方。
職員室の窓際に立って、
七海がいなくなった校庭を見つめ続けた。
(七海……
お前の笑顔は誰に向いてるんだ?)
昨日まで当たり前のように
俺に向けられていた笑顔が、
もう自分のものではない気がして——
そのことが、
言葉にならないほど苦しかった。
(負けるのか……俺は)
初めてそう思った。
七海を、
“あの男”に奪われるかもしれないという
痛みと恐怖で——
胸が潰れそうになった。
廊下の向こうへ連れ去られていく——
その後ろ姿が、ずっと頭から離れなかった。
(……あんな顔、してたんだな)
七海の横顔は、不安で揺れていた。
けれどそれ以上に……
玲央という男に触れられると、
七海の心が大きく動くのが分かってしまった。
(あれ……俺じゃない)
胸の奥が、
ゆっくりと、でも確実に沈んでいく。
***
玲央——
あの男が俺に向かって放った言葉。
七海は俺がもらいますんで。
(……あれは、冗談じゃなかった)
言った声にも、
抱く腕にも、
七海を見る目にも……
本気が滲んでいた。
(俺が知っている七海じゃない顔を……
あの男は、いくつも知っている)
その事実が胸に刺さっていた。
***
俺が七海に聞いたとき、
「七海……本当なのか?」
七海は返事ができなかった。
(あれが……答えなのか)
泣き出しそうな瞳。
震える指先。
七海は先生としての俺ではなく、
“男としての俺”に向き合うのが怖かったのだろう。
(もう……
俺が勝てる場所は少ないのかもしれない)
胸の奥がひりついた。
***
七海にとって俺は“優しい大人”だ。
七海が小さい頃から見てきた。
困ったら手を差し伸べてきた。
泣いたら慰めてきた。
(でも……
恋は、優しいだけじゃ勝てない)
ゆっくり気づいてしまった。
七海の胸をドキドキさせるのは、
俺ではない。
七海を乱す言葉を吐けるのも、
俺ではない。
“七海の目を奪っているのは、あの男だ。”
その事実が、
胸を切り裂くように痛かった。
***
(七海……
お前、昨日からずっと誰かの匂いをつけてたな)
七海が教室に入ってきた瞬間、
微かな“甘さ”を感じた。
その距離感の香りは——
俺のじゃない。
(あの男……七海に近づいていたんだ)
七海の頬の赤みも、
言えない沈黙も。
全部、
“もう俺の手が届かない場所で揺れてる”
というサインだった気がした。
***
(俺は教師だから……
本気になってはいけない)
分かっていたはずだった。
だけど、
七海が連れていかれるのを見たとき、
(……嫌だ)
喉の奥でその言葉が生まれた。
教師としてじゃない。
ひとりの男として。
(七海……
お前の全部を知っているのは、俺だと思ってた)
だけどそれは、
勘違いだったのかもしれない。
***
夕方。
職員室の窓際に立って、
七海がいなくなった校庭を見つめ続けた。
(七海……
お前の笑顔は誰に向いてるんだ?)
昨日まで当たり前のように
俺に向けられていた笑顔が、
もう自分のものではない気がして——
そのことが、
言葉にならないほど苦しかった。
(負けるのか……俺は)
初めてそう思った。
七海を、
“あの男”に奪われるかもしれないという
痛みと恐怖で——
胸が潰れそうになった。