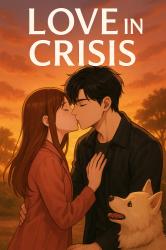昨日──
玲央くんに胸の奥まで覗き込まれるような声で
「俺だけ見ろよ」
と言われてから、
私は心がすっかりおかしくなっていた。
(だめ……思い出しただけで苦しくなる……)
でもその“苦しさ”が嫌じゃない。
そんな自分もまた苦しい。
***
「七海、おはよう」
「……あっ、お、おはようございます……!」
先生の声はいつも通り優しい。
だけど、その“優しさ”の奥に
なにか鋭いものが混ざっているのが分かった。
「……昨日の、あの人……
今日も迎えに来るのか?」
「っ……!」
(見てた……やっぱり見てたんだ……)
「七海。
気をつけてな。
……ああいうタイプは、距離が突然近づくことがあるから」
“距離が突然近づく”
その言葉が、昨日の玲央くんを思い出させて胸が跳ねた。
(気づいてる……先生も気づいてる……
私が、玲央くんで揺れてるの……)
そんな気がして、視線が合わせられなかった。
***
黒板を見るたび、
気づくと先生の視線が私に向いている。
(な、なんでこんなに見るの……?)
心配してるのか、
探ってるのか、
確かめようとしているのか……
その目はいつもの“優しい先生”じゃなくて、
もっとずっと深くて危うい。
(どうして……
どうして、今こんな……)
胸が苦しくて、
授業が終わるたびに息を吐いてしまった。
***
「七海」
「っ……!」
職員室前に呼び止められた。
「今日も……迎えが来るのか?」
「そ……それは……」
「七海。
俺に嘘をつくの、苦手だろ」
「……っ」
(やっぱり……全部、気づいてる……)
先生は一歩近づいてきて、
声を落とした。
「君が……誰のことで揺れてるのか。
昨日見たときからずっと気になってる」
「せ、先生……」
「七海は……
“あの人”に……近づいてるのか?」
その声が、
いつになく低くて痛いくらいまっすぐだった。
(そんな……言われたら……)
答えられない。
でも黙ってしまう。
その沈黙に、
先生の喉が小さく震えた。
「……七海。
俺は……君が泣いてるとき、笑ってるとき……
その全部を見てきたつもりだった」
「…………」
「でも……“昨日のお前”は……
俺が知らない顔をしてた」
「っ……!」
「……俺の知らない誰かの前で……
揺れていた顔だった」
胸がぎゅうっと締め付けられた。
(先生……そんな風に言わないで……
そんな、苦しそうな声……)
どう返せばいいのか分からなくて俯いたとき──
「あれ、七海?
まだ帰ってなかったのか」
その声が、
廊下の奥から軽く響いた。
(っ……玲央くん……!)
振り返ると、
帽子にマスク姿の玲央くんが
当然のようにそこに立っていた。
先生と私の距離を一瞬で測るように
玲央くんの目が細くなる。
「……先生。
七海には仕事があるんで、返してもらいます?」
「っ……!」
空気が、ひやりと張り詰めた。
***
玲央くんはゆっくり歩いてきて、
私の手首をそっと取った。
強くはない。
でも、絶対に離さない強さ。
「七海、行くぞ」
その言い方はいつもの軽さじゃなくて、
“決めた男の声”だった。
先生が一歩前に出る。
「君……七海をそんな風に連れ出して、
どういうつもりなんだ?」
玲央くんはピタリと足を止め、
わざわざ先生の目を見て言った。
「どうもこうも……
俺、七海を迎えに来てるだけですけど?」
「迎えに……?」
「はい。
毎日。
必要なら、朝でも夜でも」
先生の眉がきゅっと寄る。
「……七海を巻き込むのはやめたほうがいい」
「巻き込むって言い方、やめてください」
玲央くんの声のトーンが変わった。
低くて、鋭くて、どこか痛い。
「俺は七海を守るつもりでやってます。
巻き込む気なんて、最初からない」
「……君が、七海を?」
(れ、玲央くん……
そんな言い方したら……)
玲央くんは先生から目を逸らさずに続けた。
「七海は……俺の前だけ揺れてくれればいいんで」
「っ……!」
息が止まった。
先生の肩も微かに震えた。
「言っときますけど、先生。
七海、俺の胸で泣いたり震えたりしてますよ」
(れ!! れれ玲央くんー!!?!?!?)
先生の顔から一瞬、
血の気が引いたのが分かった。
「……七海」
「せ、先生……!」
「本当なのか……?」
私は何も言えなかった。
何も言えない沈黙が、
すべての答えになってしまう。
玲央くんは、
その沈黙のすべてを奪うように私の肩を抱いた。
「先生。
七海は……俺がもらいますんで」
「!!!!!?」
先生の目が揺れた。
深く、痛く。
(そんな……
そんな言い方……したら……!)
でも玲央くんの腕の強さは
拒めないほど優しくて、
苦しいほど温かかった。
「行くぞ、七海」
「……っ……」
私はそのまま連れていかれた。
先生が何も言えず立ち尽くしているのを
横目で見ながら。
(どうして……
どうしてこんな風になっちゃうの……)
胸が激しく揺れて、
涙がこぼれそうになるのを必死にこらえた。
玲央くんに胸の奥まで覗き込まれるような声で
「俺だけ見ろよ」
と言われてから、
私は心がすっかりおかしくなっていた。
(だめ……思い出しただけで苦しくなる……)
でもその“苦しさ”が嫌じゃない。
そんな自分もまた苦しい。
***
「七海、おはよう」
「……あっ、お、おはようございます……!」
先生の声はいつも通り優しい。
だけど、その“優しさ”の奥に
なにか鋭いものが混ざっているのが分かった。
「……昨日の、あの人……
今日も迎えに来るのか?」
「っ……!」
(見てた……やっぱり見てたんだ……)
「七海。
気をつけてな。
……ああいうタイプは、距離が突然近づくことがあるから」
“距離が突然近づく”
その言葉が、昨日の玲央くんを思い出させて胸が跳ねた。
(気づいてる……先生も気づいてる……
私が、玲央くんで揺れてるの……)
そんな気がして、視線が合わせられなかった。
***
黒板を見るたび、
気づくと先生の視線が私に向いている。
(な、なんでこんなに見るの……?)
心配してるのか、
探ってるのか、
確かめようとしているのか……
その目はいつもの“優しい先生”じゃなくて、
もっとずっと深くて危うい。
(どうして……
どうして、今こんな……)
胸が苦しくて、
授業が終わるたびに息を吐いてしまった。
***
「七海」
「っ……!」
職員室前に呼び止められた。
「今日も……迎えが来るのか?」
「そ……それは……」
「七海。
俺に嘘をつくの、苦手だろ」
「……っ」
(やっぱり……全部、気づいてる……)
先生は一歩近づいてきて、
声を落とした。
「君が……誰のことで揺れてるのか。
昨日見たときからずっと気になってる」
「せ、先生……」
「七海は……
“あの人”に……近づいてるのか?」
その声が、
いつになく低くて痛いくらいまっすぐだった。
(そんな……言われたら……)
答えられない。
でも黙ってしまう。
その沈黙に、
先生の喉が小さく震えた。
「……七海。
俺は……君が泣いてるとき、笑ってるとき……
その全部を見てきたつもりだった」
「…………」
「でも……“昨日のお前”は……
俺が知らない顔をしてた」
「っ……!」
「……俺の知らない誰かの前で……
揺れていた顔だった」
胸がぎゅうっと締め付けられた。
(先生……そんな風に言わないで……
そんな、苦しそうな声……)
どう返せばいいのか分からなくて俯いたとき──
「あれ、七海?
まだ帰ってなかったのか」
その声が、
廊下の奥から軽く響いた。
(っ……玲央くん……!)
振り返ると、
帽子にマスク姿の玲央くんが
当然のようにそこに立っていた。
先生と私の距離を一瞬で測るように
玲央くんの目が細くなる。
「……先生。
七海には仕事があるんで、返してもらいます?」
「っ……!」
空気が、ひやりと張り詰めた。
***
玲央くんはゆっくり歩いてきて、
私の手首をそっと取った。
強くはない。
でも、絶対に離さない強さ。
「七海、行くぞ」
その言い方はいつもの軽さじゃなくて、
“決めた男の声”だった。
先生が一歩前に出る。
「君……七海をそんな風に連れ出して、
どういうつもりなんだ?」
玲央くんはピタリと足を止め、
わざわざ先生の目を見て言った。
「どうもこうも……
俺、七海を迎えに来てるだけですけど?」
「迎えに……?」
「はい。
毎日。
必要なら、朝でも夜でも」
先生の眉がきゅっと寄る。
「……七海を巻き込むのはやめたほうがいい」
「巻き込むって言い方、やめてください」
玲央くんの声のトーンが変わった。
低くて、鋭くて、どこか痛い。
「俺は七海を守るつもりでやってます。
巻き込む気なんて、最初からない」
「……君が、七海を?」
(れ、玲央くん……
そんな言い方したら……)
玲央くんは先生から目を逸らさずに続けた。
「七海は……俺の前だけ揺れてくれればいいんで」
「っ……!」
息が止まった。
先生の肩も微かに震えた。
「言っときますけど、先生。
七海、俺の胸で泣いたり震えたりしてますよ」
(れ!! れれ玲央くんー!!?!?!?)
先生の顔から一瞬、
血の気が引いたのが分かった。
「……七海」
「せ、先生……!」
「本当なのか……?」
私は何も言えなかった。
何も言えない沈黙が、
すべての答えになってしまう。
玲央くんは、
その沈黙のすべてを奪うように私の肩を抱いた。
「先生。
七海は……俺がもらいますんで」
「!!!!!?」
先生の目が揺れた。
深く、痛く。
(そんな……
そんな言い方……したら……!)
でも玲央くんの腕の強さは
拒めないほど優しくて、
苦しいほど温かかった。
「行くぞ、七海」
「……っ……」
私はそのまま連れていかれた。
先生が何も言えず立ち尽くしているのを
横目で見ながら。
(どうして……
どうしてこんな風になっちゃうの……)
胸が激しく揺れて、
涙がこぼれそうになるのを必死にこらえた。