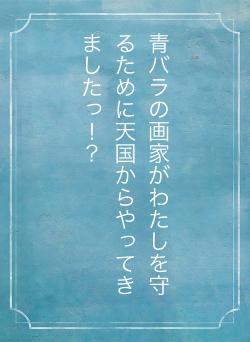カタカタ、カタッ。
カーテンが、きっちりと閉められた部屋。
そこでは、規則正しいカタカタ音が、やむことなく鳴り響いている。
土曜日の真昼間。
外では、すがすがしい青空が広がっているが、この部屋はうす暗い。
一軒家の二階。北側の部屋で、ナイトウェアすがたの黒髪の少女が、パソコンを叩いている。
猫足のデスクでぎらつく、パソコン画面。
そこには「心霊スポット情報サイト トンネルさん」という、おどろおどろしいロゴが浮かんでいた。
「ふう。五十八件目、登録完了です。夢の百件目に、いよいよ近づいてきましたね」
黒髪の少女は、ぐっと伸びをする。
彼女の名前は、隧道エポ。隧道と書いて、トンネルと読む。
心霊スポット情報サイト・トンネルさんの管理人だ。
スクロールされていくパソコンの画面に、全国の地図が映し出される。
地図には、小さな鳥居のマークがいくつも印されていた。
トンネルさんに認定された心霊スポット、という証のマークだ。
エポは再びパソコンに向かい合うと、休むまもなくメールボックスを開いた。
「しばらく開いていないうちに、かなりの量のメールがたまっていますねえ。どれどれ……ヤバい心霊スポットを送ってくれた閲覧者さんはいるでしょうか」
【トンネルさんへ 憑りつかれています。除霊してください】
「はあ。私たちは、除霊は専門外ですってば。何度かサイトでお知らせしているはずなんですがね。……次」
【トンネルさん! 心霊写真の鑑定、お願いします!】
「写真鑑定なんてわかりませんよ。この類はいつまでたっても多いですねえ。ユーチューバーさんたちの企画にでも送ったほうがいいのでは。次」
【つけていたお守りのひもが切れました。これってヤバいですか?」
「材料である布の寿命。次」
次から次へとメールをさばいていると、「エポー」と名前を呼ばれた。
マンガが散乱したソファで、男の子がだらりと寝そべっている。
年は十歳ほどで、モスグリーンのパーカーに、黒のワークパンツをはいている。
黄金色のふわふわの髪に、砂金のような瞳。
口からのぞく犬歯は、けもののようにするどい。
「このマンガの人間がさあ、ムカつくんだよー。これ書いたやつ、祟っていい?」
「いけません。今のあなたは人間のすがたをしているんですから、もっと、らしくしてください。あなたがこの家に住むとなったときに、そう約束したでしょう?」
エポはパソコンから目を離すことなく、クールに応えた。
「なんだよお。人間らしく、日々がんばってるのにー。箸だって、きれいに使えるようになっただろ。あ! そういえば、バクショクの五巻でさあ」
バクショクとは、少年誌で連載中の大人気グルメマンガ。
七尾がとてもハマっているマンガで、今さっきもよだれをたらしながら読んでいた。
「うまそうな油揚げが出てきたんだよなあ。絵なのに、なんでこんなにうまそうなんだろー。じゅるる」
「はいはい。冷蔵庫に入ってますから、それを食べておとなしくしていてください」
作業で忙しいエポは投げやりにいうが、それでも七尾は大喜びだ。
目を輝かせながら「やったあ」と一階のキッチンへと飛んでいく。
笑顔で戻ってきたその手には、白いお皿。
四角いきつね色が、べろんと乗っている。
まるで座布団のような、ふかふかの油揚げだ。
お皿をテーブルの上に置くと、手をあわせて「いただきまーす」と食べはじめた。
おぼつかない手つきだが、一生懸命に箸をあやつり、あっというまに食べ終えてしまう。
「うまかったー」
満足げにお腹をさする、七尾。
得意げに鼻を高くし、ぴかぴかのお皿をエポに見せつけた。
「どうだ、エポ。あたかも人間のような、おれさまの箸さばき!」
「そうですねえ。最初のころに比べたら、だいぶ成長したんじゃないですか」
メールをさばきながら適当に答えるエポに、七尾はムッとする。
「こらー! おれさまの話をちゃんと聞け。祟るぞ!」
「ん? このメール……」
エポの手が止まる。
パソコンをジッと見つめ、メールの内容をぶつぶつとくり返しはじめた。
【トンネルさんへ。ぼくが友達とよく行く公園で幽霊を見ました。なんとかしたいのですが、どうすればいいでしょうか。イヌヤより】
とたん、エポは流れるようにキーボードを叩きはじめた。
カタカタ、カタカタッ。
最後のエンターキーを押すときは、演奏を終えたコンダクターのように、優雅にほほえむ。
「ふふっ。感じますよ。ぞわりと肌を粟だたせてくる、このメールのヤバさ!」
「おれさまの話、聞こえてないな。これ」
心霊メールに夢中になったエポの耳には、誰の声も届かない。
「次にトンネルさんが検証する心霊スポット候補、決定です!」
「こらー、無視すんなー」
トンネルさん。
それは全国の心霊スポットを紹介している、ホラーサイトだ。
とあるユーチューバーが自身のチャンネルで紹介してから、アクセス数が急増。
今やユーチューバーだけでなく、ホラー好きやホラーイベント企画者など、多くの人が本物を求めてアクセスする、大人気サイトとなった。
その理由は。
「行くと必ず、心霊現象が起きる」という、信憑性百パーセントの心霊スポットばかりが紹介されているということ。
どんな場所だろうと管理人自らおもむき、検証。
実際に、心霊現象が起きたところのみを掲載している。
それが、ホラー好きたちの心をとらえている理由だ。
エポは中学一年生にして、その「トンネルさん」を運営する管理人なのだ。
「イヌヤさんから返信がきました。今日は土曜ですから、レスポンスが早くていいですね。今から、一時間後に待ち合わせです」
エポはイスから立ちあがると、クローゼットをひらいた。
「さあ、出かける準備を始めましょう」
ハンガーにかけられたワンピースを手に取る。
すそに十字架もようのラインがある、セーラーカラーの黒いワンピースは、エポのお気に入りの勝負服だ。
行きつけブランドの黒タイツをはき、腰まで伸ばした黒髪をていねいに櫛でとく。
そして最後、エポは胸元にブローチをつけた。
銀色の輪っかに、パールや細かい細工がほどこされたデザイン。
エポにとって、大切な宝物だ。
これを胸元で光らせると、勇気がわいてくるのだった。
少しかがんで、七尾のパーカーのフードを整えてやると、エポは「よし」、とリュックを背負った。
「七尾さんも、完璧ですよ」
すると七尾は、けもののような犬歯をのぞかせ、ニヤリと笑う。
「ふふーん。おれさまが何にでも化けられるきつねでよかったなあ。高貴なおれだからこそ、できることだぞ。ただのきつねは、電車に乗れねえもん。感謝しろ」
「ええ。七尾さんが高貴なきつねさんでよかったですよ。おかげで、安く乗ることができます。小学生は電車賃半額ですから」
「お前は本当に金にマジメな人間だなあ。もっとおれさまのことを尊敬しろ」
つまらなそうに、七尾はくちびるをとがらせた。
薄暗い玄関。
エポはストラップシューズをはき、オーバーサイズのブルゾンをはおった。
そして、しーんと静まり返った家へ、いつもの言葉を投げかける。
「行ってきます」
ぽつりとつぶやいたそれは、玄関マットのうえへと、あっけなく落ちていった。
✝
車掌の「夕暮駅ー」というテンプレートのアナウンスを聞きながら、電車を降りる。
無人駅のホームから、目的の公園がよく見えた。
エポが通う中学の、体育館くらいの広さがありそうだ。
すべり台やブランコなどの、見慣れた遊具はない。
真ん中に東屋が設置されているというだけの、普通の公園だ。
公園の向こう側に、堤防が見える。近くを川が流れているようだ。
改札を出るとすぐに、古びた看板が現れた。
その看板はもともとは白かったようだが、さび付き、ほとんどが茶色く変色してしまっている。
かろうじて、「ゆうぐれ公園 白詰町」と書かれていることだけはわかった。
「うわあー。こりゃ、文字通りさびれてるわ」
「この看板の前で、メールをくれたイヌヤさんが待ってくれているはずですが」
「……おい」
聞きなれない声に振り返ると、男の子がいた。
今のすがたの七尾と、同じくらいの年ごろだ。
「もしかして、お前らがトンネルさんの管理人?」
男の子は、信じられないとばかりに目を見開いた。
もっと、オカルトチックで手だれっぽい大人が来ると思っていたようで、かなり不満そうだ。
「あなたがイヌヤさんですか? はじめまして。今日はよろしくお願いします」
イヌヤは驚いた顔をする。
エポに、名前をいい当てられたからだ。
つまり、この二人がメールを送った相手で間違いないということになる。
イヌヤは仕方なさそうに、エポと七尾を手まねきした。
「……見てほしいものがある。こっちに来てくれ」
イヌヤに案内されてきたのは、公園入口に設置された、ピンク色のベンチだった。
座るところに、コップ一杯こぼしたくらいの、小さな水たまりができている。
昨日も今朝も、雨は降っていないはずだが。
「……これ、幽霊のしわざなんだ」
「えー。お前が水筒こぼしたとかじゃないのか」
七尾が「ぷぷ」と口もとに手を当てて、男の子を挑発する。
「嘘じゃない。拭いても拭いても、あふれ出てくるんだよ。この水!」
「まじか。ちょっと拭いてみてくんない?」
「い、いやだ」
あからさまに、おびえだすイヌヤ。
「なんでだよ。あふれてくるところ、見たいんだよ」
「この水に近づくと、腕をつかまれるんだ。幽霊のやつに」
「それ、何人くらいがつかまれましたか。あなたのお友達もやられたんですか?」
エポの質問に、イヌヤは力なく首を振った。
「つかまれたのは、今んとこおれだけ……四回くらい。強く引っぱられたりもしてる」
チッと舌打ちをするイヌヤだが、その表情は暗い。
ベンチの水に、今のところ変わったようすはないようだが……。
「エポー、どうなんだよ。この水。ポカリスエットじゃないのか」
「当たり前でしょう。ただの水でないことはたしかです。かなり、いやな気配を感じますね」
考え事をしているのか、うわのそらでブローチをなぞる、エポ。
七尾が「くそー」と、うなだれる。
「昔のおれだったら、どれだけ距離があっても、あらゆるものを見ることができたのになあ」
七尾が、悔しそうに爪を噛む。
その時、ざわっ——と空気がゆれた。
木々が、騒がしく鳴きはじめた。
「おや、風が吹いているようすはありませんが」
エポの何気ない一言に、イヌヤの動きがぴたりと硬直する。
ぴちゃん……
どこからか、水が一滴、たれた。
それだけなのに、なぜこんなにも、寒気がするのだろう。
ぴちゃ……ぴちゃ……
この音は、いやに耳に響く。
鼓膜にこびりつくようだ。
「おい、やめろってえ……っ」
イヌヤは弱弱しくうめき、両手で耳をおおった。
びちゃッ びちゃッ
びちゃッ びちゃッ
後ろから聞こえる。ベンチのほうだ。
ふり向きたくない。なのに、気になる。気になってしまう。
その不快音に誘われように、イヌヤはゆっくりとベンチをふり返った。
水が、あふれている。
水はベンチのうえで、増殖するようにあふれ、地面にしたたり落ちている。
さっきまで、コップ一杯ていどの水たまりだったはずなのに。
いつのまに、こんなにも。
イヌヤは後ずさると、逃げるようにベンチから視線を外す。
ふいに、東屋が視界のはしに映った。
誰かがいる。
もう肌寒い季節だというのに、半袖に半ズボンの男の子が東屋の真ん中に立っていた。
背丈は、自分よりも少し低い。
まるで、本当はここにいないみたいな、おぼろげな雰囲気でこちらをジッと見ている。
「ひいいい、出たあッ」
イヌヤが、悲鳴をあげた。
エポと七尾が、イヌヤの視線の先にいるものに気づく。
エポは、まちがい探しの答えを見つけたときのような笑みを浮かべた。
「ふふふっ。感じますよ。あの幽霊さんのヤバさ」
「おれにもはっきり見える。つまり、そうとう強い霊ってことだぞ、エポ」
「ええ。トンネルさん式の歓迎の儀でもてなしましょう」
エポは、リュックから取り出したスマホを手のひらで滑らせるようにして、かまえた。
トンネルさんに掲載する写真を撮影するためだ。
すると幽霊が、東屋からからだをねじらせるようにして、出てきた。
地面をなぞるようにして、すーっとエポたちに近づいてくる。
カシャカシャ、とスマホで幽霊を撮影しはじめる、エポ。
「素晴らしいです。恐ろしいほどに、心霊写真が撮れていきますよ」
スクロールされていくエポの画像フォルダーは、ほとんどが心霊写真だ。
「こ、こんな状況で何撮ってんだよ」
抗議するイヌヤ。
エポは心外だといわんばかりに、首をかしげる。
「サイトにあげる写真です。幽霊さんと記念撮影でもしてるように見えますか」
「写真なんて撮ってる場合じゃ……」
イヌヤの背中に、氷のような寒気が走った。
それは、換気対策のために少しだけ開けられた窓から吹きこむ、風の冷たさだった。
自分の後ろに、誰かが立っているのは、間違いない。
血の気が引いていく。
逃げたいと、足が勝手にどこかへと動いていく。
今、立っている……後ろに……あいつが。
ずる……っ
足元がぬるつく。
地面が、いつのまにかぬかるんでいた。
ベンチの水が、こちらまで流れてきている。
ひやり
湿り気のある何かに、足をつかまれた。
不快な感触に、心臓が飛び跳ねる。
見ると、青白い手が自分の右足首をがっちりとわしづかみにしていた。
「ひいいっ」
あいつだ。
幽霊は、どろどろの湿った地面から、上半身だけをのぞかせている。
そこから下は、地面にうまっていた。
幽霊の顔はうつむいていて、よく見えない。
湿った髪の毛が、青白い肌にはりついている。
「は……はなせよっ!」
イヌヤは恐怖で腰がぬけ、その場にひざをついた。
指で必死に地面をかいて、なんとか逃げようとする。
「おいっ! お前ら、幽霊にくわしいんだろ。早くこいつ、なんとかしろよお!」
エポと七尾へと必死に叫ぶ、イヌヤ。
そんな彼へ、エポはブローチをいじりながらたずねた。
「この幽霊さんは、イヌヤさんをこの世ではないどこかへ連れて行こうとしています。イヌヤさんに対して、かなり強い思いがあるようですが……このかたをご存知ではないですか?」
「し……知らねえっ!」
「本当に?」
エポのまっすぐな視線に、イヌヤは思わず目をそらす。
「お、おれが公園に遊びにくると、いつもこいつが現れるんだ。おれがビビるから、友達もおびえちゃっててさ。もうこんな公園来たくないっていうんだよ。だから、おれがこいつをなんとかしなきゃと思ってさあ……!」
「ふふっ。それで、トンネルさんにメールをくださったというわけですね」
イヌヤは黙って、はいているスニーカーのつま先を見つめている。
その時、幽霊につかまれている足首を強く引っぱられた。
地面がぬかるんでいるので、うまくふんばれない。
十センチほど引っぱられたあとを見て、イヌヤは泣きそうになる。
このままでは本当に、こいつにやばいところへと連れて行かれてしまう、と。
「イヌヤさんが私たちを連れて来たので、幽霊さんはいよいよ焦っているようです。必死に、イヌヤさんを連れて行こうしていますよ」
「なら早く助けろよ! 早く!」
いつまでも分析しているエポに、イヌヤはイライラをぶつける。
「エポ。祟る理由ならあるだろ。さっさとやろうぜ」
七尾がいった。
「そうですね。わかりました」
エポは黒髪を肩からはらい、手をきつねのかたちにする。
いわゆる、きつねサインというものだ。
親指、中指、薬指の輪っかから、七尾をのぞきこむ。
そして、唱えた。
砂金の瞳を持つきつねの本性を呼び起こす、不吉の言葉を。
「コックリさん、コックリさん。どうぞ祟ってください」
すると、七尾の美しい瞳がギラリと光る。
黄金色の髪やフードが、ゆらゆらとゆれはじめた。
「応じよう」
空気に波紋を作るかのような、七尾の凛とした口調。
さっきまでの子どものような態度とは、一変していた。
幼い見た目に反し、今では年齢を感じさせない不思議な空気をまとっている。
「では、その幽霊……どう祟る?」
七尾の言葉に、幽霊の手がビクン、とはねた。
ぶるぶるとふるえだし、その青白い手がイヌヤの足首から、ずるりと外れた。
ようやく解放されたイヌヤは、よろけながら起き上がる。
泥だらけなのもかまわず、四つんばいのまま逃げ出し、息も絶え絶えにエポの後ろに隠れた。
黒髪の少女はこの状況でも、涼しげな顔を絶やさない。
イヌヤはそんなエポを恐ろしげに見あげた。
「お前ら、いったい……何してるんだ。祟るって、どういうことだ」
エポは夜の闇のような透き通った瞳をイヌヤに向け、ビジネスライクにいい放つ。
「イヌヤさん。私たちが心霊スポットの情報サイトを運営する管理人ということは、ご理解いただけてますよね」
「あ、ああ……」
「あなたは、この幽霊さんをなんとかしたいといいましたね。それはどういう意味ですか?」
「意味っ?」
イヌヤの頭は恐怖と動揺と、そして戸惑いが入り混じり、めちゃくちゃだった。
「成仏してほしいとか、そういう気持ちは?」
「知らねえよっ。ただ、おれにつきまとうのを止めてほしいだけだ!」
「なるほど。よかったです。私たちはまず第一に、サイトを見てくださるかたの信頼をそこねることはしたくないですから」
エポは、蝶の羽が散るような、残酷で美しい笑みを浮かべながら、そっとつぶやいた。
——よかったです。心霊スポットの数を減らすようなことはしたくありませんから……。
その声はとても小さく、イヌヤの耳に届くことはなかった。
「コックリさん、コックリさん。祟ってもらう内容を決めました」
エポは静かに呼びかける。
「その幽霊さんに、人の言葉を思い出させてください」
「……首肯しよう」
幽霊が地面の上で、ガクガクとからだを震わせている。
ぼさぼさの髪を振り乱し、振動している幽霊から目をそらし、イヌヤは叫ぶ。
「お前ら、こいつに何したんだ!」
「イヌヤさん」
エポは、小さい子に語りかけるように、彼を呼んだ。
「イヌヤさんは、祟りとは何か知っていますか?」
パニック状態のイヌヤは、何も答えられない。
エポは、この公園のすべてに聞かせるように、一歩前へと進み出る。
「そもそも、呪いと祟りの違いをご存知でしょうか。……ご存じない? では僭越ながら、ご説明いたしましょう。呪いとは、人が人に悪意を持ってかける、おまじない的な行為のこと。では、祟りとは? それは神や仏、精霊などが起こす、心霊現象のようなもの。呪いと祟りは似ているようで、まったく違うものなのですよ」
「だから、なんだってんだよ……」
「つまり祟りとは、自分がしでかした行為に対して神から受ける、罰なのです。なので、この幽霊さんは、祟りを〝受けることができます〟。ですからね、イヌヤさん……」
エポは月に似た静けさで、イヌヤに語りかける。
恐怖ににじむ涙とあぶら汗でぐしょぐしょのイヌヤの顔は、これ以上ないほどに真っ青だった。
「会話をしましょう。この幽霊さんと」
「は?」
「なぜ、あなたに付きまとうのか聞いてみましょうよ。なんとかしたいんですよね」
これ以上ないほどに、イヌヤの顔色が悪くなる。
血の気がなくなり、紙のように真っ白だ。
エポの言葉をトリガーに、幽霊の口がガクガクと動きはじめる。
「おま、エ………」
「は……?」
「おまえ、おまえ、おまエエエエエ……」
「ひいいいいいっ!」
イヌヤが絶叫する。
幽霊は、エポの後ろに隠れているイヌヤに向かって指をさした。
「お前が、あんなことをしなければ……ぼくは……ぼくは……お前がぼくを、コロしたんだッ!」
イヌヤは、弾かれたようにその場にうずくまり、「うう……うう……」と泣きはじめた。
「あなたは誰ですか? いったい、何があったのですか」
エポはゆっくりとたずねた。
「ぼくは……連司」
幽霊はじょじょに言葉を思い出してきたのか、滑らかな口調になっていく。
「生きてるころは、こいつの……狗也のクラスメイトだった」
連司が何かをいうたび、狗也は自分のからだを抱きしめ、小さくうずくまった。
「あれは、激しい雨の日だった……」
連司のその言葉に、狗也がバッと自分の耳をふさぐ。
すると七尾が「こーら」と、狗也の手を耳から外した。
イヤミったらしく笑う七尾を、狗也は顔面蒼白でにらみつけた。
「ぼくは、狗也に呼び出されたんだ。ゲームをしよう、ってさ。ぼくは、狗也にいじめられていた。だから、断れなかった。どんなに雨が降っていても、行かなければならなかった。公園に行ったら、狗也と数人の仲間がいた。そして……そいつらに囲まれて、こういわれたんだ」
連司から、ごりごりという歯ぎしりが聞こえる。
その時のことを思い出しているのだろう。
「〝白詰川に由花のブレスレットを投げといてやったから、取りに行け〟ってさ」
白詰川とは、公園のすぐそばを流れている川のことだ。
「ぼくの妹の由花が、大事にしていたブレスレット。お祭りの縁日で、ぼくが買ってあげたものだ。とても気に入ったって、毎日つけてくれていた。でも……公園に行く前の日、由花に泣いて謝られたよ。ブレスレット、失くしちゃった。ごめんねって……」
「それでは、あなたは妹さんのブレスレットを取り戻すために、川へ入り……」
エポのそれにかぶせるように、連司は答えた。
「水のいきおいに流された。気づいたら、この公園にいた。からだを失い、由花のブレスレットも取り戻せないまま……」
狗也は、耳をふさぐのを邪魔してきた七尾を突き飛ばし、連司に怒鳴りちらした。
「仕方ないだろ、むしゃくしゃしてたんだ! おれだってさ! 大変なんだ! 親に毎日、勉強しろ、勉強しろって、怒られて。成績悪くなったら、外にしめ出されて、放置されて。反省しろって、怒鳴られて……おれだって! おれだってさあ……!」
泣き出してしまった狗也に、連司は冷たくいい放つ。
「そんなふうに謝っても、手遅れだ……ぼくはもう」
連司の手がぐにゃりと伸び、狗也の手をつかんだ。
「死んでるんだから」
狗也が絶叫する。冷たい手に引っぱられ、地面を滑っていく。
「た、助けて! 助けてよ!」
エポと七尾へと投げられた叫びとともに、狗也はあっというまにどろどろの地面にのみこまれていく。
最後には、静寂のみが残された。
地面はもう、すっかり乾いている。
✝
帰りの電車のなか、スマホを見ているエポの隣で、七尾は盛大なため息をついた。
「今回は疲れたなー」
「そうですね。でもトンネルさん的にも、七尾さん的にも満足できる幽霊さんだったんじゃないですか」
「だな! ゆうぐれ公園……おれさま復活への一ページに、くわえてやってもいいな!」
七尾の砂金の瞳が、怪しく光る。
コックリさん。
それが、七尾の本当の名前だ。
コックリさんとは、呼び出したものの願いをなんでも答えてくれる、狐の妖怪。
しかし今、七尾のちからは半分になってしまっている。
昔ほどコックリさんをやる人間が減ってしまったので、ちからがほとんどなくなってしまったのだ。
「この調子でいけば、おれさまが元のすがたに戻れる日も近いかもなあー」
エポが見ているスマホに、トンネルさんのトップページが表示された。
現在の心霊スポット登録数は、「五十八件」。
今回のゆうぐれ公園で、「五十九件」になる。
「トンネルさんに、心霊スポットを百件登録できたら、〝死んだ友人を生き返らせてもらえる〟。そういう契約でしたよね。……コックリさんの七尾さん」
「おお。百件めざして、いっしょにがんばろうな」
七尾は三日月のように目を細め、ニヤリと笑った。
NEW! ホラースポット
・白詰町 ゆうぐれ公園
地面のなかから、「だして……だして……」という男の子の声が聞こえる。
カーテンが、きっちりと閉められた部屋。
そこでは、規則正しいカタカタ音が、やむことなく鳴り響いている。
土曜日の真昼間。
外では、すがすがしい青空が広がっているが、この部屋はうす暗い。
一軒家の二階。北側の部屋で、ナイトウェアすがたの黒髪の少女が、パソコンを叩いている。
猫足のデスクでぎらつく、パソコン画面。
そこには「心霊スポット情報サイト トンネルさん」という、おどろおどろしいロゴが浮かんでいた。
「ふう。五十八件目、登録完了です。夢の百件目に、いよいよ近づいてきましたね」
黒髪の少女は、ぐっと伸びをする。
彼女の名前は、隧道エポ。隧道と書いて、トンネルと読む。
心霊スポット情報サイト・トンネルさんの管理人だ。
スクロールされていくパソコンの画面に、全国の地図が映し出される。
地図には、小さな鳥居のマークがいくつも印されていた。
トンネルさんに認定された心霊スポット、という証のマークだ。
エポは再びパソコンに向かい合うと、休むまもなくメールボックスを開いた。
「しばらく開いていないうちに、かなりの量のメールがたまっていますねえ。どれどれ……ヤバい心霊スポットを送ってくれた閲覧者さんはいるでしょうか」
【トンネルさんへ 憑りつかれています。除霊してください】
「はあ。私たちは、除霊は専門外ですってば。何度かサイトでお知らせしているはずなんですがね。……次」
【トンネルさん! 心霊写真の鑑定、お願いします!】
「写真鑑定なんてわかりませんよ。この類はいつまでたっても多いですねえ。ユーチューバーさんたちの企画にでも送ったほうがいいのでは。次」
【つけていたお守りのひもが切れました。これってヤバいですか?」
「材料である布の寿命。次」
次から次へとメールをさばいていると、「エポー」と名前を呼ばれた。
マンガが散乱したソファで、男の子がだらりと寝そべっている。
年は十歳ほどで、モスグリーンのパーカーに、黒のワークパンツをはいている。
黄金色のふわふわの髪に、砂金のような瞳。
口からのぞく犬歯は、けもののようにするどい。
「このマンガの人間がさあ、ムカつくんだよー。これ書いたやつ、祟っていい?」
「いけません。今のあなたは人間のすがたをしているんですから、もっと、らしくしてください。あなたがこの家に住むとなったときに、そう約束したでしょう?」
エポはパソコンから目を離すことなく、クールに応えた。
「なんだよお。人間らしく、日々がんばってるのにー。箸だって、きれいに使えるようになっただろ。あ! そういえば、バクショクの五巻でさあ」
バクショクとは、少年誌で連載中の大人気グルメマンガ。
七尾がとてもハマっているマンガで、今さっきもよだれをたらしながら読んでいた。
「うまそうな油揚げが出てきたんだよなあ。絵なのに、なんでこんなにうまそうなんだろー。じゅるる」
「はいはい。冷蔵庫に入ってますから、それを食べておとなしくしていてください」
作業で忙しいエポは投げやりにいうが、それでも七尾は大喜びだ。
目を輝かせながら「やったあ」と一階のキッチンへと飛んでいく。
笑顔で戻ってきたその手には、白いお皿。
四角いきつね色が、べろんと乗っている。
まるで座布団のような、ふかふかの油揚げだ。
お皿をテーブルの上に置くと、手をあわせて「いただきまーす」と食べはじめた。
おぼつかない手つきだが、一生懸命に箸をあやつり、あっというまに食べ終えてしまう。
「うまかったー」
満足げにお腹をさする、七尾。
得意げに鼻を高くし、ぴかぴかのお皿をエポに見せつけた。
「どうだ、エポ。あたかも人間のような、おれさまの箸さばき!」
「そうですねえ。最初のころに比べたら、だいぶ成長したんじゃないですか」
メールをさばきながら適当に答えるエポに、七尾はムッとする。
「こらー! おれさまの話をちゃんと聞け。祟るぞ!」
「ん? このメール……」
エポの手が止まる。
パソコンをジッと見つめ、メールの内容をぶつぶつとくり返しはじめた。
【トンネルさんへ。ぼくが友達とよく行く公園で幽霊を見ました。なんとかしたいのですが、どうすればいいでしょうか。イヌヤより】
とたん、エポは流れるようにキーボードを叩きはじめた。
カタカタ、カタカタッ。
最後のエンターキーを押すときは、演奏を終えたコンダクターのように、優雅にほほえむ。
「ふふっ。感じますよ。ぞわりと肌を粟だたせてくる、このメールのヤバさ!」
「おれさまの話、聞こえてないな。これ」
心霊メールに夢中になったエポの耳には、誰の声も届かない。
「次にトンネルさんが検証する心霊スポット候補、決定です!」
「こらー、無視すんなー」
トンネルさん。
それは全国の心霊スポットを紹介している、ホラーサイトだ。
とあるユーチューバーが自身のチャンネルで紹介してから、アクセス数が急増。
今やユーチューバーだけでなく、ホラー好きやホラーイベント企画者など、多くの人が本物を求めてアクセスする、大人気サイトとなった。
その理由は。
「行くと必ず、心霊現象が起きる」という、信憑性百パーセントの心霊スポットばかりが紹介されているということ。
どんな場所だろうと管理人自らおもむき、検証。
実際に、心霊現象が起きたところのみを掲載している。
それが、ホラー好きたちの心をとらえている理由だ。
エポは中学一年生にして、その「トンネルさん」を運営する管理人なのだ。
「イヌヤさんから返信がきました。今日は土曜ですから、レスポンスが早くていいですね。今から、一時間後に待ち合わせです」
エポはイスから立ちあがると、クローゼットをひらいた。
「さあ、出かける準備を始めましょう」
ハンガーにかけられたワンピースを手に取る。
すそに十字架もようのラインがある、セーラーカラーの黒いワンピースは、エポのお気に入りの勝負服だ。
行きつけブランドの黒タイツをはき、腰まで伸ばした黒髪をていねいに櫛でとく。
そして最後、エポは胸元にブローチをつけた。
銀色の輪っかに、パールや細かい細工がほどこされたデザイン。
エポにとって、大切な宝物だ。
これを胸元で光らせると、勇気がわいてくるのだった。
少しかがんで、七尾のパーカーのフードを整えてやると、エポは「よし」、とリュックを背負った。
「七尾さんも、完璧ですよ」
すると七尾は、けもののような犬歯をのぞかせ、ニヤリと笑う。
「ふふーん。おれさまが何にでも化けられるきつねでよかったなあ。高貴なおれだからこそ、できることだぞ。ただのきつねは、電車に乗れねえもん。感謝しろ」
「ええ。七尾さんが高貴なきつねさんでよかったですよ。おかげで、安く乗ることができます。小学生は電車賃半額ですから」
「お前は本当に金にマジメな人間だなあ。もっとおれさまのことを尊敬しろ」
つまらなそうに、七尾はくちびるをとがらせた。
薄暗い玄関。
エポはストラップシューズをはき、オーバーサイズのブルゾンをはおった。
そして、しーんと静まり返った家へ、いつもの言葉を投げかける。
「行ってきます」
ぽつりとつぶやいたそれは、玄関マットのうえへと、あっけなく落ちていった。
✝
車掌の「夕暮駅ー」というテンプレートのアナウンスを聞きながら、電車を降りる。
無人駅のホームから、目的の公園がよく見えた。
エポが通う中学の、体育館くらいの広さがありそうだ。
すべり台やブランコなどの、見慣れた遊具はない。
真ん中に東屋が設置されているというだけの、普通の公園だ。
公園の向こう側に、堤防が見える。近くを川が流れているようだ。
改札を出るとすぐに、古びた看板が現れた。
その看板はもともとは白かったようだが、さび付き、ほとんどが茶色く変色してしまっている。
かろうじて、「ゆうぐれ公園 白詰町」と書かれていることだけはわかった。
「うわあー。こりゃ、文字通りさびれてるわ」
「この看板の前で、メールをくれたイヌヤさんが待ってくれているはずですが」
「……おい」
聞きなれない声に振り返ると、男の子がいた。
今のすがたの七尾と、同じくらいの年ごろだ。
「もしかして、お前らがトンネルさんの管理人?」
男の子は、信じられないとばかりに目を見開いた。
もっと、オカルトチックで手だれっぽい大人が来ると思っていたようで、かなり不満そうだ。
「あなたがイヌヤさんですか? はじめまして。今日はよろしくお願いします」
イヌヤは驚いた顔をする。
エポに、名前をいい当てられたからだ。
つまり、この二人がメールを送った相手で間違いないということになる。
イヌヤは仕方なさそうに、エポと七尾を手まねきした。
「……見てほしいものがある。こっちに来てくれ」
イヌヤに案内されてきたのは、公園入口に設置された、ピンク色のベンチだった。
座るところに、コップ一杯こぼしたくらいの、小さな水たまりができている。
昨日も今朝も、雨は降っていないはずだが。
「……これ、幽霊のしわざなんだ」
「えー。お前が水筒こぼしたとかじゃないのか」
七尾が「ぷぷ」と口もとに手を当てて、男の子を挑発する。
「嘘じゃない。拭いても拭いても、あふれ出てくるんだよ。この水!」
「まじか。ちょっと拭いてみてくんない?」
「い、いやだ」
あからさまに、おびえだすイヌヤ。
「なんでだよ。あふれてくるところ、見たいんだよ」
「この水に近づくと、腕をつかまれるんだ。幽霊のやつに」
「それ、何人くらいがつかまれましたか。あなたのお友達もやられたんですか?」
エポの質問に、イヌヤは力なく首を振った。
「つかまれたのは、今んとこおれだけ……四回くらい。強く引っぱられたりもしてる」
チッと舌打ちをするイヌヤだが、その表情は暗い。
ベンチの水に、今のところ変わったようすはないようだが……。
「エポー、どうなんだよ。この水。ポカリスエットじゃないのか」
「当たり前でしょう。ただの水でないことはたしかです。かなり、いやな気配を感じますね」
考え事をしているのか、うわのそらでブローチをなぞる、エポ。
七尾が「くそー」と、うなだれる。
「昔のおれだったら、どれだけ距離があっても、あらゆるものを見ることができたのになあ」
七尾が、悔しそうに爪を噛む。
その時、ざわっ——と空気がゆれた。
木々が、騒がしく鳴きはじめた。
「おや、風が吹いているようすはありませんが」
エポの何気ない一言に、イヌヤの動きがぴたりと硬直する。
ぴちゃん……
どこからか、水が一滴、たれた。
それだけなのに、なぜこんなにも、寒気がするのだろう。
ぴちゃ……ぴちゃ……
この音は、いやに耳に響く。
鼓膜にこびりつくようだ。
「おい、やめろってえ……っ」
イヌヤは弱弱しくうめき、両手で耳をおおった。
びちゃッ びちゃッ
びちゃッ びちゃッ
後ろから聞こえる。ベンチのほうだ。
ふり向きたくない。なのに、気になる。気になってしまう。
その不快音に誘われように、イヌヤはゆっくりとベンチをふり返った。
水が、あふれている。
水はベンチのうえで、増殖するようにあふれ、地面にしたたり落ちている。
さっきまで、コップ一杯ていどの水たまりだったはずなのに。
いつのまに、こんなにも。
イヌヤは後ずさると、逃げるようにベンチから視線を外す。
ふいに、東屋が視界のはしに映った。
誰かがいる。
もう肌寒い季節だというのに、半袖に半ズボンの男の子が東屋の真ん中に立っていた。
背丈は、自分よりも少し低い。
まるで、本当はここにいないみたいな、おぼろげな雰囲気でこちらをジッと見ている。
「ひいいい、出たあッ」
イヌヤが、悲鳴をあげた。
エポと七尾が、イヌヤの視線の先にいるものに気づく。
エポは、まちがい探しの答えを見つけたときのような笑みを浮かべた。
「ふふふっ。感じますよ。あの幽霊さんのヤバさ」
「おれにもはっきり見える。つまり、そうとう強い霊ってことだぞ、エポ」
「ええ。トンネルさん式の歓迎の儀でもてなしましょう」
エポは、リュックから取り出したスマホを手のひらで滑らせるようにして、かまえた。
トンネルさんに掲載する写真を撮影するためだ。
すると幽霊が、東屋からからだをねじらせるようにして、出てきた。
地面をなぞるようにして、すーっとエポたちに近づいてくる。
カシャカシャ、とスマホで幽霊を撮影しはじめる、エポ。
「素晴らしいです。恐ろしいほどに、心霊写真が撮れていきますよ」
スクロールされていくエポの画像フォルダーは、ほとんどが心霊写真だ。
「こ、こんな状況で何撮ってんだよ」
抗議するイヌヤ。
エポは心外だといわんばかりに、首をかしげる。
「サイトにあげる写真です。幽霊さんと記念撮影でもしてるように見えますか」
「写真なんて撮ってる場合じゃ……」
イヌヤの背中に、氷のような寒気が走った。
それは、換気対策のために少しだけ開けられた窓から吹きこむ、風の冷たさだった。
自分の後ろに、誰かが立っているのは、間違いない。
血の気が引いていく。
逃げたいと、足が勝手にどこかへと動いていく。
今、立っている……後ろに……あいつが。
ずる……っ
足元がぬるつく。
地面が、いつのまにかぬかるんでいた。
ベンチの水が、こちらまで流れてきている。
ひやり
湿り気のある何かに、足をつかまれた。
不快な感触に、心臓が飛び跳ねる。
見ると、青白い手が自分の右足首をがっちりとわしづかみにしていた。
「ひいいっ」
あいつだ。
幽霊は、どろどろの湿った地面から、上半身だけをのぞかせている。
そこから下は、地面にうまっていた。
幽霊の顔はうつむいていて、よく見えない。
湿った髪の毛が、青白い肌にはりついている。
「は……はなせよっ!」
イヌヤは恐怖で腰がぬけ、その場にひざをついた。
指で必死に地面をかいて、なんとか逃げようとする。
「おいっ! お前ら、幽霊にくわしいんだろ。早くこいつ、なんとかしろよお!」
エポと七尾へと必死に叫ぶ、イヌヤ。
そんな彼へ、エポはブローチをいじりながらたずねた。
「この幽霊さんは、イヌヤさんをこの世ではないどこかへ連れて行こうとしています。イヌヤさんに対して、かなり強い思いがあるようですが……このかたをご存知ではないですか?」
「し……知らねえっ!」
「本当に?」
エポのまっすぐな視線に、イヌヤは思わず目をそらす。
「お、おれが公園に遊びにくると、いつもこいつが現れるんだ。おれがビビるから、友達もおびえちゃっててさ。もうこんな公園来たくないっていうんだよ。だから、おれがこいつをなんとかしなきゃと思ってさあ……!」
「ふふっ。それで、トンネルさんにメールをくださったというわけですね」
イヌヤは黙って、はいているスニーカーのつま先を見つめている。
その時、幽霊につかまれている足首を強く引っぱられた。
地面がぬかるんでいるので、うまくふんばれない。
十センチほど引っぱられたあとを見て、イヌヤは泣きそうになる。
このままでは本当に、こいつにやばいところへと連れて行かれてしまう、と。
「イヌヤさんが私たちを連れて来たので、幽霊さんはいよいよ焦っているようです。必死に、イヌヤさんを連れて行こうしていますよ」
「なら早く助けろよ! 早く!」
いつまでも分析しているエポに、イヌヤはイライラをぶつける。
「エポ。祟る理由ならあるだろ。さっさとやろうぜ」
七尾がいった。
「そうですね。わかりました」
エポは黒髪を肩からはらい、手をきつねのかたちにする。
いわゆる、きつねサインというものだ。
親指、中指、薬指の輪っかから、七尾をのぞきこむ。
そして、唱えた。
砂金の瞳を持つきつねの本性を呼び起こす、不吉の言葉を。
「コックリさん、コックリさん。どうぞ祟ってください」
すると、七尾の美しい瞳がギラリと光る。
黄金色の髪やフードが、ゆらゆらとゆれはじめた。
「応じよう」
空気に波紋を作るかのような、七尾の凛とした口調。
さっきまでの子どものような態度とは、一変していた。
幼い見た目に反し、今では年齢を感じさせない不思議な空気をまとっている。
「では、その幽霊……どう祟る?」
七尾の言葉に、幽霊の手がビクン、とはねた。
ぶるぶるとふるえだし、その青白い手がイヌヤの足首から、ずるりと外れた。
ようやく解放されたイヌヤは、よろけながら起き上がる。
泥だらけなのもかまわず、四つんばいのまま逃げ出し、息も絶え絶えにエポの後ろに隠れた。
黒髪の少女はこの状況でも、涼しげな顔を絶やさない。
イヌヤはそんなエポを恐ろしげに見あげた。
「お前ら、いったい……何してるんだ。祟るって、どういうことだ」
エポは夜の闇のような透き通った瞳をイヌヤに向け、ビジネスライクにいい放つ。
「イヌヤさん。私たちが心霊スポットの情報サイトを運営する管理人ということは、ご理解いただけてますよね」
「あ、ああ……」
「あなたは、この幽霊さんをなんとかしたいといいましたね。それはどういう意味ですか?」
「意味っ?」
イヌヤの頭は恐怖と動揺と、そして戸惑いが入り混じり、めちゃくちゃだった。
「成仏してほしいとか、そういう気持ちは?」
「知らねえよっ。ただ、おれにつきまとうのを止めてほしいだけだ!」
「なるほど。よかったです。私たちはまず第一に、サイトを見てくださるかたの信頼をそこねることはしたくないですから」
エポは、蝶の羽が散るような、残酷で美しい笑みを浮かべながら、そっとつぶやいた。
——よかったです。心霊スポットの数を減らすようなことはしたくありませんから……。
その声はとても小さく、イヌヤの耳に届くことはなかった。
「コックリさん、コックリさん。祟ってもらう内容を決めました」
エポは静かに呼びかける。
「その幽霊さんに、人の言葉を思い出させてください」
「……首肯しよう」
幽霊が地面の上で、ガクガクとからだを震わせている。
ぼさぼさの髪を振り乱し、振動している幽霊から目をそらし、イヌヤは叫ぶ。
「お前ら、こいつに何したんだ!」
「イヌヤさん」
エポは、小さい子に語りかけるように、彼を呼んだ。
「イヌヤさんは、祟りとは何か知っていますか?」
パニック状態のイヌヤは、何も答えられない。
エポは、この公園のすべてに聞かせるように、一歩前へと進み出る。
「そもそも、呪いと祟りの違いをご存知でしょうか。……ご存じない? では僭越ながら、ご説明いたしましょう。呪いとは、人が人に悪意を持ってかける、おまじない的な行為のこと。では、祟りとは? それは神や仏、精霊などが起こす、心霊現象のようなもの。呪いと祟りは似ているようで、まったく違うものなのですよ」
「だから、なんだってんだよ……」
「つまり祟りとは、自分がしでかした行為に対して神から受ける、罰なのです。なので、この幽霊さんは、祟りを〝受けることができます〟。ですからね、イヌヤさん……」
エポは月に似た静けさで、イヌヤに語りかける。
恐怖ににじむ涙とあぶら汗でぐしょぐしょのイヌヤの顔は、これ以上ないほどに真っ青だった。
「会話をしましょう。この幽霊さんと」
「は?」
「なぜ、あなたに付きまとうのか聞いてみましょうよ。なんとかしたいんですよね」
これ以上ないほどに、イヌヤの顔色が悪くなる。
血の気がなくなり、紙のように真っ白だ。
エポの言葉をトリガーに、幽霊の口がガクガクと動きはじめる。
「おま、エ………」
「は……?」
「おまえ、おまえ、おまエエエエエ……」
「ひいいいいいっ!」
イヌヤが絶叫する。
幽霊は、エポの後ろに隠れているイヌヤに向かって指をさした。
「お前が、あんなことをしなければ……ぼくは……ぼくは……お前がぼくを、コロしたんだッ!」
イヌヤは、弾かれたようにその場にうずくまり、「うう……うう……」と泣きはじめた。
「あなたは誰ですか? いったい、何があったのですか」
エポはゆっくりとたずねた。
「ぼくは……連司」
幽霊はじょじょに言葉を思い出してきたのか、滑らかな口調になっていく。
「生きてるころは、こいつの……狗也のクラスメイトだった」
連司が何かをいうたび、狗也は自分のからだを抱きしめ、小さくうずくまった。
「あれは、激しい雨の日だった……」
連司のその言葉に、狗也がバッと自分の耳をふさぐ。
すると七尾が「こーら」と、狗也の手を耳から外した。
イヤミったらしく笑う七尾を、狗也は顔面蒼白でにらみつけた。
「ぼくは、狗也に呼び出されたんだ。ゲームをしよう、ってさ。ぼくは、狗也にいじめられていた。だから、断れなかった。どんなに雨が降っていても、行かなければならなかった。公園に行ったら、狗也と数人の仲間がいた。そして……そいつらに囲まれて、こういわれたんだ」
連司から、ごりごりという歯ぎしりが聞こえる。
その時のことを思い出しているのだろう。
「〝白詰川に由花のブレスレットを投げといてやったから、取りに行け〟ってさ」
白詰川とは、公園のすぐそばを流れている川のことだ。
「ぼくの妹の由花が、大事にしていたブレスレット。お祭りの縁日で、ぼくが買ってあげたものだ。とても気に入ったって、毎日つけてくれていた。でも……公園に行く前の日、由花に泣いて謝られたよ。ブレスレット、失くしちゃった。ごめんねって……」
「それでは、あなたは妹さんのブレスレットを取り戻すために、川へ入り……」
エポのそれにかぶせるように、連司は答えた。
「水のいきおいに流された。気づいたら、この公園にいた。からだを失い、由花のブレスレットも取り戻せないまま……」
狗也は、耳をふさぐのを邪魔してきた七尾を突き飛ばし、連司に怒鳴りちらした。
「仕方ないだろ、むしゃくしゃしてたんだ! おれだってさ! 大変なんだ! 親に毎日、勉強しろ、勉強しろって、怒られて。成績悪くなったら、外にしめ出されて、放置されて。反省しろって、怒鳴られて……おれだって! おれだってさあ……!」
泣き出してしまった狗也に、連司は冷たくいい放つ。
「そんなふうに謝っても、手遅れだ……ぼくはもう」
連司の手がぐにゃりと伸び、狗也の手をつかんだ。
「死んでるんだから」
狗也が絶叫する。冷たい手に引っぱられ、地面を滑っていく。
「た、助けて! 助けてよ!」
エポと七尾へと投げられた叫びとともに、狗也はあっというまにどろどろの地面にのみこまれていく。
最後には、静寂のみが残された。
地面はもう、すっかり乾いている。
✝
帰りの電車のなか、スマホを見ているエポの隣で、七尾は盛大なため息をついた。
「今回は疲れたなー」
「そうですね。でもトンネルさん的にも、七尾さん的にも満足できる幽霊さんだったんじゃないですか」
「だな! ゆうぐれ公園……おれさま復活への一ページに、くわえてやってもいいな!」
七尾の砂金の瞳が、怪しく光る。
コックリさん。
それが、七尾の本当の名前だ。
コックリさんとは、呼び出したものの願いをなんでも答えてくれる、狐の妖怪。
しかし今、七尾のちからは半分になってしまっている。
昔ほどコックリさんをやる人間が減ってしまったので、ちからがほとんどなくなってしまったのだ。
「この調子でいけば、おれさまが元のすがたに戻れる日も近いかもなあー」
エポが見ているスマホに、トンネルさんのトップページが表示された。
現在の心霊スポット登録数は、「五十八件」。
今回のゆうぐれ公園で、「五十九件」になる。
「トンネルさんに、心霊スポットを百件登録できたら、〝死んだ友人を生き返らせてもらえる〟。そういう契約でしたよね。……コックリさんの七尾さん」
「おお。百件めざして、いっしょにがんばろうな」
七尾は三日月のように目を細め、ニヤリと笑った。
NEW! ホラースポット
・白詰町 ゆうぐれ公園
地面のなかから、「だして……だして……」という男の子の声が聞こえる。