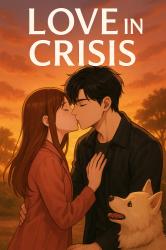御堂家での生活にも、少しずつ慣れてきたころ。
紗菜はようやく“婚約者としての立ち振る舞いレッスン”にも慣れ始めていた。
息つく暇もない日々の中で、唯一心の支えになっているのが、怜司の言葉だった。
――離れるな。俺のそばにいろ。
あの夜、怜司に抱きしめられた温もりは、忘れるどころか、思い出すたびに胸が甘く疼く。
少しだけ、自分にも自信がついてきた……ちょうどそのとき。
“彼女”は現れた。
高級車が玄関前に音もなく停まり、黒いヒールで降り立った女性は、ただの一歩で空気を変えた。
黒髪をすっきりまとめ、ハイブランドのスーツを美しく着こなしている。
澄んだ表情に、完璧な美しさ。
「……こんにちは。桜井紗菜さん、で間違いない?」
落ち着いた声。
初対面なのに“格の差”を感じる洗練された雰囲気。
「は、はい……あなたは……?」
女性は小さく微笑む。
「私は氷川舞。怜司さんの、元婚約候補よ」
(元……婚約候補……?)
その言葉の重さに、紗菜は自然と背筋を伸ばしていた。
氷川舞。
聞いたことがある。
政財界でも名の知れた氷川本家の令嬢。
怜司の“正式婚約候補リスト”の筆頭だったはず。
そんな人が、いきなり紗菜に会いに来た理由は――想像しなくてもわかる。
「少し……お話しできる?」
舞は優しい声で言ったが、その瞳は紗菜を試すようだった。
二人はサロンに移動した。
広い部屋の静けさが、余計に緊張を煽る。
舞はまっすぐ紗菜を見つめ、口を開いた。
「本題から言うわね。あなた……怜司さんと“契約婚”してるんでしょ?」
紗菜はぎゅっと指を組んだまま頷くしかない。
「……はい。半年だけの、形式的なもので……」
「形式的?」
舞が微笑む。その笑みは優雅で、でもどこか刺すようだった。
「それでも、“御堂怜司の花嫁”の席に座るのよ。その意味、あなた、理解してる?」
胸がぎゅっと痛む。
「御堂家は甘くないわ。あなたが怜司さんの隣に立つことで、どれだけの重圧と……どれだけの批判を受けるか。
あなたの覚悟ひとつで、怜司さんが傷つくことだってあるの」
(……そんなこと言われたら……何も言えない……)
舞はさらに続ける。
「私、怜司さんのことが嫌いなわけじゃないの。
ただ……彼の隣に立つ女性がどれほどのものを背負うか、よく知っているだけ」
その声は冷静で、感情的ではなく、むしろ本気で言っているようだった。
「あなたみたいな普通の子が悪いとは言わない。でも――」
そこで舞の指がすっと紗菜の胸元へ向く。
「“身の丈に合わない”幸せを追えば、壊れるのはあなたよ」
刺さった。
言葉なのに、本当に胸を刺されたみたいに痛い。
(私は……身の丈に合わない……?)
舞は立ち上がり、紗菜に丁寧に会釈した。
「怜司さんを大切にしてあげて。
あなたが怜司さんを傷つけるような結果にならないことを願っているわ」
去っていく後ろ姿まで完璧だった。
残された紗菜は、まるで嵐に吹かれたあとみたいに座り込んだまま動けない。
(……私じゃ、ダメなのかな)
胸がしめつけられ、息が苦しくなる。
舞の言葉が現実を突きつけてくる。
“あなたみたいな普通の子が悪いとは言わない。でも――身の丈に合わない幸せを追えば、壊れるのはあなた”
(舞さんのほうが……怜司さんにふさわしいんじゃ……)
そのとき、背後から影が落ちた。
「……紗菜?」
怜司だった。
紗菜は慌てて立ち上がるが、目元が熱くなっているのを隠しきれなかった。
「どうした」
怜司は一歩近づく。
気づかれたくないのに、涙が一粒落ちた。
「いや……なんでも……」
「嘘をつくな」
怜司はそっと紗菜の頬に触れる。
優しい指先が涙の跡をなぞる。
「舞に……何を言われた」
低い声。
抑え込まれた怒りが滲んでいる。
紗菜はかすかに首を振った。
「怜司さん……あのね……私……あなたの隣に立つ資格なんてないんじゃないかなって……」
怜司の表情が変わった。
紗菜の手首をそっと掴み、ぐっと自分の胸元へ引き寄せる。
「誰がそんなこと言った」
「っ……」
「お前は俺が選んだ女だ。それ以上の“資格”がどこにある」
耳が熱くなる。
息が苦しくなるほど近い距離。
怜司の指が紗菜の顎をそっと持ち上げる。
逃げられない。
「……嫉妬したんだろう」
「え……?」
「舞は美人だし、完璧だし、誰から見ても俺の“相手としてふさわしい”ように見えるからな」
その言葉が胸に刺さる。
でも怜司は続けた。
「でも……俺は、お前がいい」
紗菜の心臓が跳ねた。
「完璧じゃなくていい。
普通の子でいい。
泣いたり、悩んだり、嫉妬したり――
そういう“お前らしさ”が、俺を救うんだ」
紗菜の目がじわっと潤む。
怜司はその涙を親指で拭い、ふっと小さな笑みを浮かべた。
「……そんな顔で泣くな。
俺まで……おかしくなる」
そのまま怜司の手が紗菜の後頭部に添えられる。
同時に胸へ引き寄せられ、ぎゅっと強く抱きしめられた。
「紗菜。俺はお前にしか心を開けない。
だから……自分を下に見るな」
温かい。
胸の奥が甘く痛くて、涙がこぼれそうになる。
(私……この人のこと……本当に……)
怜司の腕の中で、紗菜はそっと目を閉じた。
――この胸に触れるたび、
“普通のOL”だった自分が、
“御堂怜司の婚約者”へと変わっていく。
紗菜はようやく“婚約者としての立ち振る舞いレッスン”にも慣れ始めていた。
息つく暇もない日々の中で、唯一心の支えになっているのが、怜司の言葉だった。
――離れるな。俺のそばにいろ。
あの夜、怜司に抱きしめられた温もりは、忘れるどころか、思い出すたびに胸が甘く疼く。
少しだけ、自分にも自信がついてきた……ちょうどそのとき。
“彼女”は現れた。
高級車が玄関前に音もなく停まり、黒いヒールで降り立った女性は、ただの一歩で空気を変えた。
黒髪をすっきりまとめ、ハイブランドのスーツを美しく着こなしている。
澄んだ表情に、完璧な美しさ。
「……こんにちは。桜井紗菜さん、で間違いない?」
落ち着いた声。
初対面なのに“格の差”を感じる洗練された雰囲気。
「は、はい……あなたは……?」
女性は小さく微笑む。
「私は氷川舞。怜司さんの、元婚約候補よ」
(元……婚約候補……?)
その言葉の重さに、紗菜は自然と背筋を伸ばしていた。
氷川舞。
聞いたことがある。
政財界でも名の知れた氷川本家の令嬢。
怜司の“正式婚約候補リスト”の筆頭だったはず。
そんな人が、いきなり紗菜に会いに来た理由は――想像しなくてもわかる。
「少し……お話しできる?」
舞は優しい声で言ったが、その瞳は紗菜を試すようだった。
二人はサロンに移動した。
広い部屋の静けさが、余計に緊張を煽る。
舞はまっすぐ紗菜を見つめ、口を開いた。
「本題から言うわね。あなた……怜司さんと“契約婚”してるんでしょ?」
紗菜はぎゅっと指を組んだまま頷くしかない。
「……はい。半年だけの、形式的なもので……」
「形式的?」
舞が微笑む。その笑みは優雅で、でもどこか刺すようだった。
「それでも、“御堂怜司の花嫁”の席に座るのよ。その意味、あなた、理解してる?」
胸がぎゅっと痛む。
「御堂家は甘くないわ。あなたが怜司さんの隣に立つことで、どれだけの重圧と……どれだけの批判を受けるか。
あなたの覚悟ひとつで、怜司さんが傷つくことだってあるの」
(……そんなこと言われたら……何も言えない……)
舞はさらに続ける。
「私、怜司さんのことが嫌いなわけじゃないの。
ただ……彼の隣に立つ女性がどれほどのものを背負うか、よく知っているだけ」
その声は冷静で、感情的ではなく、むしろ本気で言っているようだった。
「あなたみたいな普通の子が悪いとは言わない。でも――」
そこで舞の指がすっと紗菜の胸元へ向く。
「“身の丈に合わない”幸せを追えば、壊れるのはあなたよ」
刺さった。
言葉なのに、本当に胸を刺されたみたいに痛い。
(私は……身の丈に合わない……?)
舞は立ち上がり、紗菜に丁寧に会釈した。
「怜司さんを大切にしてあげて。
あなたが怜司さんを傷つけるような結果にならないことを願っているわ」
去っていく後ろ姿まで完璧だった。
残された紗菜は、まるで嵐に吹かれたあとみたいに座り込んだまま動けない。
(……私じゃ、ダメなのかな)
胸がしめつけられ、息が苦しくなる。
舞の言葉が現実を突きつけてくる。
“あなたみたいな普通の子が悪いとは言わない。でも――身の丈に合わない幸せを追えば、壊れるのはあなた”
(舞さんのほうが……怜司さんにふさわしいんじゃ……)
そのとき、背後から影が落ちた。
「……紗菜?」
怜司だった。
紗菜は慌てて立ち上がるが、目元が熱くなっているのを隠しきれなかった。
「どうした」
怜司は一歩近づく。
気づかれたくないのに、涙が一粒落ちた。
「いや……なんでも……」
「嘘をつくな」
怜司はそっと紗菜の頬に触れる。
優しい指先が涙の跡をなぞる。
「舞に……何を言われた」
低い声。
抑え込まれた怒りが滲んでいる。
紗菜はかすかに首を振った。
「怜司さん……あのね……私……あなたの隣に立つ資格なんてないんじゃないかなって……」
怜司の表情が変わった。
紗菜の手首をそっと掴み、ぐっと自分の胸元へ引き寄せる。
「誰がそんなこと言った」
「っ……」
「お前は俺が選んだ女だ。それ以上の“資格”がどこにある」
耳が熱くなる。
息が苦しくなるほど近い距離。
怜司の指が紗菜の顎をそっと持ち上げる。
逃げられない。
「……嫉妬したんだろう」
「え……?」
「舞は美人だし、完璧だし、誰から見ても俺の“相手としてふさわしい”ように見えるからな」
その言葉が胸に刺さる。
でも怜司は続けた。
「でも……俺は、お前がいい」
紗菜の心臓が跳ねた。
「完璧じゃなくていい。
普通の子でいい。
泣いたり、悩んだり、嫉妬したり――
そういう“お前らしさ”が、俺を救うんだ」
紗菜の目がじわっと潤む。
怜司はその涙を親指で拭い、ふっと小さな笑みを浮かべた。
「……そんな顔で泣くな。
俺まで……おかしくなる」
そのまま怜司の手が紗菜の後頭部に添えられる。
同時に胸へ引き寄せられ、ぎゅっと強く抱きしめられた。
「紗菜。俺はお前にしか心を開けない。
だから……自分を下に見るな」
温かい。
胸の奥が甘く痛くて、涙がこぼれそうになる。
(私……この人のこと……本当に……)
怜司の腕の中で、紗菜はそっと目を閉じた。
――この胸に触れるたび、
“普通のOL”だった自分が、
“御堂怜司の婚約者”へと変わっていく。