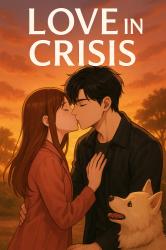結婚式の翌日。
紗菜は、まだ現実を飲み込めないまま、電車の窓に映る自分の顔をみつめていた。
「……なんで、私が“契約花嫁”なんてことに……」
天井の蛍光灯に照らされた自分の表情は、驚きと不安の混ざった“昨日のまま”。
(普通のOLで、地味で、特技も何もないのに……)
(相手は、御堂怜司。財閥の御曹司。手の届かない世界の人。)
昨日の彼の言葉が、まだ耳の奥で響いていた。
『君なら、悪くないと思った』
(……あれって、どういう意味だったの?)
そんな疑問を抱えたまま、紗菜は指定された車両に乗り換える。
そこには、運転手付きの黒い車が待っていた。
「桜井紗菜様ですね。御堂家よりお迎えに参りました」
丁寧な言葉遣いに、紗菜は慌てて頭を下げた。
――どう考えても、自分はそんな扱いを受けるような人間じゃない。
しかし車は、その“自分の価値観”などお構いなしに、
高級住宅街を抜け、さらに奥へ奥へと進んでいく。
そして目の前に現れたのは――
ガラスの城。
いや、そうとしか言いようがなかった。
天井まで届くガラス張りの壁。
真っ白な外壁と、彫刻のように整えられた庭木。
重厚な鉄のゲートがゆっくりと開く音がするたび、紗菜の心臓は跳ねた。
(ここが……怜司さんの家……?)
門をくぐった瞬間、まるで空気まで変わったように感じた。
普通と豪奢の境界線を、確かに越えてしまったのだ。
玄関ホールに足を踏み入れたそのとき。
カツ、カツ――と靴音が響く。
ゆっくりと階段から降りてきたのは、怜司だった。
黒のシャツにダークグレーのスラックス。
“仕事帰りの御曹司”という存在だけで、空気が締まる。
「……来たのか」
それだけなのに、胸の奥がじん、と熱くなる。
「え、えっと……あの、昨日のことなんですけど……
契約結婚って、その……本当に私なんかで……?」
怜司は足を止め、真っすぐに紗菜を見る。
目が合った瞬間、呼吸が浅くなった。
彼の瞳には、冷たさよりも――意志があった。
「君じゃなきゃ困る」
「っ……!」
言葉が喉にひっかかった。
「祖母――会長は、身分だの家柄だのと煩い。
“結婚候補”なんて勝手にリストまで作り始めた」
怜司は少しだけ表情を曇らせる。
「……俺は、ああいう政治的な婚姻が嫌なんだ」
そして、さっきより少し柔らかい声で続けた。
「昨日、お前を見たとき……直感した」
「ちょ、ちょっと待ってください!
私、特別なこと何もしてませんよ……!?
むしろ、私は――」
怜司は近づき、彼女の言葉をそっと遮った。
「静かに。落ち着け」
その声音が優しすぎて、紗菜は一瞬言葉を失った。
怜司はさらに歩み寄る。
距離が……近い。
「俺が選んだ理由は君にはわからないだろうが……」
指先が紗菜の髪に触れ、ふわりと頬に落ちる。
「……“普通の幸せ”を知っている女性を、俺は欲しかった」
心臓が跳ねた。
頬が熱くなり、息が詰まる。
「お前には、俺の世界にない“大切なもの”がある。
俺は……それを欲している」
まっすぐな声。
嘘やごまかしのない、本音の響き。
(そんなふうに言われたら……断れない……)
怜司は小さな書類の束を手にして、紗菜の前に差し出した。
「これが契約書だ。
半年間、俺の婚約者として生活してもらう」
紗菜は震える手で受け取り、ページをめくる。
そこには細かい条項がずらりと並んでいて――
その中のひとつに、目が留まった。
【御堂怜司は、桜井紗菜の生活を全面的に保証する】
【精神的・身体的に無理な要求は絶対に行わない】
【紗菜を守ること】
(え……?)
思わず顔を上げると、怜司は少しだけ照れたように視線をそらした。
「……会長が口を出してこないように俺が書いた。
“俺の花嫁に負担をかけさせるな”ってな」
ドクン――
心臓が大きな音を立てた。
(……花嫁……って……)
怜司は、ほんの一呼吸のあと、紗菜に向き直った。
「紗菜。
契約でも形だけでも構わない。
――俺の隣に立ってほしい」
紗菜の胸はぎゅう、と締めつけられた。
この豪華な世界にも、自分を必要としてくれる人がいる。
そんなふうに思えた瞬間だった。
そして――
ゆっくりとペンを取り、契約書に名前を書いた。
「……桜井紗菜、署名しました」
怜司の瞳が、かすかに揺れる。
その揺れが、なぜか優しさに見えた。
「……これで今日から、お前は俺の婚約者だ」
怜司はそっと紗菜の手を取り、温かく握る。
その仕草は、契約のためのスキンシップではなく――
紗菜を包み、導く“本物の手”だった。
(……こんなの、もう……)
――恋してしまうに決まってる。
そう思った瞬間、怜司の親指が紗菜の手の甲を、
優しくなぞった。
そして、低く甘い声で囁く。
「覚悟しておけよ。
契約でも……俺は、お前を甘やかすつもりだ」
紗菜の心臓が、大きく跳ねた。
こうして紗菜は、
“ガラスの城で始まる、身分差×溺愛婚”へと足を踏み出した。
紗菜は、まだ現実を飲み込めないまま、電車の窓に映る自分の顔をみつめていた。
「……なんで、私が“契約花嫁”なんてことに……」
天井の蛍光灯に照らされた自分の表情は、驚きと不安の混ざった“昨日のまま”。
(普通のOLで、地味で、特技も何もないのに……)
(相手は、御堂怜司。財閥の御曹司。手の届かない世界の人。)
昨日の彼の言葉が、まだ耳の奥で響いていた。
『君なら、悪くないと思った』
(……あれって、どういう意味だったの?)
そんな疑問を抱えたまま、紗菜は指定された車両に乗り換える。
そこには、運転手付きの黒い車が待っていた。
「桜井紗菜様ですね。御堂家よりお迎えに参りました」
丁寧な言葉遣いに、紗菜は慌てて頭を下げた。
――どう考えても、自分はそんな扱いを受けるような人間じゃない。
しかし車は、その“自分の価値観”などお構いなしに、
高級住宅街を抜け、さらに奥へ奥へと進んでいく。
そして目の前に現れたのは――
ガラスの城。
いや、そうとしか言いようがなかった。
天井まで届くガラス張りの壁。
真っ白な外壁と、彫刻のように整えられた庭木。
重厚な鉄のゲートがゆっくりと開く音がするたび、紗菜の心臓は跳ねた。
(ここが……怜司さんの家……?)
門をくぐった瞬間、まるで空気まで変わったように感じた。
普通と豪奢の境界線を、確かに越えてしまったのだ。
玄関ホールに足を踏み入れたそのとき。
カツ、カツ――と靴音が響く。
ゆっくりと階段から降りてきたのは、怜司だった。
黒のシャツにダークグレーのスラックス。
“仕事帰りの御曹司”という存在だけで、空気が締まる。
「……来たのか」
それだけなのに、胸の奥がじん、と熱くなる。
「え、えっと……あの、昨日のことなんですけど……
契約結婚って、その……本当に私なんかで……?」
怜司は足を止め、真っすぐに紗菜を見る。
目が合った瞬間、呼吸が浅くなった。
彼の瞳には、冷たさよりも――意志があった。
「君じゃなきゃ困る」
「っ……!」
言葉が喉にひっかかった。
「祖母――会長は、身分だの家柄だのと煩い。
“結婚候補”なんて勝手にリストまで作り始めた」
怜司は少しだけ表情を曇らせる。
「……俺は、ああいう政治的な婚姻が嫌なんだ」
そして、さっきより少し柔らかい声で続けた。
「昨日、お前を見たとき……直感した」
「ちょ、ちょっと待ってください!
私、特別なこと何もしてませんよ……!?
むしろ、私は――」
怜司は近づき、彼女の言葉をそっと遮った。
「静かに。落ち着け」
その声音が優しすぎて、紗菜は一瞬言葉を失った。
怜司はさらに歩み寄る。
距離が……近い。
「俺が選んだ理由は君にはわからないだろうが……」
指先が紗菜の髪に触れ、ふわりと頬に落ちる。
「……“普通の幸せ”を知っている女性を、俺は欲しかった」
心臓が跳ねた。
頬が熱くなり、息が詰まる。
「お前には、俺の世界にない“大切なもの”がある。
俺は……それを欲している」
まっすぐな声。
嘘やごまかしのない、本音の響き。
(そんなふうに言われたら……断れない……)
怜司は小さな書類の束を手にして、紗菜の前に差し出した。
「これが契約書だ。
半年間、俺の婚約者として生活してもらう」
紗菜は震える手で受け取り、ページをめくる。
そこには細かい条項がずらりと並んでいて――
その中のひとつに、目が留まった。
【御堂怜司は、桜井紗菜の生活を全面的に保証する】
【精神的・身体的に無理な要求は絶対に行わない】
【紗菜を守ること】
(え……?)
思わず顔を上げると、怜司は少しだけ照れたように視線をそらした。
「……会長が口を出してこないように俺が書いた。
“俺の花嫁に負担をかけさせるな”ってな」
ドクン――
心臓が大きな音を立てた。
(……花嫁……って……)
怜司は、ほんの一呼吸のあと、紗菜に向き直った。
「紗菜。
契約でも形だけでも構わない。
――俺の隣に立ってほしい」
紗菜の胸はぎゅう、と締めつけられた。
この豪華な世界にも、自分を必要としてくれる人がいる。
そんなふうに思えた瞬間だった。
そして――
ゆっくりとペンを取り、契約書に名前を書いた。
「……桜井紗菜、署名しました」
怜司の瞳が、かすかに揺れる。
その揺れが、なぜか優しさに見えた。
「……これで今日から、お前は俺の婚約者だ」
怜司はそっと紗菜の手を取り、温かく握る。
その仕草は、契約のためのスキンシップではなく――
紗菜を包み、導く“本物の手”だった。
(……こんなの、もう……)
――恋してしまうに決まってる。
そう思った瞬間、怜司の親指が紗菜の手の甲を、
優しくなぞった。
そして、低く甘い声で囁く。
「覚悟しておけよ。
契約でも……俺は、お前を甘やかすつもりだ」
紗菜の心臓が、大きく跳ねた。
こうして紗菜は、
“ガラスの城で始まる、身分差×溺愛婚”へと足を踏み出した。