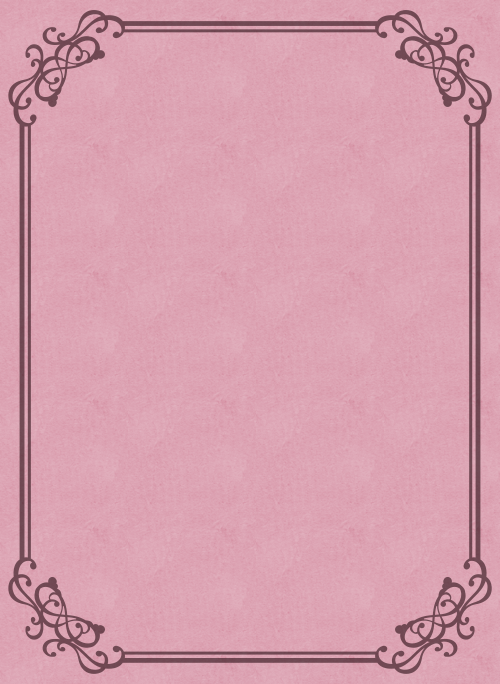「次の支援先、決まりましたわ」
アメリアが馬車の中で広げた地図を指差す。
目的地は、西部高台に位置する“トルナ村”。
「定着率12%。村民の半数は“開拓支援自体に反発的”。行政への不信、代表不在、対話拒否が続いている場所です」
「まって。それってもう“村”として成立してないんじゃ……」
「だからこそ、行く価値がありますの」
馬車はがたんと揺れ、風がきしむ。
「前回のルグレア村と違って、今度は“対話の糸口すらない”可能性が高い」
「つまり、“耕しに行く”というより、“壁に鍬を叩きつける”ようなものですね」
「ええ。ですから今回は、“支援”という言葉そのものを問い直す必要があるかもしれません」
アメリアの視線は、すでに“まだ名のない土地”の向こうを見据えていた。
馬車がトルナ村の門前に到着したのは、午後の日差しが村の影を濃くし始めた頃だった。
門は閉ざされていた。無言の拒絶。
「……誰か、いらっしゃいませんの?」
呼びかけに応える者はいない。だが、視線は感じた。
木の柵の隙間から、石の建物の影から、鋭く冷たい目線が向けられていた。
「完全に“外からの介入者”扱いですね……」
「正直、棒人間すら入り込めない雰囲気だ……」
それでもアメリアは、正面に立ち、門を叩いた。
「カレジア村・開拓連盟支援隊、アメリア・ルヴァリエと申します。わたくしたちは、“支配しに来た”のではありません。“耕す選択肢を届けに来た”のです」
それでも門は開かない。
数分の沈黙。
やがて、門の上から男の声が落ちてきた。
「帰れ。もう“自分たちのために来た”という言葉には、飽きた」
アメリアは即座に返す。
「それなら、わたくしは“あなたたちのため”には来ていません。“わたくしたちの未来のため”に来たのです」
「……なんだと?」
「あなたたちが“ここで暮らす”という選択肢を失えば、連盟そのものが“機能不全”になる。それはすなわち、開拓という言葉が“砂の上の理想”になるということです。だから、わたくしたちは来ました。“ここで暮らし続けるために、あなたたちに選んでほしい”と」
再び沈黙。
ルークが呟いた。
「……お嬢様、理論と情熱を同時にぶつけるの、反則ですよ……」
バタン、と音を立てて門が少しだけ開いた。
その隙間から現れたのは、ボサボサの黒髪と深い眼差しを持つ青年だった。
「俺はラド。村の臨時代表だ。話は……聞いてやる」
アメリアは、一歩前に出て、微笑んだ。
「ありがとうございます。ではまず、鍬と椅子を一脚、貸していただけますか?」
「椅子?」
「ええ。“ここに座る理由”を、まず耕しますの」
臨時代表ラドに案内されたのは、村の中心にある石造りの集会所。
「中に入ってもいいが、ここでは誰も歓迎しねえ。忘れんな」
「心得ておりますわ」
木製の長机、固い椅子。そこに座ったラドの背には、言葉より重い沈黙があった。
アメリアは、その向かいにゆっくりと腰を下ろす。
「まずは、お話を聞かせてください」
「聞いてどうする。どうせ、上の都合で“支援対象地”に選ばれたってだけだろ」
「“上”の意志で来たのは事実です。ですが“わたくしたち”が動いているのは、“下から積み上げる未来”のためです」
ラドの眉が少しだけ動いた。
「綺麗事だな」
「ええ。綺麗事を“実際に耕してきた”のが、わたくしたちカレジア村ですの」
「……耕したものが腐ることもある」
「土が腐るのではありません。“信頼”が“見放される”ことこそ、腐敗のはじまりですわ」
一拍の沈黙。
ラドは机の上に拳を置いた。
「いいか。“この村”は、3回、支援を受けて裏切られた。最初は農具だけを渡され、実地指導なし。次は行政が派遣した技官が“やる気がない”と切り捨てて帰った。最後は、視察名目で来た連盟職員が、“やっぱりこの村は無理だ”と文書に書いたのを読んだ。そうして、“自分たちは見限られた”と知ってなお、誰を信じろって言うんだよ」
静かに、アメリアは答えた。
「信じていただかなくて、構いませんわ」
ラドが目を見開いた。
「わたくしは、“支援に信頼を求める”とは思っておりません。支援とは、“信頼されたい側”が“努力し続けること”に意味があると考えております。だから、まずは鍬を振らせていただきますの」
「……へえ」
「“信じられる”かどうかではなく、“何が残るか”で支援の価値は決まるはずです」
ラドは立ち上がった。
「……明日の朝、お前らのやり方を見せてみろ。その上で、“この村で何ができるか”を話してやる」
アメリアは深く一礼した。
「光栄ですわ」
その夜、支援隊の宿舎(倉庫を改修したもの)で、ルークがふと呟いた。
「お嬢様、今日すごかった……火花っていうか、“思想の地割れ”だった……」
「でも……耕しとは、元々“硬い土”を相手にするものですわ」
翌朝。空気は冷え、土はまだ湿っていた。
だが、アメリアは既に鍬を握っていた。
「わたくしたちは、“命令”をするために来たのではありません。ただ、“手を動かす姿”を見せることで、あなたたち自身に問いを投げかけますの」
広場の一角に設けられたデモ畑。
アメリアが耕し、ガストンが整地し、リリアが資料整理。
ルークは実況と棒人間看板の設置、ゼクスは“鍬の使い方”を彫った石板を立てた。
「支援って……講義じゃないのか」
「黙って、やって見せるだけ?」
村人たちの戸惑いは、やがてざわめきに変わる。
その日の昼過ぎ。
子どもたちが近づいてきた。
「これ、触っていい?」
「わたしも、やってみたい……」
「もちろん。鍬には“誰かの名前”なんてついていませんから」
子どもたちが畝を踏みしめ、初めての耕しに声をあげる。
その姿を見て、大人たちが動いた。
「……あいつらが、土に触れたのは初めてだ」
「じゃあ、オレらはそれを“育てる側”に回るべきかもな」
午後には、計7名の村人が耕作に加わっていた。
夕刻。
ラドが現れ、畑の前で立ち止まった。
「……見せるだけ、ってのは、本当に効くんだな」
アメリアは微笑む。
「ええ。“土の音”は、言葉より届きますの」
ラドは一歩踏み出して、鍬を手に取った。
「……俺にも、貸してくれ」
その瞬間、村人の誰かが言った。
「……村長の手だ」
言葉は短く、だが確かなものだった。
支援八日目。空は晴れ渡り、朝露に濡れた土はやわらかかった。
広場では、村人たちとカレジア支援隊が共に並び、
最後の“共耕式畑づくり”に取りかかっていた。
ラドが最前列で鍬を振るい、ゼクスの石板指示に従って作業が進んでいく。
「……この畝、真っ直ぐじゃないけど、なんかいいな」
「まっすぐだけが“正しい耕し方”じゃないってことですね」
(リリア)
アメリアは畑の中央で手を止め、周囲を見渡した。
かつて沈黙と拒絶に覆われていた場所に、いま確かに“声”があった。
笑い声、土を叩く音、鍬を置いて腰を伸ばす仕草。
それはすべて、“生きている村”の証だった。
午後。
支援隊の帰還を前に、村人たちがひとつの提案を持ってきた。
「この畑……名前をつけたいんだ」
アメリアは目を見開いた。
「ええ、もちろん。どんな名前を?」
ラドが、一歩前に出て言った。
「“アメリア畝”」
「えっ!?」(支援隊全員)
「いや、“カレジア”でもよかったんだけどさ……お前の鍬が、この村の“最初の音”だったから」
アメリアは一瞬だけ戸惑い、そして、深く頭を下げた。
「身に余る光栄ですわ。では、もうひとつ提案をさせていただいてよろしいかしら?」
「お?」
「“アメリア畝”ではなく、“第一畝”と名付けてくださいませんか」
「それは……なぜ?」
「この先、“第二畝”も、“第三畝”も、あなた方自身の手で育てていくべきだからです」
ラドが、にやりと笑った。
「了解だ。……なら、俺たちが責任持って“第二”を耕すさ」
広場に、拍手と笑いが溶けていった。
その夕暮れ。
アメリアは広場の端に小さな杭を立てた。
そこにはゼクスが刻んだ文字があった。
【第一畝:この畝は、信頼を土に変えた鍬の音から始まった】
支援最終日。朝靄の中、支援隊は荷物をまとめていた。
だが、その日はいつもと違っていた。
村の広場には、すでに村人たちが集まり、何かを準備していたのだ。
「これは……?」
ラドが前に出る。
「見送り式だ。俺たちが“初めて主催する式典”だ」
中央に飾られていたのは、村人たちが手作りした“鍬型の木彫りオブジェ”。
その下には、子どもたちが描いた絵と、手書きの言葉が並んでいた。
『ありがとうカレジア』
『また来てねアメリアおねーちゃん』
『鍬が好きになったよ』
アメリアは、喉の奥が熱くなるのを感じた。
リリアは鼻をすすりながら小声で言う。
「お嬢様、“支援”って、こんなに重くて、あたたかいものだったんですね……」
ラドがアメリアに、小さな木箱を差し出す。
「これは、村で初めて掘った芋だ。小さいけど、オレたちの“再出発の証”だ」
「……受け取りますわ。とても、大切なものとして」
ルークが叫ぶ。
「干し芋にしたら永久保存するぞおおお!!」
「干し芋にする前提ですの!?」
そのとき、ゼクスが最後の石板を立てた。
【ここに、第一の鍬が置かれた。次は、誰かの手に。】
馬車が揺れる。
村の風景が遠ざかる。
アメリアは後ろを振り返り、小さく手を振った。
「さようなら、“トルナ村”。いえ、“歩き始めたあなたたち”へ」
アメリアが馬車の中で広げた地図を指差す。
目的地は、西部高台に位置する“トルナ村”。
「定着率12%。村民の半数は“開拓支援自体に反発的”。行政への不信、代表不在、対話拒否が続いている場所です」
「まって。それってもう“村”として成立してないんじゃ……」
「だからこそ、行く価値がありますの」
馬車はがたんと揺れ、風がきしむ。
「前回のルグレア村と違って、今度は“対話の糸口すらない”可能性が高い」
「つまり、“耕しに行く”というより、“壁に鍬を叩きつける”ようなものですね」
「ええ。ですから今回は、“支援”という言葉そのものを問い直す必要があるかもしれません」
アメリアの視線は、すでに“まだ名のない土地”の向こうを見据えていた。
馬車がトルナ村の門前に到着したのは、午後の日差しが村の影を濃くし始めた頃だった。
門は閉ざされていた。無言の拒絶。
「……誰か、いらっしゃいませんの?」
呼びかけに応える者はいない。だが、視線は感じた。
木の柵の隙間から、石の建物の影から、鋭く冷たい目線が向けられていた。
「完全に“外からの介入者”扱いですね……」
「正直、棒人間すら入り込めない雰囲気だ……」
それでもアメリアは、正面に立ち、門を叩いた。
「カレジア村・開拓連盟支援隊、アメリア・ルヴァリエと申します。わたくしたちは、“支配しに来た”のではありません。“耕す選択肢を届けに来た”のです」
それでも門は開かない。
数分の沈黙。
やがて、門の上から男の声が落ちてきた。
「帰れ。もう“自分たちのために来た”という言葉には、飽きた」
アメリアは即座に返す。
「それなら、わたくしは“あなたたちのため”には来ていません。“わたくしたちの未来のため”に来たのです」
「……なんだと?」
「あなたたちが“ここで暮らす”という選択肢を失えば、連盟そのものが“機能不全”になる。それはすなわち、開拓という言葉が“砂の上の理想”になるということです。だから、わたくしたちは来ました。“ここで暮らし続けるために、あなたたちに選んでほしい”と」
再び沈黙。
ルークが呟いた。
「……お嬢様、理論と情熱を同時にぶつけるの、反則ですよ……」
バタン、と音を立てて門が少しだけ開いた。
その隙間から現れたのは、ボサボサの黒髪と深い眼差しを持つ青年だった。
「俺はラド。村の臨時代表だ。話は……聞いてやる」
アメリアは、一歩前に出て、微笑んだ。
「ありがとうございます。ではまず、鍬と椅子を一脚、貸していただけますか?」
「椅子?」
「ええ。“ここに座る理由”を、まず耕しますの」
臨時代表ラドに案内されたのは、村の中心にある石造りの集会所。
「中に入ってもいいが、ここでは誰も歓迎しねえ。忘れんな」
「心得ておりますわ」
木製の長机、固い椅子。そこに座ったラドの背には、言葉より重い沈黙があった。
アメリアは、その向かいにゆっくりと腰を下ろす。
「まずは、お話を聞かせてください」
「聞いてどうする。どうせ、上の都合で“支援対象地”に選ばれたってだけだろ」
「“上”の意志で来たのは事実です。ですが“わたくしたち”が動いているのは、“下から積み上げる未来”のためです」
ラドの眉が少しだけ動いた。
「綺麗事だな」
「ええ。綺麗事を“実際に耕してきた”のが、わたくしたちカレジア村ですの」
「……耕したものが腐ることもある」
「土が腐るのではありません。“信頼”が“見放される”ことこそ、腐敗のはじまりですわ」
一拍の沈黙。
ラドは机の上に拳を置いた。
「いいか。“この村”は、3回、支援を受けて裏切られた。最初は農具だけを渡され、実地指導なし。次は行政が派遣した技官が“やる気がない”と切り捨てて帰った。最後は、視察名目で来た連盟職員が、“やっぱりこの村は無理だ”と文書に書いたのを読んだ。そうして、“自分たちは見限られた”と知ってなお、誰を信じろって言うんだよ」
静かに、アメリアは答えた。
「信じていただかなくて、構いませんわ」
ラドが目を見開いた。
「わたくしは、“支援に信頼を求める”とは思っておりません。支援とは、“信頼されたい側”が“努力し続けること”に意味があると考えております。だから、まずは鍬を振らせていただきますの」
「……へえ」
「“信じられる”かどうかではなく、“何が残るか”で支援の価値は決まるはずです」
ラドは立ち上がった。
「……明日の朝、お前らのやり方を見せてみろ。その上で、“この村で何ができるか”を話してやる」
アメリアは深く一礼した。
「光栄ですわ」
その夜、支援隊の宿舎(倉庫を改修したもの)で、ルークがふと呟いた。
「お嬢様、今日すごかった……火花っていうか、“思想の地割れ”だった……」
「でも……耕しとは、元々“硬い土”を相手にするものですわ」
翌朝。空気は冷え、土はまだ湿っていた。
だが、アメリアは既に鍬を握っていた。
「わたくしたちは、“命令”をするために来たのではありません。ただ、“手を動かす姿”を見せることで、あなたたち自身に問いを投げかけますの」
広場の一角に設けられたデモ畑。
アメリアが耕し、ガストンが整地し、リリアが資料整理。
ルークは実況と棒人間看板の設置、ゼクスは“鍬の使い方”を彫った石板を立てた。
「支援って……講義じゃないのか」
「黙って、やって見せるだけ?」
村人たちの戸惑いは、やがてざわめきに変わる。
その日の昼過ぎ。
子どもたちが近づいてきた。
「これ、触っていい?」
「わたしも、やってみたい……」
「もちろん。鍬には“誰かの名前”なんてついていませんから」
子どもたちが畝を踏みしめ、初めての耕しに声をあげる。
その姿を見て、大人たちが動いた。
「……あいつらが、土に触れたのは初めてだ」
「じゃあ、オレらはそれを“育てる側”に回るべきかもな」
午後には、計7名の村人が耕作に加わっていた。
夕刻。
ラドが現れ、畑の前で立ち止まった。
「……見せるだけ、ってのは、本当に効くんだな」
アメリアは微笑む。
「ええ。“土の音”は、言葉より届きますの」
ラドは一歩踏み出して、鍬を手に取った。
「……俺にも、貸してくれ」
その瞬間、村人の誰かが言った。
「……村長の手だ」
言葉は短く、だが確かなものだった。
支援八日目。空は晴れ渡り、朝露に濡れた土はやわらかかった。
広場では、村人たちとカレジア支援隊が共に並び、
最後の“共耕式畑づくり”に取りかかっていた。
ラドが最前列で鍬を振るい、ゼクスの石板指示に従って作業が進んでいく。
「……この畝、真っ直ぐじゃないけど、なんかいいな」
「まっすぐだけが“正しい耕し方”じゃないってことですね」
(リリア)
アメリアは畑の中央で手を止め、周囲を見渡した。
かつて沈黙と拒絶に覆われていた場所に、いま確かに“声”があった。
笑い声、土を叩く音、鍬を置いて腰を伸ばす仕草。
それはすべて、“生きている村”の証だった。
午後。
支援隊の帰還を前に、村人たちがひとつの提案を持ってきた。
「この畑……名前をつけたいんだ」
アメリアは目を見開いた。
「ええ、もちろん。どんな名前を?」
ラドが、一歩前に出て言った。
「“アメリア畝”」
「えっ!?」(支援隊全員)
「いや、“カレジア”でもよかったんだけどさ……お前の鍬が、この村の“最初の音”だったから」
アメリアは一瞬だけ戸惑い、そして、深く頭を下げた。
「身に余る光栄ですわ。では、もうひとつ提案をさせていただいてよろしいかしら?」
「お?」
「“アメリア畝”ではなく、“第一畝”と名付けてくださいませんか」
「それは……なぜ?」
「この先、“第二畝”も、“第三畝”も、あなた方自身の手で育てていくべきだからです」
ラドが、にやりと笑った。
「了解だ。……なら、俺たちが責任持って“第二”を耕すさ」
広場に、拍手と笑いが溶けていった。
その夕暮れ。
アメリアは広場の端に小さな杭を立てた。
そこにはゼクスが刻んだ文字があった。
【第一畝:この畝は、信頼を土に変えた鍬の音から始まった】
支援最終日。朝靄の中、支援隊は荷物をまとめていた。
だが、その日はいつもと違っていた。
村の広場には、すでに村人たちが集まり、何かを準備していたのだ。
「これは……?」
ラドが前に出る。
「見送り式だ。俺たちが“初めて主催する式典”だ」
中央に飾られていたのは、村人たちが手作りした“鍬型の木彫りオブジェ”。
その下には、子どもたちが描いた絵と、手書きの言葉が並んでいた。
『ありがとうカレジア』
『また来てねアメリアおねーちゃん』
『鍬が好きになったよ』
アメリアは、喉の奥が熱くなるのを感じた。
リリアは鼻をすすりながら小声で言う。
「お嬢様、“支援”って、こんなに重くて、あたたかいものだったんですね……」
ラドがアメリアに、小さな木箱を差し出す。
「これは、村で初めて掘った芋だ。小さいけど、オレたちの“再出発の証”だ」
「……受け取りますわ。とても、大切なものとして」
ルークが叫ぶ。
「干し芋にしたら永久保存するぞおおお!!」
「干し芋にする前提ですの!?」
そのとき、ゼクスが最後の石板を立てた。
【ここに、第一の鍬が置かれた。次は、誰かの手に。】
馬車が揺れる。
村の風景が遠ざかる。
アメリアは後ろを振り返り、小さく手を振った。
「さようなら、“トルナ村”。いえ、“歩き始めたあなたたち”へ」