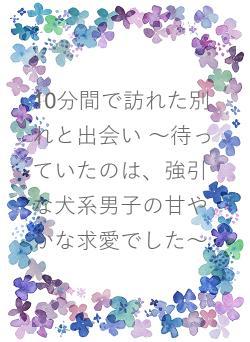「……あなたから、すごくいい匂いがしたので。何の香水を使っているのかなって、気になったんです」
観念した結香が正直に話せば、黒髪の彼は目を丸めた。かと思えば、クスクスと笑いだす。
口許に指を添えているその仕草からは、気品のようなものが感じられる。笑い方ひとつとっても綺麗な人だと思う。けれど――。
「……そんなに笑わなくてもいいじゃないですか」
「ふっ……いや、すまない。肩書や容姿について評価されたことはあっても、そんな風に匂いについて触れられたことはなかったからね」
「……それって嫌味ですか?」
「嫌味に聴こえたならすまないが、事実だよ」
平然とした顔で、さらりと返される。
何だか鼻につく男だと思いながらも、彼が容姿端麗であることは事実だ。実際これまでの人生で、その容姿について数えきれないほど褒めそやされて生きてきたのだろう。
「君はずいぶん鼻が良いんだね」
「……馬鹿にしてますよね?」
「何故? 褒めているんだよ」
揶揄されていると思った結香が不満げな顔をすれば、黒髪の彼は心底不思議そうな表情で目を丸めた。どうやら、心からの誉め言葉だったようだ。