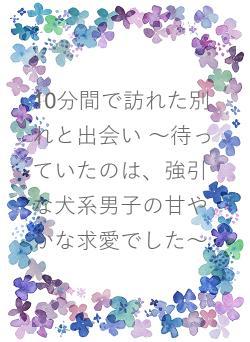「黙っていてすまなかった。だが、社長という肩書きのせいで君に距離を置かれたり、遠慮されたくはなかったんだ」
「驚きはしましたけど……事情は分かりましたし、大丈夫です」
優雅の言う通り、もし初めから社長だと分かっていたら、何を話すにも緊張や遠慮の気持ちが勝ってしまい、今のような関係は築けていなかっただろう。
「あの日、エレベーターで君が、俺のつけていた香について触れてくれただろう? それよりもずっと前から、君と話せる機会を伺っていた。……といったら、困らせてしまうかな」
「……え?」
それはどういうことなのか。困惑を顕わにしている結香を見てクスリと微笑んだ優雅は、過去の思い出を語り始める。
「白石さんは覚えていないかもしれないけど、今からちょうど一年ほど前にも、俺と君は話したことがあるんだよ」
「えっ、私と真宮さんがですか?」
「あぁ。あの頃から父には、社長引継ぎの件について話を持ち掛けられていてね。一時期、日本に戻ってきていたんだ。だが当時は、俺が社長の座に就任して上手くやっていけるのかと悩んでいてね。会社の近くにある喫茶店に入って、窓際のカウンター席でボーッとしていた時、隣に白石さんが座ってきたんだ」
結香は一年前の記憶を辿ろうとするが、優雅と出会った記憶は中々思い出せない。
優雅は更に話を続けていく。