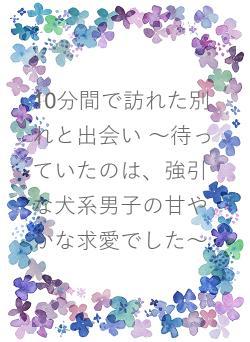(……勘違い、されちゃったよね)
別に優雅とは交際しているわけでもないし、友人という関係にすらなれているのかも分からない。はっきりとした名前も付けられないような関係性だ。
だから、勘違いされて困ることなど何一つないはず。それなのに――どうしてこんなにも、胸が痛むのか。
自分がはっきり否定しなかったのが悪いことも分かっていたが、何故か声が出せなかった。
……それは多分、自信がないからだ。
昨日見た、優雅の恥じらうような表情が忘れられない。その顔を向けられていた美しい女性のことも。
優雅はあの女性と付き合っているのかもしれない。そう考えてもいたのだが、さっき見た優雅の表情はひどく苦しそうだった。
結香と洸樹がよりを戻したとして、どうして優雅がそれを気にするのだろう。
――優雅の気持ちが分からなかった。正解が何一つ分からず、心の中はぐちゃぐちゃだ。
結香はしばらくの間、その場で立ちすくみボーッとしていたが、頼りない足取りで動き出す。
エレベーター乗り場まで行き、そこでようやく、ここが最上階だということに気づいた。
一階の釦を押してエレベーターがくるのを待っていれば、綺麗なソプラノ声に名前を呼ばれた。
「白石結香さん、でお間違いないでしょうか?」
振り向けば、そこに立っていたのは眼鏡をかけスーツを着ている美しい女性。
――優雅の仕事仲間であろう、例の女性だった。