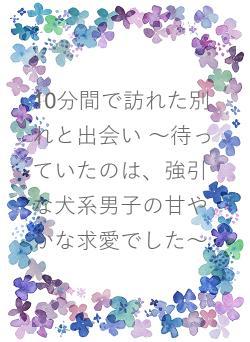***
遅めの昼食を終えた二人は、その後も近くのアパレルショップを巡った。
楽しい時間が過ぎていくのはあっという間だ。気づけば陽も沈み始め、見上げる空は藍色と橙色が混ざり合っている。
優雅はこれから予定が入っているらしく、そろそろ解散しようということになった。
「本当に家まで送らなくてもいいのか?」
「はい。ここから電車で一本ですし、帰りにスーパーで買い物もしたいので」
「わかった。それじゃあ、気をつけて帰ってくれ。今日のデート、楽しかったよ」
「で、デートですか?」
「あぁ。俺はデートだと思って過ごしていたけどね」
「でも、リサーチとか言ってませんでしたか?」
「それもあったけど……本音はただ、君と過ごしたかったんだ」
――それは、どういう意味で言っているのだろうか。
結香は考えあぐねてしまう。
期待してはだめだと思いながらも、心の片隅にある“もしかしたら”の希望を消せ切れない。
芽生え始めたばかりの恋心が、今にも顔を出そうとしている。
「……白石さん。君に伝えておきたいことがあるんだ」
優雅は開いていた距離を、一歩詰めてくる。顔を上げれば、熱っぽい目は結香を真っ直ぐに見下ろしていた。心臓がドクドクと激しく鳴り響いているのが分かる。
「……結香?」
――けれど、緊張と甘やかさが混ざり合った空気を引き裂くようにしてかけられた声に、結香と優雅は同時に視線を横に動かした。
数メートル離れた場所に立っていたのは、背丈のあるひょろりとした男だった。
明るく染められた金髪は、根本の方が少し黒っぽくなっている。作業着を着ている彼は電気工事会社で働いていたはずだ。もしかしたら勤務中で、工事を行う現場に向かっている途中なのかもしれない。
「……洸樹」
結香が名前を呼んだこの男は、もう一年近くは顔を合わせることのなかった、元カレだった。