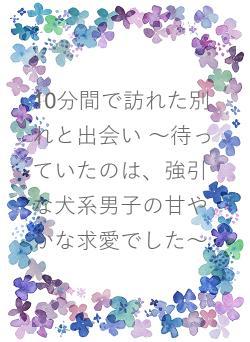「いえ、これ以上ご迷惑はかけられませんので! というか、真宮さんの買い物に付き合うはずだったのに、私まで楽しんでしまってすみません……」
「どうして謝るんだ? むしろ俺は嬉しいよ、白石さんが楽しんでくれていて。君は本当に香水の類が好きなんだね」
優雅は微笑む。その表情が優しくて、何故だか胸の辺りがぎゅっと締め付けられる。
苦しいけれど、嫌ではない。むしろ、この胸の痛みは……。
結香は今にも自覚してしまいそうな胸の内に気づいて、慌ててオムライスを頬張って気を紛らわせる。
「白石さんは、いつから香水が好きだったんだ?」
「え、っと、そうですね……本格的に香水の類を買いだしたのは、高校生の頃だと思います。でも私、香水が好きというよりは、香りを楽しむことが好きなんです」
「香りを?」
「はい。例えば、雨が降り出す前の特有の匂いとか、喫茶店で珈琲を淹れている香りとか、そういう日常から感じられる匂いも好きなんです。春は桜だったり、今の時期なら金木犀とか、そういう人工的じゃない、自然の香りも好きで」
「なるほど。白石さんは風流を楽しむことのできる人なんだな」
「いや、風流とかそんな大層な言葉で表してもらえるような人間じゃないんですけど……! 言っちゃえば、ただの匂いフェチなんです。それに香水とかって、匂いを嗅ぐだけで異国の地に行ったような気分にもなれちゃいますし、お気に入りの匂いをまとったら、それだけで気持ちも強くなれたような気がするっていうか……私的には、お守り代わりに使うこともあったりして。だから、香りってすごいなって思うんです」
自身の思いをつらつらと語っていた結香は、ハッとした。どうでもいい話を長々と聞かせてしまったと、申し訳ない気持ちでいっぱいになってしまう。