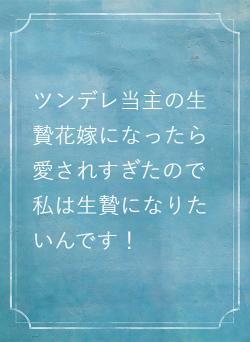彼女が驚いたように俺を見つめる。
「私、入谷さんのこと、無自覚イケメンだと思ってました」
「あはは。無自覚どころか超自覚してわざとやってたんだけど」
「えっ?」
「俺はぐいぐい取り囲んでくる君達じゃなくて、深沢さんに興味があるよって」
果たして俺の心はどれだけ彼女に伝わるだろうか。
「それにさ、俺が嫌われてるからかもよ?」
「入谷さんが? そんなわけ……」
「だって俺、将来有望なしごできエリート営業部員だよ? 先輩、同期、後輩。みんな表面では笑い合ってるけど裏では誰にやっかまれてるかわからない。実際本社にいた時も何度も嫌がらせされてるし」
「そうなんだ……」
「望むならUSBの犯人捜ししてもいいけど。どうする?」
彼女はすぐに大きく首を横に振った。
「いいです。たとえ誰かの仕業とわかったとしても気まずいだけだから」
「うん、賛成。だけどたしかに俺達が会ってることはもう会社の人に知られない方がいいね。今夜のことも二人だけの秘密にしよう」
「はい」
「遅くまで俺のためにがんばってくれてありがとう。あとは何も心配しなくていいから。安心して眠って」
ずっと俺を見上げている彼女が健気すぎて、また頭をぽんぽんしてしまう。
そろそろ拒絶されるかと思いきや、彼女はそっと目を閉じた。
えっ!? まさかそれって!? いいの!!?
俺がキスしてもいいのかと慌てた瞬間、彼女は目を閉じて椅子に座ったまま眠っていた。
なんだ、眠かっただけか。あーびっくりした!
眠ってしまった彼女を起こさないようそっと抱きかかえてソファーへと運ぶ。
横になって眠っている彼女はまるで、毒林檎を齧って眠ってしまった白雪姫のようだ。
少しだけでいいから触れてみたい。その頬に唇に……。
いや、もし触れている時に目を覚まされたら言い訳できない。
ただでさえ嫌われていてもう後がないのだから。
触れたい衝動を我慢して彼女の身体の上に毛布をかけると、俺はプレゼンの資料作成を一人で続けた。
「私、入谷さんのこと、無自覚イケメンだと思ってました」
「あはは。無自覚どころか超自覚してわざとやってたんだけど」
「えっ?」
「俺はぐいぐい取り囲んでくる君達じゃなくて、深沢さんに興味があるよって」
果たして俺の心はどれだけ彼女に伝わるだろうか。
「それにさ、俺が嫌われてるからかもよ?」
「入谷さんが? そんなわけ……」
「だって俺、将来有望なしごできエリート営業部員だよ? 先輩、同期、後輩。みんな表面では笑い合ってるけど裏では誰にやっかまれてるかわからない。実際本社にいた時も何度も嫌がらせされてるし」
「そうなんだ……」
「望むならUSBの犯人捜ししてもいいけど。どうする?」
彼女はすぐに大きく首を横に振った。
「いいです。たとえ誰かの仕業とわかったとしても気まずいだけだから」
「うん、賛成。だけどたしかに俺達が会ってることはもう会社の人に知られない方がいいね。今夜のことも二人だけの秘密にしよう」
「はい」
「遅くまで俺のためにがんばってくれてありがとう。あとは何も心配しなくていいから。安心して眠って」
ずっと俺を見上げている彼女が健気すぎて、また頭をぽんぽんしてしまう。
そろそろ拒絶されるかと思いきや、彼女はそっと目を閉じた。
えっ!? まさかそれって!? いいの!!?
俺がキスしてもいいのかと慌てた瞬間、彼女は目を閉じて椅子に座ったまま眠っていた。
なんだ、眠かっただけか。あーびっくりした!
眠ってしまった彼女を起こさないようそっと抱きかかえてソファーへと運ぶ。
横になって眠っている彼女はまるで、毒林檎を齧って眠ってしまった白雪姫のようだ。
少しだけでいいから触れてみたい。その頬に唇に……。
いや、もし触れている時に目を覚まされたら言い訳できない。
ただでさえ嫌われていてもう後がないのだから。
触れたい衝動を我慢して彼女の身体の上に毛布をかけると、俺はプレゼンの資料作成を一人で続けた。