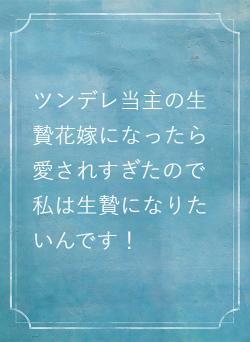そんな中、何気なく読んでいた図書室便りの「今月の図書」のコラムが俺の心にガンガン響いていることに気が付いた。
毎月いつ更新されるのか楽しみで、用もないのに階段の踊り場詣でをするようになっていたのだ。
コラムの内容は本の紹介なのに読むと不思議と靄が晴れていくような気持ちになった。
一言もそんなことは書かれてないのに、その独特な物事の捉え方に目から鱗が落ちて元気になれた。
誰が書いているのだろうと気になりはじめ同じクラスの図書委員に聞くと、一学年下の「深沢月見」だと教えてくれた。
彼女のことは知っていた。
但しそれは、友達だった雪見ちゃんの「双子の姉の眼鏡をかけている方」という認識でしかなかった。
しかしそれからは、廊下ですれ違ったりするたびに意識するようになった。
図書室で本を読んでいる彼女の横顔を、気付かれないよう本棚の陰からそっと見つめたりもした。
窓から入ってくる光を浴びて静かに本を読む彼女の姿。
それは深く暗い森で彷徨い歩いている俺を、東の空から昇って照らしだしてくれた満月のようだった。
夜空で輝く満月には手が届くはずもなく見上げることしかできない。
しかしその光は確実に俺に届き照らし導いてくれた。
大袈裟なのはわかっている。でもそれだけ俺の心は壊れていた。
彼女は俺の希望になった。
なぜならあれほど信じていなかった「好き」という感情が、自分の中から溢れ出してくるのを抑えきれなかったから。
彼女の横顔の曲線は雪見ちゃんと同じなのに、誰も彼女の美しさに気付いていないことに安堵した。
彼女の魅力がわかるのは俺だけだと、自負し自尊した。
毎月いつ更新されるのか楽しみで、用もないのに階段の踊り場詣でをするようになっていたのだ。
コラムの内容は本の紹介なのに読むと不思議と靄が晴れていくような気持ちになった。
一言もそんなことは書かれてないのに、その独特な物事の捉え方に目から鱗が落ちて元気になれた。
誰が書いているのだろうと気になりはじめ同じクラスの図書委員に聞くと、一学年下の「深沢月見」だと教えてくれた。
彼女のことは知っていた。
但しそれは、友達だった雪見ちゃんの「双子の姉の眼鏡をかけている方」という認識でしかなかった。
しかしそれからは、廊下ですれ違ったりするたびに意識するようになった。
図書室で本を読んでいる彼女の横顔を、気付かれないよう本棚の陰からそっと見つめたりもした。
窓から入ってくる光を浴びて静かに本を読む彼女の姿。
それは深く暗い森で彷徨い歩いている俺を、東の空から昇って照らしだしてくれた満月のようだった。
夜空で輝く満月には手が届くはずもなく見上げることしかできない。
しかしその光は確実に俺に届き照らし導いてくれた。
大袈裟なのはわかっている。でもそれだけ俺の心は壊れていた。
彼女は俺の希望になった。
なぜならあれほど信じていなかった「好き」という感情が、自分の中から溢れ出してくるのを抑えきれなかったから。
彼女の横顔の曲線は雪見ちゃんと同じなのに、誰も彼女の美しさに気付いていないことに安堵した。
彼女の魅力がわかるのは俺だけだと、自負し自尊した。