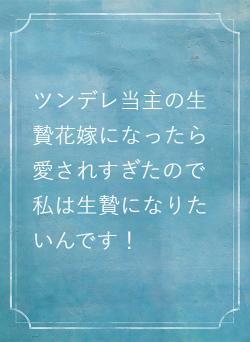彼女の名前は深沢月見。
俺が彼女に向けて言った「雪見ちゃん」は彼女の一卵性双生児の妹の名前だ。
雪見ちゃんと呼んだのはほんの冗談だった。
笑って違うって言ってくれると思ったのに。
俺を思い出すきっかけになると思っただけなのに。
いつも冷静でほとんど感情を表に出すことのない彼女が、あんなにも取り乱して泣き叫ぶなんて。
後悔してもしきれない。愚かな自分を呪いたくなる。
もしかしたら彼女は妹に対してコンプレックスを抱いているのかもしれない。
二人は双子だから顔や体形は瓜二つだけれど、全く違う人間だ。
いつもかわいい笑顔でサラサラロングストレートヘアが印象的な雪見ちゃんは、中学校でも目立つ存在で男子の間でも人気でモテていた。
片や彼女は眼鏡をかけいつも髪を後ろに一つに束ねている所謂地味な感じで、人との関わり合いも自分から避けているように見えた。
そんな彼女を俺が見つめるようになったきっかけは、中学校の階段の踊り場に毎月掲示されていた図書室便りだった。
その頃の俺は親の離婚問題で心が壊れていた。
思春期ど真ん中だったしこの世に永遠の愛なんて存在しないと諦観していた。
人を愛すること、愛されることに懐疑的だった。
別に女嫌いではないから告白されたら誰とでも付き合っていたが、相手の「好き」という言葉も心も信じていなかった。
「好き」はいつしか「嫌い」になる。
だから相手をかわいいとか一緒にいて楽しいとか思っても「好き」になることはなかった。
そんなものはどうせいつか壊れて無くなる。
氷のように冷たく虚無的な心を抱いていることを、友達にも親にも誰にも言えなかった。
本当の自分を隠し繕って過ごす偽りの毎日。
俺が彼女に向けて言った「雪見ちゃん」は彼女の一卵性双生児の妹の名前だ。
雪見ちゃんと呼んだのはほんの冗談だった。
笑って違うって言ってくれると思ったのに。
俺を思い出すきっかけになると思っただけなのに。
いつも冷静でほとんど感情を表に出すことのない彼女が、あんなにも取り乱して泣き叫ぶなんて。
後悔してもしきれない。愚かな自分を呪いたくなる。
もしかしたら彼女は妹に対してコンプレックスを抱いているのかもしれない。
二人は双子だから顔や体形は瓜二つだけれど、全く違う人間だ。
いつもかわいい笑顔でサラサラロングストレートヘアが印象的な雪見ちゃんは、中学校でも目立つ存在で男子の間でも人気でモテていた。
片や彼女は眼鏡をかけいつも髪を後ろに一つに束ねている所謂地味な感じで、人との関わり合いも自分から避けているように見えた。
そんな彼女を俺が見つめるようになったきっかけは、中学校の階段の踊り場に毎月掲示されていた図書室便りだった。
その頃の俺は親の離婚問題で心が壊れていた。
思春期ど真ん中だったしこの世に永遠の愛なんて存在しないと諦観していた。
人を愛すること、愛されることに懐疑的だった。
別に女嫌いではないから告白されたら誰とでも付き合っていたが、相手の「好き」という言葉も心も信じていなかった。
「好き」はいつしか「嫌い」になる。
だから相手をかわいいとか一緒にいて楽しいとか思っても「好き」になることはなかった。
そんなものはどうせいつか壊れて無くなる。
氷のように冷たく虚無的な心を抱いていることを、友達にも親にも誰にも言えなかった。
本当の自分を隠し繕って過ごす偽りの毎日。