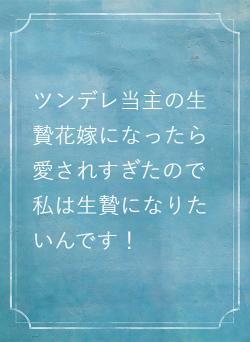「離してください」
彼女の言葉がとても静かに、重く、低く俺に響く。
こんな都会の喧騒の中で、彼女の声以外の音がすべて停止してしまったかのように。
抱きしめている両腕も力強く振り払われて、否応なしに彼女の様子が徒ならぬことに気付いた。
「どうしたの? そんなに顔色変えて……」
「私じゃないから。入谷さんが思い出してほしかったの、私なんかじゃないんです!」
叫ぶように言い放った彼女は泣いていた。
呆気にとられて立ち尽くす俺を残し、彼女は新しいタクシーを捕まえて乗り込もうとした。
「待って!」
後ろから彼女の片手を掴む。
「ごめん、違うんだ! そうじゃなくて……」
「私じゃダメなんです。私じゃ……御馳走までしてもらったのにごめんなさい。お先に失礼します」
彼女は俺の手を振り払うとタクシーに乗り込み去って行った。
遠ざかっていくタクシーのテールランプを見つめながら激しく後悔する。
ああ俺は、なんて馬鹿なことを言ってしまったのだろう。
さっきまでの彼女との楽しかった時間がまるで龍宮城での一時だったかのように、開けてはならない禁断の玉手匣の蓋を開けてしまった俺は一気に現実の世界へと戻らされてしまった。
彼女の言葉がとても静かに、重く、低く俺に響く。
こんな都会の喧騒の中で、彼女の声以外の音がすべて停止してしまったかのように。
抱きしめている両腕も力強く振り払われて、否応なしに彼女の様子が徒ならぬことに気付いた。
「どうしたの? そんなに顔色変えて……」
「私じゃないから。入谷さんが思い出してほしかったの、私なんかじゃないんです!」
叫ぶように言い放った彼女は泣いていた。
呆気にとられて立ち尽くす俺を残し、彼女は新しいタクシーを捕まえて乗り込もうとした。
「待って!」
後ろから彼女の片手を掴む。
「ごめん、違うんだ! そうじゃなくて……」
「私じゃダメなんです。私じゃ……御馳走までしてもらったのにごめんなさい。お先に失礼します」
彼女は俺の手を振り払うとタクシーに乗り込み去って行った。
遠ざかっていくタクシーのテールランプを見つめながら激しく後悔する。
ああ俺は、なんて馬鹿なことを言ってしまったのだろう。
さっきまでの彼女との楽しかった時間がまるで龍宮城での一時だったかのように、開けてはならない禁断の玉手匣の蓋を開けてしまった俺は一気に現実の世界へと戻らされてしまった。