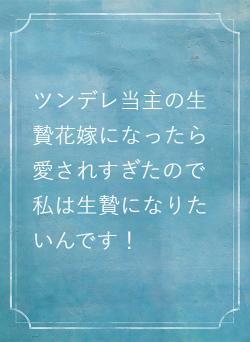本気で言ったのに彼女はきょとんとしているだけ。
落ち込むな! 負けるな俺!
彼女のポーカーフェイスはもし世界大会があるなら優勝するくらいの天下無双なんだよきっと!
「これ見て」
俺は鞄の中から一冊の冊子を取り出した。年に一回発行されている会社の社内報だ。
数ページしかない薄い冊子の最後のページを開いて彼女に見せる。
「これは!」
そのページには、社内で募集された川柳コンクールに応募して優秀賞を獲った彼女の顔写真と川柳が掲載されていた。
顔写真の下には「優秀賞の深沢さん」と書かれている。
「この顔写真と名前見た時にすぐに君だとわかって、懐かしくて会いたくなったんだ。本社で課長に昇進したところでやりがいも見つけられそうになかったし。それなら東京でまた一から頑張ろうかなと思って」
「まさかこれを見てた人がいるなんて! すっごい恥ずかしいんですけど」
「なんで? この川柳なんて最高じゃん。窓の外……」
「きゃああああ! 声に出して読まないでください! 大体この川柳コンクール、応募したの私とうちの営業2課の課長だけだったんですから」
「課長の川柳は佳作だったんだね」
「二人しか応募してなくて私が優秀賞だったから。課長すごい落ち込んでたんです。だからこの話は絶対に課長の前でしないでください!」
「わかったわかった。でもほんと君って変わってないね。才能が豊かでおもしろい」
「入谷さんって、一体私の何を知っていたんですか?」
「それは君が自分で思い出してくれないと。俺、これでもすっげえプライド傷付いてるんだから。あの中学校で俺のこと知らない奴なんていないと思ってたから」
落ち込むな! 負けるな俺!
彼女のポーカーフェイスはもし世界大会があるなら優勝するくらいの天下無双なんだよきっと!
「これ見て」
俺は鞄の中から一冊の冊子を取り出した。年に一回発行されている会社の社内報だ。
数ページしかない薄い冊子の最後のページを開いて彼女に見せる。
「これは!」
そのページには、社内で募集された川柳コンクールに応募して優秀賞を獲った彼女の顔写真と川柳が掲載されていた。
顔写真の下には「優秀賞の深沢さん」と書かれている。
「この顔写真と名前見た時にすぐに君だとわかって、懐かしくて会いたくなったんだ。本社で課長に昇進したところでやりがいも見つけられそうになかったし。それなら東京でまた一から頑張ろうかなと思って」
「まさかこれを見てた人がいるなんて! すっごい恥ずかしいんですけど」
「なんで? この川柳なんて最高じゃん。窓の外……」
「きゃああああ! 声に出して読まないでください! 大体この川柳コンクール、応募したの私とうちの営業2課の課長だけだったんですから」
「課長の川柳は佳作だったんだね」
「二人しか応募してなくて私が優秀賞だったから。課長すごい落ち込んでたんです。だからこの話は絶対に課長の前でしないでください!」
「わかったわかった。でもほんと君って変わってないね。才能が豊かでおもしろい」
「入谷さんって、一体私の何を知っていたんですか?」
「それは君が自分で思い出してくれないと。俺、これでもすっげえプライド傷付いてるんだから。あの中学校で俺のこと知らない奴なんていないと思ってたから」