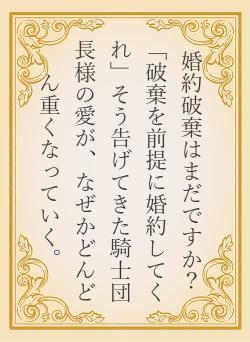就業後連れて来てもらったのは、会社から歩いて数分ほどのおしゃれな居酒屋だった。
完全個室で落ち着いた雰囲気だ。
「やっぱり個室がいいよね」
知ってます。
大学時代のサークルでの飲み会も、できるだけ個室にしてくれと幹事にお願いしていたのを覚えている。
「いらっしゃいませ! おしぼりです。ご注文はそちらのタッチパネルでお願いします」
目の前におしぼりが置かれ、簡単な説明をして店員さんは戻っていった。
そして私はこの後の流れも知っている。
まず先輩はおしぼりで手は拭かない。
おしぼりはそのままにして、後で枝豆などを食べた時に指を拭く用に置いておくのだ。
持参したアルコールティッシュで手を拭くと、もう一つ液晶用ウェットティッシュを取り出しタッチパネルを拭いた。
先輩はいつも鞄に入れていて、これでよくスマホ画面を拭いている。
一通り周りのものを拭き終え、そしてやっと注文をはじめるのだ。
「幸村さん、ハイボールでいい?」
「えっはい。私がハイボール好きなのよく覚えてましたね」
「幸村さんのことは何でも覚えてるよ」
「えっと……ありがとうございます……」
純粋に嬉しかった。
私も、先輩のことはよく覚えている。
二年以上一度も会っていないのに、まるで昨日のことのように思い出せる。
「仕事はどう? やっていけそう?」
「まだ配属されて一日目なのでわかりませんが、先輩の教え方わかりやすいですし、頑張れそうです」
「良かった。無理に誘ってごめんね。どうしても話したいことがあったんだ」
なんだろう。仕事の話だろうか。
それとも……。
黙っていると、真剣な表情で先輩が口を開く。
「ねぇ、幸村さん」
「はい」
「あの頃、僕たちけっこう仲良くしてたと思わない?」
あの頃とは、サークル時代まだ先輩を避ける前のことだろう。
咲子と凌さんと四人でよく一緒にいたし、天体観測も二人で星空を眺めた。
そう、天体観測の日までは。
「なんで急に僕のこと避けるようになったの?」
「避けてる、というわけでは……」
ない、とは言えない。
どう接したらいいのかわからなくて、先輩に嫌われるのが怖くて、距離をとってしまっていた。
「僕、なにかしてしまったのかな?」
「違います! 先輩はなにも悪くないです」
申し訳なさそうに聞いてくる先輩に、急いで否定した。
そこに、ハイボールとビールが運ばれてきた。
隣り合ったジョッキを触れあうギリギリで、乾杯する仕草をする。
そのまま両手でハイボールを持ち、なにも言わず一口飲む。
言えなくて後悔していた。
もうこの先、伝えることなんてないと思っていた。
でも今、目の前に先輩がいる。
あの頃の想いを打ち明けるなら、今しかないよね。
「私、先輩のこと、好きだったんです。あの日、流星群の日、一緒に並んで見てて。それで手が、当たりましたよね。その後先輩にアルコールティッシュ渡されて凄くショックだったんです。だって、私は手を拭きたいなんて思わなかった。むしろ、もっと触れたいって思ってしまったんです。先輩にとっては迷惑なことなのに……」
「……幸村さん、勘違いしてるよ」
「勘違い?」
「手が当たったんじゃないよ。僕が触れたんだ」
「え……」
そう言いながら顔をじっと見つめられる。
「好きな人にだけは触れたいって思うの、変かな」
「好きな、人……」
先輩の言葉に全身の体温が上がっていくのを感じた。
顔が沸騰しそうなくらい熱い。
予想外の言葉に固まっていると、机の上でハイボールを持っていた手に先輩が手を重ねてくる。
「言ったよね。幸村さんなら嫌じゃないって」
「で、でも、アルコールティッシュを渡されて……」
「あれは、幸村さんが嫌がったと思ったんだ。すぐに手をよけられて」
「私も、先輩が嫌だろうと思って」
「僕たち同じこと思ってたんだ」
「そう、みたいですね」
「ねぇ、幸村さん。僕のこと好きだった、って言ったよね。今は? もう、好きじゃない?」
先輩のことは考えないようにしていた。
ずっと気持ちに蓋をしていた。
忘れたと思っていたのに、たった一日でこんなにも思い出してしまう。
ドキドキ、不安、嬉しさ、苦しさ、温かさ。
全てが、たった一日で。
あの頃の、先輩を好きだという気持ちが。
「いえ……そんなことは……」
「じゃあさ、付き合おうよ」
付き合おう、そのストレートな言葉が胸に響く。
大学時代、先輩のことが好きだった。それは胸を張って言える。
でも、付き合うことを具体的に考えたことはあまりなかった。
当時は先輩に嫌われないように、自然にそばにいられるように、そのことで必死だった。
「だめかな?」
「だめじゃ、ありません」
「じゃあ、付き合ってくれる?」
付き合って、どうなるかは自分でも想像がつかない。
でも、心の奥底にしまっていた想いが今、目の前にある。
ここで、また蓋をしてしまえばきっと後悔する。
「…………はい、よろしくお願いします」
小さく頭を下げると、先輩は嬉しそうに顔を綻ばせた。
こんな顔、するんだ。
「良かった。本当はあの流星群の日に言いたかったんだ」
「そう、だったんですか?」
流星群の日、まさか告白しようとしていただなんて考えてもいなかった。
どうして、避けるようなことしてしまったのだろう。
あの時の後悔が消えることはないのかもしれないけど、これからの時間を大切にしていこう。
勇気を出して、好きだったと打ち明けて良かった。
先輩は私の顔を見ながら『明日からが楽しみだ』と呟く。
私は明日から、そんな先輩の隣で仕事が手につくか不安になった。
先輩は、こんなにも積極的で真っ直ぐだっただろうか。
あの頃よりも、もっとドキドキしている私がいた。
完全個室で落ち着いた雰囲気だ。
「やっぱり個室がいいよね」
知ってます。
大学時代のサークルでの飲み会も、できるだけ個室にしてくれと幹事にお願いしていたのを覚えている。
「いらっしゃいませ! おしぼりです。ご注文はそちらのタッチパネルでお願いします」
目の前におしぼりが置かれ、簡単な説明をして店員さんは戻っていった。
そして私はこの後の流れも知っている。
まず先輩はおしぼりで手は拭かない。
おしぼりはそのままにして、後で枝豆などを食べた時に指を拭く用に置いておくのだ。
持参したアルコールティッシュで手を拭くと、もう一つ液晶用ウェットティッシュを取り出しタッチパネルを拭いた。
先輩はいつも鞄に入れていて、これでよくスマホ画面を拭いている。
一通り周りのものを拭き終え、そしてやっと注文をはじめるのだ。
「幸村さん、ハイボールでいい?」
「えっはい。私がハイボール好きなのよく覚えてましたね」
「幸村さんのことは何でも覚えてるよ」
「えっと……ありがとうございます……」
純粋に嬉しかった。
私も、先輩のことはよく覚えている。
二年以上一度も会っていないのに、まるで昨日のことのように思い出せる。
「仕事はどう? やっていけそう?」
「まだ配属されて一日目なのでわかりませんが、先輩の教え方わかりやすいですし、頑張れそうです」
「良かった。無理に誘ってごめんね。どうしても話したいことがあったんだ」
なんだろう。仕事の話だろうか。
それとも……。
黙っていると、真剣な表情で先輩が口を開く。
「ねぇ、幸村さん」
「はい」
「あの頃、僕たちけっこう仲良くしてたと思わない?」
あの頃とは、サークル時代まだ先輩を避ける前のことだろう。
咲子と凌さんと四人でよく一緒にいたし、天体観測も二人で星空を眺めた。
そう、天体観測の日までは。
「なんで急に僕のこと避けるようになったの?」
「避けてる、というわけでは……」
ない、とは言えない。
どう接したらいいのかわからなくて、先輩に嫌われるのが怖くて、距離をとってしまっていた。
「僕、なにかしてしまったのかな?」
「違います! 先輩はなにも悪くないです」
申し訳なさそうに聞いてくる先輩に、急いで否定した。
そこに、ハイボールとビールが運ばれてきた。
隣り合ったジョッキを触れあうギリギリで、乾杯する仕草をする。
そのまま両手でハイボールを持ち、なにも言わず一口飲む。
言えなくて後悔していた。
もうこの先、伝えることなんてないと思っていた。
でも今、目の前に先輩がいる。
あの頃の想いを打ち明けるなら、今しかないよね。
「私、先輩のこと、好きだったんです。あの日、流星群の日、一緒に並んで見てて。それで手が、当たりましたよね。その後先輩にアルコールティッシュ渡されて凄くショックだったんです。だって、私は手を拭きたいなんて思わなかった。むしろ、もっと触れたいって思ってしまったんです。先輩にとっては迷惑なことなのに……」
「……幸村さん、勘違いしてるよ」
「勘違い?」
「手が当たったんじゃないよ。僕が触れたんだ」
「え……」
そう言いながら顔をじっと見つめられる。
「好きな人にだけは触れたいって思うの、変かな」
「好きな、人……」
先輩の言葉に全身の体温が上がっていくのを感じた。
顔が沸騰しそうなくらい熱い。
予想外の言葉に固まっていると、机の上でハイボールを持っていた手に先輩が手を重ねてくる。
「言ったよね。幸村さんなら嫌じゃないって」
「で、でも、アルコールティッシュを渡されて……」
「あれは、幸村さんが嫌がったと思ったんだ。すぐに手をよけられて」
「私も、先輩が嫌だろうと思って」
「僕たち同じこと思ってたんだ」
「そう、みたいですね」
「ねぇ、幸村さん。僕のこと好きだった、って言ったよね。今は? もう、好きじゃない?」
先輩のことは考えないようにしていた。
ずっと気持ちに蓋をしていた。
忘れたと思っていたのに、たった一日でこんなにも思い出してしまう。
ドキドキ、不安、嬉しさ、苦しさ、温かさ。
全てが、たった一日で。
あの頃の、先輩を好きだという気持ちが。
「いえ……そんなことは……」
「じゃあさ、付き合おうよ」
付き合おう、そのストレートな言葉が胸に響く。
大学時代、先輩のことが好きだった。それは胸を張って言える。
でも、付き合うことを具体的に考えたことはあまりなかった。
当時は先輩に嫌われないように、自然にそばにいられるように、そのことで必死だった。
「だめかな?」
「だめじゃ、ありません」
「じゃあ、付き合ってくれる?」
付き合って、どうなるかは自分でも想像がつかない。
でも、心の奥底にしまっていた想いが今、目の前にある。
ここで、また蓋をしてしまえばきっと後悔する。
「…………はい、よろしくお願いします」
小さく頭を下げると、先輩は嬉しそうに顔を綻ばせた。
こんな顔、するんだ。
「良かった。本当はあの流星群の日に言いたかったんだ」
「そう、だったんですか?」
流星群の日、まさか告白しようとしていただなんて考えてもいなかった。
どうして、避けるようなことしてしまったのだろう。
あの時の後悔が消えることはないのかもしれないけど、これからの時間を大切にしていこう。
勇気を出して、好きだったと打ち明けて良かった。
先輩は私の顔を見ながら『明日からが楽しみだ』と呟く。
私は明日から、そんな先輩の隣で仕事が手につくか不安になった。
先輩は、こんなにも積極的で真っ直ぐだっただろうか。
あの頃よりも、もっとドキドキしている私がいた。