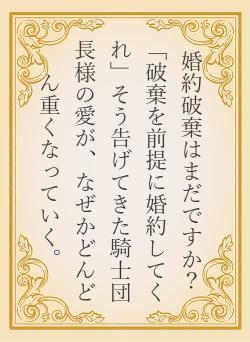頭が痛い。
でも、冷たくて、気持ちいい。
そんな感覚で目が覚めた。
視界には、自分の部屋の天井と――
「――先輩?!」
「目、覚めた? 勝手に部屋に上がってごめんね」
「いえ、それは大丈夫です。それより私……」
「家に入ろうしたときまたふらついて、意識も朦朧としてたからそばにいた方がいいと思って」
なんとなく、思い出してきた気がする。
ふらふらして、先輩の言っていることに返事もできなくて、支えてもらいながら、ベッドまで来たんだ。
それで、横になった瞬間眠ってしまった。
「ご迷惑をおかけしました。もう大丈夫ですので、先輩は帰ってくださいね」
体を起こそうとすると、先輩に止められた。
「幸村さんの大丈夫は信用ならないからね。このまま寝てて」
先輩は優しくフッと笑う。
熱で浮かされているからか、その表情に安心して、私はベッドに体を沈めた。
そして先輩は濡らしたタオルでそっと汗を拭いてくれる。
さっきの冷たい感覚はこれだったんだ。
「ありがとうございます」
「食欲はある? 何か食べた方がいいし、買ってくるよ」
「いいんですか?」
「うん。ちょっと待っててね」
先輩は私の頭を撫でると、部屋を出て行った。
一人になった部屋に寂しさを感じながら、天井を見上げる。
そうだ、今のうちに着替えておこう。
私は重い身体を起こし、さっと部屋着に着替え、またベッドに入る。
最近まともに話せていなかったから、仕事モードじゃない先輩と話せていることがなんだか嬉しい。
迷惑をかけて申し訳ないけど、熱出してよかったかも。
なんて思っていると、先輩がコンビニの袋を持って帰ってきた。
「スポーツドリンクと、レトルトのおかゆと、あとプリン買ってきたんだけど食べられる?」
「ありがとうございます。スポーツドリンク、いただけますか?」
先輩は頷くと、袋からペットボトルを取り出す。
けれど、なぜかそのまま固まってしまった。
ペットボトルを持ったままじっと見て、何か悩んでいる様子だ。
そういえば、先輩はいつも買って来たものを洗ってるんだよね。
このまま私に渡していいか迷っているのかも。
「そのままで大丈夫ですよ」
そう言うと、そっとペットボトルを渡してくれた。
「ありがとうございます。いただきます」
「うん。これは冷蔵庫に入れておくね」
たくさん汗をかいているからか、スポーツドリンクが体に染みる。
先輩はキッチンにコンビニの袋を置いて、手を洗っていた。
そして袋からプリンを取り出し、先ほどのペットボトル同様持ったままじっと見ている。
少し手を震わせたあと、そのまま冷蔵庫に入れた。
本当は洗って入れたかったのかな。
私が食べるものだったら気にしなくてもいいんだけどな。
その後も先輩はそばにいてくれた。
汗を拭いたり、おかゆを温めて食べさせてくれたり。
一生懸命看病してくれているなと感じる。
けれど、私は気付いていた。
何かをするたびに手を洗っていること。
落ち着かない様子でソワソワしていること。
初めて彼女の家に来たら落ち着かないものなのかもしれないけれど、そうではないと思う。
パッと見は片付けているけれど、先月以来大掃除はしていないし、もしかしたら先輩にとっては居心地の悪い空間なのかもしれない。
それに、ずっと服や足元を気にしている。
着替えたいのかもしれないけど、貸してあげられる服なんてここにはない。
狭い部屋だし、来客用のスリッパもない。
お風呂だって、入りたいに決まってる。
私の汗も拭きたくないだろうな。
それでも先輩は何も言わずに、私に尽くしてくれている。
「私の部屋、先輩の部屋みたいに綺麗じゃないですし、いろいろと不便なこともあると思うのでもう帰ってもらって大丈夫ですよ。本当にありがとうございました」
「病人がそんなこと気にしないで。僕は大丈夫だよ」
――これくらいは、我慢できるから。
そう続いているような気がした。
無理をさせているんじゃないかという気持ちが、今わかった。
先輩は私のことを想ってしてくれている。
すごく嬉しいことだ。ありがたいと思う。
でも、嬉しいのと同じくらい申し訳なくて、私は大丈夫だからそんなに無理しないでと思ってしまう。
私が先輩に近づこうと頑張っていたことは、こんなふうに先輩を苦しめていたのかもしれない。
普通にしてほしいという先輩の気持ちが、今ならよくわかる。
わかっているけれど、先輩の大丈夫という言葉に甘えてしまいたくなる。
そばにいて欲しい。
気を遣わないで欲しいという思いと、相手に寄り添いたいという思い。
どちらもわかるからこそ、なんと伝えたらいいかわからなくなる。
でも、だからってもう目を背けてばかりじゃだめだな。
熱が下がったら、伝えよう。
それまでは、甘えてもいいかな。
このわがままは熱のせいにして、もう少しだけ、先輩のそばにいさせてもらおう。
「先輩、手を握ってもいいですか」
こんな汗ばんだ手、嫌だろうな。
けれど先輩はそっと手を握ってくれた。
私が眠ったら、手を洗ってくれていいですからね。
心の中で呟いて、私は目を閉じた。
でも、冷たくて、気持ちいい。
そんな感覚で目が覚めた。
視界には、自分の部屋の天井と――
「――先輩?!」
「目、覚めた? 勝手に部屋に上がってごめんね」
「いえ、それは大丈夫です。それより私……」
「家に入ろうしたときまたふらついて、意識も朦朧としてたからそばにいた方がいいと思って」
なんとなく、思い出してきた気がする。
ふらふらして、先輩の言っていることに返事もできなくて、支えてもらいながら、ベッドまで来たんだ。
それで、横になった瞬間眠ってしまった。
「ご迷惑をおかけしました。もう大丈夫ですので、先輩は帰ってくださいね」
体を起こそうとすると、先輩に止められた。
「幸村さんの大丈夫は信用ならないからね。このまま寝てて」
先輩は優しくフッと笑う。
熱で浮かされているからか、その表情に安心して、私はベッドに体を沈めた。
そして先輩は濡らしたタオルでそっと汗を拭いてくれる。
さっきの冷たい感覚はこれだったんだ。
「ありがとうございます」
「食欲はある? 何か食べた方がいいし、買ってくるよ」
「いいんですか?」
「うん。ちょっと待っててね」
先輩は私の頭を撫でると、部屋を出て行った。
一人になった部屋に寂しさを感じながら、天井を見上げる。
そうだ、今のうちに着替えておこう。
私は重い身体を起こし、さっと部屋着に着替え、またベッドに入る。
最近まともに話せていなかったから、仕事モードじゃない先輩と話せていることがなんだか嬉しい。
迷惑をかけて申し訳ないけど、熱出してよかったかも。
なんて思っていると、先輩がコンビニの袋を持って帰ってきた。
「スポーツドリンクと、レトルトのおかゆと、あとプリン買ってきたんだけど食べられる?」
「ありがとうございます。スポーツドリンク、いただけますか?」
先輩は頷くと、袋からペットボトルを取り出す。
けれど、なぜかそのまま固まってしまった。
ペットボトルを持ったままじっと見て、何か悩んでいる様子だ。
そういえば、先輩はいつも買って来たものを洗ってるんだよね。
このまま私に渡していいか迷っているのかも。
「そのままで大丈夫ですよ」
そう言うと、そっとペットボトルを渡してくれた。
「ありがとうございます。いただきます」
「うん。これは冷蔵庫に入れておくね」
たくさん汗をかいているからか、スポーツドリンクが体に染みる。
先輩はキッチンにコンビニの袋を置いて、手を洗っていた。
そして袋からプリンを取り出し、先ほどのペットボトル同様持ったままじっと見ている。
少し手を震わせたあと、そのまま冷蔵庫に入れた。
本当は洗って入れたかったのかな。
私が食べるものだったら気にしなくてもいいんだけどな。
その後も先輩はそばにいてくれた。
汗を拭いたり、おかゆを温めて食べさせてくれたり。
一生懸命看病してくれているなと感じる。
けれど、私は気付いていた。
何かをするたびに手を洗っていること。
落ち着かない様子でソワソワしていること。
初めて彼女の家に来たら落ち着かないものなのかもしれないけれど、そうではないと思う。
パッと見は片付けているけれど、先月以来大掃除はしていないし、もしかしたら先輩にとっては居心地の悪い空間なのかもしれない。
それに、ずっと服や足元を気にしている。
着替えたいのかもしれないけど、貸してあげられる服なんてここにはない。
狭い部屋だし、来客用のスリッパもない。
お風呂だって、入りたいに決まってる。
私の汗も拭きたくないだろうな。
それでも先輩は何も言わずに、私に尽くしてくれている。
「私の部屋、先輩の部屋みたいに綺麗じゃないですし、いろいろと不便なこともあると思うのでもう帰ってもらって大丈夫ですよ。本当にありがとうございました」
「病人がそんなこと気にしないで。僕は大丈夫だよ」
――これくらいは、我慢できるから。
そう続いているような気がした。
無理をさせているんじゃないかという気持ちが、今わかった。
先輩は私のことを想ってしてくれている。
すごく嬉しいことだ。ありがたいと思う。
でも、嬉しいのと同じくらい申し訳なくて、私は大丈夫だからそんなに無理しないでと思ってしまう。
私が先輩に近づこうと頑張っていたことは、こんなふうに先輩を苦しめていたのかもしれない。
普通にしてほしいという先輩の気持ちが、今ならよくわかる。
わかっているけれど、先輩の大丈夫という言葉に甘えてしまいたくなる。
そばにいて欲しい。
気を遣わないで欲しいという思いと、相手に寄り添いたいという思い。
どちらもわかるからこそ、なんと伝えたらいいかわからなくなる。
でも、だからってもう目を背けてばかりじゃだめだな。
熱が下がったら、伝えよう。
それまでは、甘えてもいいかな。
このわがままは熱のせいにして、もう少しだけ、先輩のそばにいさせてもらおう。
「先輩、手を握ってもいいですか」
こんな汗ばんだ手、嫌だろうな。
けれど先輩はそっと手を握ってくれた。
私が眠ったら、手を洗ってくれていいですからね。
心の中で呟いて、私は目を閉じた。