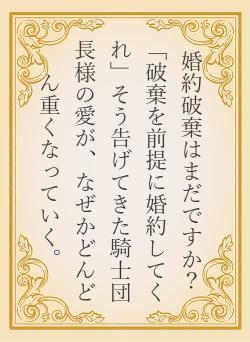翌日、先輩はいつも通りだった。
何事もなかったように仕事をこなす。
結局、私は何も変えることができなかった。
もう諦めるしかないのかもしれない。
そもそも私は新入社員だ。
まだ一人前に仕事をこなせないのに、恋にかまけてばかりじゃだめだ。
そう自分に言い聞かせて、先輩とのことは考えず、仕事に励むことにした。
仕事をして、家に帰るだけの日々。
ありきたりな日常が過ぎていった。
そんなある日、社食で一人昼食を食べていると、目の前の席に日高さんが座った。
「ここ、いいかしら?」
聞いているけれど、お箸を持ち、もうここで食べる気満々なようだ。
「はい……」
日高さんはお蕎麦を啜りながら、私を見る。
「あなたたち、何かあったの?」
あなたたち、とは私と先輩のことだよね。
何かあったと言えばあった。
でも、こんなこと日高さんに言ってもいいのだろうか。
「この前ね、松永くん泣いてた」
「え? 泣いてた?」
「かもしれない」
「かも、しれない……」
びっくりした。
本当に泣いていたかははっきりしてないんだ。
でも、どうして? いつのことだろう。
それって、私のことと関係あるのかな。
私の考えていることがわかるのか、日高さんは話を続ける。
「先月、けっこう遅くまで残ってた日あったでしょ? 私も残ってたの。販促イベントの準備で営業部にいたんだけど、松永くんが肩を震わせて歩いてたのを見かけたのよ。声をかけられる雰囲気でもなかったし、はっきりとはわからないけど」
「そう……だったんですね」
あの日のことだよね。
同じフロアにはだれもいなかったから、日高さんが残っているとは思っていなかった。
あの日、怒らせてしまったと思っていたけど、そうじゃなかった?
もし泣いていたのだとしたら、先輩をひどく傷つけてしまったということ。
いや、そうじゃなくても私はきっと、先輩を悲しませた。
「私が口を挟むことでもないし、何も言わないつもりだったんだけど、最近見てられなくて」
「気を遣わせてしまいすみません……」
「謝る必要はないわよ。でも幸村さん、あなたすごく疲れた顔してるわよ? けっこう残業もしてるんじゃない? 体調には気をつけてね」
「はい、ありがとうございます」
日高さんはごちそうさま、と手を合わせ、トレーを持って戻っていった。
きっと先輩のことが好きなはずなのに、私のことを気にかけてくれるなんて優しい人だ。
それにしても、私は見てわかるほどに疲れた顔をしているのだろうか。
言われてみれば、たしかに最近残業が続いて少し疲れてるかも。
でも、顔に出ていたなんてだめだな。
午後からは気合いを入れて頑張ろう。
◇ ◇ ◇
気合いを入れたつもりだったのに、なんだか頭がボーっとして、全然はかどらなかった。
心なしか、寒気もするような気がする。
自分が思っていた以上に体調が良くないのかも。
明日が土曜日で良かった。
早く仕事を終わらせて、帰ってゆっくり休もう。
そしてなんとか今日の仕事を終わらせ、席を立つ。
すると、視界が揺らいだ。
あ、倒れる――
と思ったけれど、先輩が抱きとめてくれた。
「大丈夫?」
「すみません、大丈夫です」
「熱あるでしょ。体、すごく熱いよ」
やっぱり、熱あるんだ。
そうじゃないかとは思っていたけど、気づかないふりをしていた。
「帰って、休みますね。お疲れ様でした」
頭を下げて帰ろうとしたけれど、腕を掴まれた。
「送っていく」
「大丈夫ですよ。一人で帰れるので」
「そんな状態で放っておけるわけないよ」
先輩は自分の荷物をまとめると、私の手を引いて歩き出す。
「ありがとうございます……」
「体調が悪いの気付けなくてごめん。つらかったら言ってくれたらよかったのに」
「明日休みですし、今日一日くらい頑張れるかなと」
「幸村さんは、ちょっと頑張りすぎだよ」
心配してくれているような声に、胸がギュッとなる。
これは後輩として心配してくれているのだろうか。
それとも、彼女として?
私はまだ、彼女なんだろうか……。
先輩の優しさが、苦しい。
でも、それ以上に嬉しくて、先輩の手の温もりに安心した。
「幸村さん、ごめんね」
「どうして謝るんですか?」
「この前、ひどいこと言ったから。あの後すごく後悔してたんだ。でも、どうやって僕の気持ちを伝えたらいいかわからなくて、何も言えなかった」
先輩も、私と同じだったんだ。
上手く伝えられない気持ち。
どうすればいいかわからなくて、苦しかったのかもしれない。
それがわかっただけでも良かった。
「私も、すみませんでした」
「幸村さんは、何も悪くないよ」
お互いの気持ちを伝え合うことは難しい。
でも、まだきっと私たちは想い合えている。握られた手の温もりから、そう感じた。
体調が良くなったら、もう一度先輩とよく話そう。
そのまま部屋の前まで送ってくれ、お礼を言う。
「一人で大丈夫?」
「はい。寝たら大丈夫だと思うので」
「じゃあ、お大事にね」
「送っていただいてありがとうございました」
頭を下げるけれど、先輩はまだ帰ろうとしない。
私が部屋に入るまで見送ってくれるのかな?
だったら早くしないと。
鞄から鍵を取り出し、ドアを開ける。
中に入ろうとした瞬間、また視界がぐらついた。
「幸村さん!」
先輩の焦る声が聞こえたけれど、頭が回らなくて上手く返事ができなかった。
何事もなかったように仕事をこなす。
結局、私は何も変えることができなかった。
もう諦めるしかないのかもしれない。
そもそも私は新入社員だ。
まだ一人前に仕事をこなせないのに、恋にかまけてばかりじゃだめだ。
そう自分に言い聞かせて、先輩とのことは考えず、仕事に励むことにした。
仕事をして、家に帰るだけの日々。
ありきたりな日常が過ぎていった。
そんなある日、社食で一人昼食を食べていると、目の前の席に日高さんが座った。
「ここ、いいかしら?」
聞いているけれど、お箸を持ち、もうここで食べる気満々なようだ。
「はい……」
日高さんはお蕎麦を啜りながら、私を見る。
「あなたたち、何かあったの?」
あなたたち、とは私と先輩のことだよね。
何かあったと言えばあった。
でも、こんなこと日高さんに言ってもいいのだろうか。
「この前ね、松永くん泣いてた」
「え? 泣いてた?」
「かもしれない」
「かも、しれない……」
びっくりした。
本当に泣いていたかははっきりしてないんだ。
でも、どうして? いつのことだろう。
それって、私のことと関係あるのかな。
私の考えていることがわかるのか、日高さんは話を続ける。
「先月、けっこう遅くまで残ってた日あったでしょ? 私も残ってたの。販促イベントの準備で営業部にいたんだけど、松永くんが肩を震わせて歩いてたのを見かけたのよ。声をかけられる雰囲気でもなかったし、はっきりとはわからないけど」
「そう……だったんですね」
あの日のことだよね。
同じフロアにはだれもいなかったから、日高さんが残っているとは思っていなかった。
あの日、怒らせてしまったと思っていたけど、そうじゃなかった?
もし泣いていたのだとしたら、先輩をひどく傷つけてしまったということ。
いや、そうじゃなくても私はきっと、先輩を悲しませた。
「私が口を挟むことでもないし、何も言わないつもりだったんだけど、最近見てられなくて」
「気を遣わせてしまいすみません……」
「謝る必要はないわよ。でも幸村さん、あなたすごく疲れた顔してるわよ? けっこう残業もしてるんじゃない? 体調には気をつけてね」
「はい、ありがとうございます」
日高さんはごちそうさま、と手を合わせ、トレーを持って戻っていった。
きっと先輩のことが好きなはずなのに、私のことを気にかけてくれるなんて優しい人だ。
それにしても、私は見てわかるほどに疲れた顔をしているのだろうか。
言われてみれば、たしかに最近残業が続いて少し疲れてるかも。
でも、顔に出ていたなんてだめだな。
午後からは気合いを入れて頑張ろう。
◇ ◇ ◇
気合いを入れたつもりだったのに、なんだか頭がボーっとして、全然はかどらなかった。
心なしか、寒気もするような気がする。
自分が思っていた以上に体調が良くないのかも。
明日が土曜日で良かった。
早く仕事を終わらせて、帰ってゆっくり休もう。
そしてなんとか今日の仕事を終わらせ、席を立つ。
すると、視界が揺らいだ。
あ、倒れる――
と思ったけれど、先輩が抱きとめてくれた。
「大丈夫?」
「すみません、大丈夫です」
「熱あるでしょ。体、すごく熱いよ」
やっぱり、熱あるんだ。
そうじゃないかとは思っていたけど、気づかないふりをしていた。
「帰って、休みますね。お疲れ様でした」
頭を下げて帰ろうとしたけれど、腕を掴まれた。
「送っていく」
「大丈夫ですよ。一人で帰れるので」
「そんな状態で放っておけるわけないよ」
先輩は自分の荷物をまとめると、私の手を引いて歩き出す。
「ありがとうございます……」
「体調が悪いの気付けなくてごめん。つらかったら言ってくれたらよかったのに」
「明日休みですし、今日一日くらい頑張れるかなと」
「幸村さんは、ちょっと頑張りすぎだよ」
心配してくれているような声に、胸がギュッとなる。
これは後輩として心配してくれているのだろうか。
それとも、彼女として?
私はまだ、彼女なんだろうか……。
先輩の優しさが、苦しい。
でも、それ以上に嬉しくて、先輩の手の温もりに安心した。
「幸村さん、ごめんね」
「どうして謝るんですか?」
「この前、ひどいこと言ったから。あの後すごく後悔してたんだ。でも、どうやって僕の気持ちを伝えたらいいかわからなくて、何も言えなかった」
先輩も、私と同じだったんだ。
上手く伝えられない気持ち。
どうすればいいかわからなくて、苦しかったのかもしれない。
それがわかっただけでも良かった。
「私も、すみませんでした」
「幸村さんは、何も悪くないよ」
お互いの気持ちを伝え合うことは難しい。
でも、まだきっと私たちは想い合えている。握られた手の温もりから、そう感じた。
体調が良くなったら、もう一度先輩とよく話そう。
そのまま部屋の前まで送ってくれ、お礼を言う。
「一人で大丈夫?」
「はい。寝たら大丈夫だと思うので」
「じゃあ、お大事にね」
「送っていただいてありがとうございました」
頭を下げるけれど、先輩はまだ帰ろうとしない。
私が部屋に入るまで見送ってくれるのかな?
だったら早くしないと。
鞄から鍵を取り出し、ドアを開ける。
中に入ろうとした瞬間、また視界がぐらついた。
「幸村さん!」
先輩の焦る声が聞こえたけれど、頭が回らなくて上手く返事ができなかった。