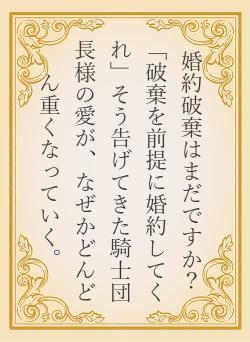なんでもない、平凡な日常が続いていた。
先輩とは、当たり障りなく一緒に仕事をするだけ。
それ以上でも以下でもなく、休みの日に会うこともなかった。
連絡もほとんどとっていない。
仕事が落ち着けばデートに誘おうと思っていたのに、できないままだ。
その上、一緒に屋上でお弁当を食べられなくなっていた。
屋上にあるタンクの入れ替え工事でしばらくの間立ち入り禁止になったのだ。
佐久間くんと昼休みを過ごしていた流れで自然と別々に食べるようになり、私は以前のように社食で食べたりコンビニや売店で買ったりしている。
ちなみに佐久間くんは企画のことで忙しくしているらしい。
会社での、唯一の二人きりの時間もなくなった。
仕事での必要最低限の会話をするだけ。
まるで、本当にただの職場の先輩後輩のようだった。
「幸村さん、これ入力お願いできる?」
「わかりました」
「ありがとう。僕、少し総務部に行ってくるから」
先輩は席を立ち、隣の総務部へと向かう。
無意識に目で追ってしまっていた。
先輩は、いたって普通だ。
普通過ぎて、配属された初日に言われたことが遠い昔のように感じる。
『嫌じゃないよ、幸村さんなら』
『幸村さんが入社してくるの楽しみにしてたんだ』
緊張して、でも嬉しくて、まさか告白されるなんて思っていなかった。
先輩と過ごす日々は楽しくて、もっと好きになった。
でも、こんなに苦しい気持ちになるなんて知らなかった。
――あ、先輩笑ってる。
隣には日高さんがいる。仕事の話をしているのではないのだろうか。
最近、私に笑いかけてくれなくなったな。
あの、フッと笑う表情が恋しくてたまらない――
そんなこと、言えないけれど。
こうして見ていると、本当にお似合いの二人だ。
どこか疎外感を感じる。
先輩の言っていた、惨めだという言葉が今ならわかる気がする。
私よりも、日高さんの方が先輩にふさわしいのではないかと。
先輩は『いつもちょうど良い距離で僕の側に居てくれる、それが凄く心地良かった』と私を好きになったきっかけを話してくれた。
でもそれって、日高さんにも言えることなのではないだろうか。
先輩に対する気遣いができていて、ちょうど良い距離感で接している。
それに、先輩も信頼を置いている――
私、何を考えているんだろう。
仕事しないと。
◇ ◇ ◇
「先輩、お先に失礼します」
「うん、お疲れ様。もう遅いから気を付けて帰ってね」
「ありがとうございます。お疲れ様でした」
金曜日、挨拶を交わして会社を出る。
気を付けてね、なんていうちょっとした優しさが嬉しくもあり、悲しくもある。
最後に一緒に帰ったあの日から、私たちの距離は遠くなっていた。
あれから佐久間くんとの話に触れることもなく、何事もなかったかのように過ごしている。
先輩との関係も、なかったかのように。
別れ話をしたわけではない。
喧嘩、という感じでもない。
でも、これって付き合っていると言えるのだろうか。
恋愛経験の浅い私には、この状況がわからない。
「自然消滅ってやつじゃないよね……」
このまま、終わってしまうのだろうか。
考えれば考えるほど不安になってくる。
それなのに、先輩には何も言えない自分が嫌になる。
お似合いだって言われてしまったのは、私と佐久間くんが仲良くし過ぎていたせいだろうか。
そんなつもりは全然なかった。
先輩に嫌な思いをさせてしまったのなら、謝らないと。
でももし、もう私のことを好きじゃないと言われたら?
私の行動に呆れて、何も言えないのだとしたら?
ここ最近、ずっとそんなことばかり考えている。
ああ、もうだめだ。
私は家に帰り、咲子に連絡しようと鞄からスマホを取り出した。
すると、タイミングよく咲子から電話がかかってきた。
通話ボタンをスクロールして、電話に出る。
「咲子、ちょうどよかった私も電話しようと――」
「め゛い゛ぃぃぃ~」
けれど、咲子の声はかすれ、鼻声だった。
私の話よりも、咲子の状況が気になる。
「どうしたの? 泣いてる? なにかあった?」
外からかけてきているのだろうか。
微かに風の音が聞こえる。
それ以上に鼻をすする音が気になるけれど。
「私、凌と別れるかも……」
咲子が泣いているなんて珍しいと思ったら、まさかの内容だった。
「別れる?! ってなんで?!」
「芽衣、私どうしたらよかったのかなぁ」
「咲子、今どこにいるの?」
先輩とは、当たり障りなく一緒に仕事をするだけ。
それ以上でも以下でもなく、休みの日に会うこともなかった。
連絡もほとんどとっていない。
仕事が落ち着けばデートに誘おうと思っていたのに、できないままだ。
その上、一緒に屋上でお弁当を食べられなくなっていた。
屋上にあるタンクの入れ替え工事でしばらくの間立ち入り禁止になったのだ。
佐久間くんと昼休みを過ごしていた流れで自然と別々に食べるようになり、私は以前のように社食で食べたりコンビニや売店で買ったりしている。
ちなみに佐久間くんは企画のことで忙しくしているらしい。
会社での、唯一の二人きりの時間もなくなった。
仕事での必要最低限の会話をするだけ。
まるで、本当にただの職場の先輩後輩のようだった。
「幸村さん、これ入力お願いできる?」
「わかりました」
「ありがとう。僕、少し総務部に行ってくるから」
先輩は席を立ち、隣の総務部へと向かう。
無意識に目で追ってしまっていた。
先輩は、いたって普通だ。
普通過ぎて、配属された初日に言われたことが遠い昔のように感じる。
『嫌じゃないよ、幸村さんなら』
『幸村さんが入社してくるの楽しみにしてたんだ』
緊張して、でも嬉しくて、まさか告白されるなんて思っていなかった。
先輩と過ごす日々は楽しくて、もっと好きになった。
でも、こんなに苦しい気持ちになるなんて知らなかった。
――あ、先輩笑ってる。
隣には日高さんがいる。仕事の話をしているのではないのだろうか。
最近、私に笑いかけてくれなくなったな。
あの、フッと笑う表情が恋しくてたまらない――
そんなこと、言えないけれど。
こうして見ていると、本当にお似合いの二人だ。
どこか疎外感を感じる。
先輩の言っていた、惨めだという言葉が今ならわかる気がする。
私よりも、日高さんの方が先輩にふさわしいのではないかと。
先輩は『いつもちょうど良い距離で僕の側に居てくれる、それが凄く心地良かった』と私を好きになったきっかけを話してくれた。
でもそれって、日高さんにも言えることなのではないだろうか。
先輩に対する気遣いができていて、ちょうど良い距離感で接している。
それに、先輩も信頼を置いている――
私、何を考えているんだろう。
仕事しないと。
◇ ◇ ◇
「先輩、お先に失礼します」
「うん、お疲れ様。もう遅いから気を付けて帰ってね」
「ありがとうございます。お疲れ様でした」
金曜日、挨拶を交わして会社を出る。
気を付けてね、なんていうちょっとした優しさが嬉しくもあり、悲しくもある。
最後に一緒に帰ったあの日から、私たちの距離は遠くなっていた。
あれから佐久間くんとの話に触れることもなく、何事もなかったかのように過ごしている。
先輩との関係も、なかったかのように。
別れ話をしたわけではない。
喧嘩、という感じでもない。
でも、これって付き合っていると言えるのだろうか。
恋愛経験の浅い私には、この状況がわからない。
「自然消滅ってやつじゃないよね……」
このまま、終わってしまうのだろうか。
考えれば考えるほど不安になってくる。
それなのに、先輩には何も言えない自分が嫌になる。
お似合いだって言われてしまったのは、私と佐久間くんが仲良くし過ぎていたせいだろうか。
そんなつもりは全然なかった。
先輩に嫌な思いをさせてしまったのなら、謝らないと。
でももし、もう私のことを好きじゃないと言われたら?
私の行動に呆れて、何も言えないのだとしたら?
ここ最近、ずっとそんなことばかり考えている。
ああ、もうだめだ。
私は家に帰り、咲子に連絡しようと鞄からスマホを取り出した。
すると、タイミングよく咲子から電話がかかってきた。
通話ボタンをスクロールして、電話に出る。
「咲子、ちょうどよかった私も電話しようと――」
「め゛い゛ぃぃぃ~」
けれど、咲子の声はかすれ、鼻声だった。
私の話よりも、咲子の状況が気になる。
「どうしたの? 泣いてる? なにかあった?」
外からかけてきているのだろうか。
微かに風の音が聞こえる。
それ以上に鼻をすする音が気になるけれど。
「私、凌と別れるかも……」
咲子が泣いているなんて珍しいと思ったら、まさかの内容だった。
「別れる?! ってなんで?!」
「芽衣、私どうしたらよかったのかなぁ」
「咲子、今どこにいるの?」