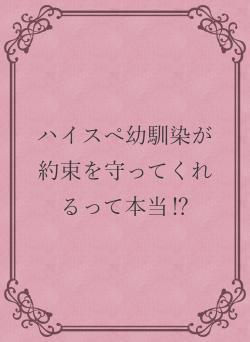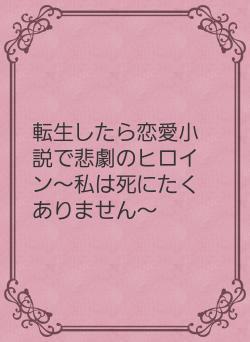父親は姿を現した杏に微笑みかけた。
「迎えにきたぞ杏、さぁ家に帰ろう。皆も待っている…杏に謝りたいと紗代も言っているぞ。」
「…お父様…私はもう…」
杏が父親の申し出を断ろうとすると、父親は杏の腕を掴んだ。
「さぁ、帰ろう!」
拒む杏を父親はグイグイと引っ張りお屋敷を出ようとした。
女性たちが杏たちを止めようとした時、父親は黒く丸い玉をお屋敷に向かって投げつけた。
するとドンという爆発音と火が出たのだった。
女性たちが慌てて火を消そうとした騒ぎに紛れて父親はお屋敷から杏を連れて出てしまった。
お屋敷を出た父親は、なぜか財前家には向かわず山の奥へと歩いているようだ。
「お父様、どちらに向かうのですか…」
杏に向かって振り返った父親は、先程とは打って変わって恐い顔をしている。
「杏、悪いがお前には死んでもらう。」
「…そ…そんな…私を騙したのですか?」
父親はふっと半分口角を上げて馬鹿にしたような笑みを浮かべた。
「皆がお前を待っているとでも思ったのか?…お前が邪魔なんだよ。お前さえいなくなれば、神様は紗代を嫁に迎えてくれるはずだ。」
「紗代様はご縁談が決まったのではないでしょうか。」
「五条家も悪くないが、神の嫁になれたらその方が良い。…それに紗代はあの美しい神様を気にいっているんだ。」
「…それで私を殺しに来たのですね。」